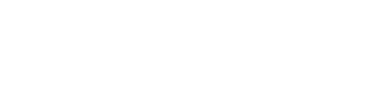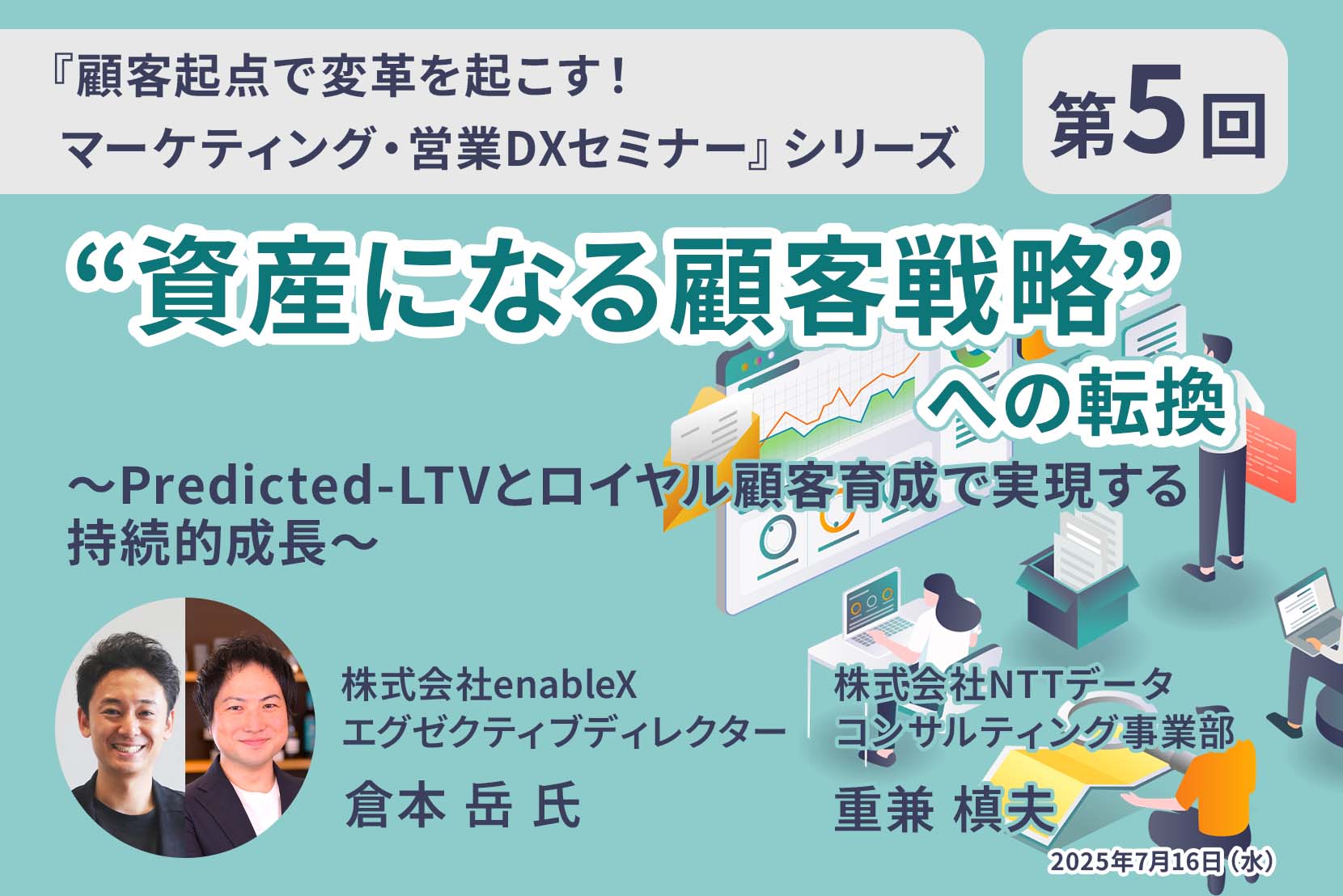自社の健康食品が売れない理由は何?売り方とECモール別の戦略とは

健康食品市場は拡大を続け、多くの企業が新規参入を果たしています。
しかし、「良い商品を作ったのに売れない」「競合に埋もれてしまう」といった悩みを抱える企業も少なくありません。
本記事では、健康食品が売れない主な原因を明らかにしながら、売上を伸ばすために必要なブランディングや販売促進施策、ECモール別の戦略を詳しく解説します。
健康食品を展開するうえでのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
健康食品が売れない理由とその背景
健康食品業界は年々成長を遂げている一方で、自社商品がなかなか売れないと感じている事業者は少なくありません。本見出しでは、売上が伸び悩む要因について3つの代表的な視点から整理します。
市場の成熟と競合商品の増加
近年の健康意識の高まりとともに、健康食品市場は拡大の一途をたどってきました。その結果、数多くの企業が参入し、商品の種類も急増しています。市場が成熟することで、似たような商品が乱立し、消費者にとっては選択肢が多すぎる状況となっています。さらに、価格競争が激化し、広告費の投入やプロモーション合戦も当たり前になってきました。こうした中で、自社商品の独自性を打ち出すことが難しくなり、売上が思うように伸びない要因となっているのです。
消費者の不信感と情報過多の問題
現代の消費者は、インターネットやSNSを通じて多くの情報を得ることができます。一方で、その情報の正確性や信頼性には大きな差があります。過去に報道された過剰表示や虚偽広告の問題により、健康食品全体に対する不信感を持っている人も少なくありません。また、「〇〇に効く」「絶対に痩せる」など過剰なキャッチコピーに慣れてしまった消費者にとっては、言葉だけでは商品の価値が伝わらないのです。誠実な情報発信と、実感に基づく訴求が求められています。
商品の機能・効果が伝わりにくいパッケージや訴求内容
健康食品は「健康をサポートする」という抽象的な目的を持つため、視覚的な訴求や言語表現において、消費者に具体的な価値が伝わりづらい商品も多く見られます。特にパッケージデザインがシンプルすぎたり、効果や使用シーンが明確でない場合は、消費者が「自分に必要かどうか」を判断しにくく、購買に至らない可能性が高まります。パッケージや販促物においても、対象顧客の理解レベルに合わせたわかりやすい言葉とビジュアルが求められるでしょう。
健康食品市場の現状と消費動向
健康食品市場は近年、急速に拡大を続けており、健康志向の高まりやライフスタイルの変化とともに、多様な製品が登場しています。本見出しでは、市場の規模と動向、そして消費者ニーズの多様化について整理します。
市場規模とセグメント別の成長傾向
健康食品の市場は、日本国内で1兆2,382億円(2024年予測)とされており、前年とほぼ同水準を維持しています。中でも「機能性表示食品」や「栄養補助食品」など、効果や安全性が明確な製品の人気が続いています(出典:commercepick.com)。
セグメント別では、以下の傾向が見られます:
- 高齢者向けの骨や関節サポート商品
- 働き盛り世代向けのエナジー系サプリメント
- 美容志向層向けのコラーゲン・ビタミン商品
- ダイエット層向けの糖質カット系食品
特定の効果を狙ったパーソナルな製品へのニーズが高まりつつあり、それぞれのターゲット層に合った訴求が必要とされています。
消費者ニーズの多様化とターゲットの分散
消費者の健康への意識は、年齢や性別、ライフスタイルにより大きく異なります。たとえば:
- 若年層は「手軽さ」「美容効果」「SNS映え」などに関心
- 子育て世代は「家族の健康」「時短」などの実用性重視
- 高齢者は「安全性」「医師推奨」「飲みやすさ」などを重視
このように、従来の「万人向け商品」では届きづらい時代となりつつあり、ターゲットごとのマーケティング設計が求められます。
注目される成分や訴求ワードの変化
以下のようなキーワードが、特に注目を集めています:
- 機能性表示食品:科学的根拠に基づいた効果を表示できる制度。
- プロバイオティクス・プレバイオティクス:腸内環境改善による免疫力向上や美肌効果。
- ビタミンD、CBD、アスタキサンチンなど、成分に対するエビデンス重視の傾向。
また、「ナチュラル」「オーガニック」「グルテンフリー」といった、食の安心・安全への志向も強くなっており、パッケージ上の表示やブランドサイトでの説明が鍵となります。
健康食品におけるブランディングの重要性
競争が激しい健康食品市場において、単なる機能訴求だけでは消費者に選ばれにくくなっています。ここでは、ブランドとしての信頼を得るために必要な3つの視点からブランディングのあり方を解説します。
ブランドストーリーによる信頼構築
現代の消費者は、商品そのものだけでなく、その背後にある“ストーリー”にも価値を感じます。「どのような想いで開発されたのか」「開発者の信念は何か」といった情報が、信頼感や共感を生むのです。たとえば、「創業者が家族の健康を守るために開発した」といった背景があると、それに共感するユーザーの購入動機となる可能性があります。
用語補足 – ブランドストーリーとは
ブランドストーリーとは、企業や商品がどのような想いや経緯で誕生し、どのようなビジョンをもっているのかを物語として伝えるマーケティング手法です。顧客との信頼関係構築やブランド価値の向上に寄与します。
成分や製造過程の「透明性」が選ばれる鍵
消費者の信頼を得るためには、「成分が何でできているのか」「どのような工程で製造されているのか」といった透明性が不可欠です。第三者機関の認証取得や、製造工程の動画公開などが有効です。特に健康食品の場合は安全性が重要視されるため、トレーサビリティの確保が大きな差別化要因になります。
用語補足 – トレーサビリティとは
トレーサビリティとは、食品が「いつ、どこで、誰によって、どのように」生産・加工・流通されたかを追跡可能にする仕組みです。消費者への安心提供に直結する重要な要素です。
デザイン・ネーミングによる差別化の強化
同じ機能性を持つ商品であっても、ネーミングやパッケージデザインが異なるだけで売れ行きに大きな差が出ます。ユーザーの目を惹き、かつ購買意欲を喚起するには、機能性を端的に伝える名称や、信頼感と親しみやすさを兼ね備えたデザインが鍵となります。加えて、「漢方由来」や「オーガニック認証」などのアイコン表示も、選ばれる理由の一つになります。
効果的な販売促進戦略の立案
健康食品市場において成果を上げるためには、ただ商品を作るだけではなく、「誰に」「どのように」届けるかを明確にする戦略的なプロモーションが必要です。本見出しでは、販売促進の鍵となる3つの視点から解説します。
USP(独自の強み)の再定義
数ある健康食品の中で「選ばれる」ためには、他社製品との差別化が必要です。そのためには、USP(Unique Selling Proposition=独自の強み)の明確化が不可欠です。例えば「腸内環境に特化した特許成分を配合」「スポーツ選手監修」「アレルゲンフリー対応」など、具体的な強みを言語化し、販促活動に活用することが求められます。
見出し4:用語補足 – USP(独自の強み)とは
USPとは、自社製品やサービスが他社と異なり、消費者にとって明確な利点を提供する要素のことを指します。商品の価値を短く、分かりやすく伝えるキャッチコピーに活用されます。
セグメント別マーケティング(高齢者、子育て世代、アスリートなど)
消費者の属性ごとにニーズは大きく異なるため、セグメントごとのアプローチが必要です。たとえば:
- 高齢者層:関節・骨・目の健康訴求、摂取しやすい形状(ソフトカプセル等)
- 子育て世代:育児・家族の健康サポート、安全性への配慮(無添加・国産など)
- アスリート:疲労回復、筋肉維持、プロ仕様の成分設計
これらのニーズに応じたLP(ランディングページ)や広告クリエイティブの最適化が求められます。
購買行動を促すキャンペーン・価格設計
健康食品は継続してこそ効果を実感できる商品です。そのため、初回トライアルや定期購入への導線設計が重要です。具体的には:
- 初回半額+送料無料キャンペーン
- 「3個まとめ買いで1個無料」などのセット販売
- 「友人紹介で両者にポイント付与」などの紹介プログラム
これらを通じて購買のハードルを下げ、継続購入につなげることが可能です。
(前略)
オンラインとオフラインの販促チャネル活用
健康食品の販売チャネルは年々多様化しており、オンラインとオフラインの両方を活用した統合的な戦略が求められます。本見出しでは、各チャネルの特徴と活用方法について詳しく解説します。
自社EC・Amazon・楽天などの最適化
健康食品の販路としては、自社ECサイトの運営と大手ECモール(Amazon、楽天市場など)への出店の両輪が重要です。それぞれに強みと特徴があるため、目的に応じた戦略設計が求められます。
まず、自社ECではブランディングの自由度が高く、顧客データの収集やCRM(顧客関係管理)にも活かしやすいのがメリットです。サイト内ではブランドの世界観をしっかり伝えるビジュアル設計や、継続購入に誘導するUI/UXがポイントとなります。また、定期購入導線や商品比較ページ、レビュー掲載などを強化することで、購買率を高めることができます。
一方、Amazonは「検索→即購入」というスピード重視のユーザーが多いため、検索対策(SEO)やレビュー数・評価の管理が極めて重要です。特にAmazon広告(スポンサープロダクト)を活用して検索上位に表示される工夫も必要です。また、FBA(フルフィルメント by Amazon)を使うことで配送や在庫管理の負担軽減にもつながります。
楽天市場では、モール独自のイベント(楽天スーパーSALE、買い回りキャンペーンなど)を活かした販促が有効です。また、ポイント施策の設計が売上に直結するため、利益率を見ながら戦略的にポイント還元を実施する必要があります。楽天内SEO(検索対策)としては、商品名や商品説明にキーワードを効果的に配置することも重要です。
これらに加え、Yahoo!ショッピングやQoo10、最近ではau PAY マーケットなど、多様なモールごとに最適化された対策を取ることで、販路全体のパフォーマンスが底上げされます。
- 自社EC:ブランド価値の訴求とLTV向上に強み
- Amazon:利便性と信頼を重視した購買層への即効性
- 楽天市場:イベント活用とポイント設計による売上強化
各チャネルの特性を理解し、それぞれに適した戦略を立てることが、売上拡大の近道といえるでしょう。
各モールにおいては、以下の最適化施策が有効です:
- 商品タイトルに主要キーワードを含める(SEO対策)
- 商品画像を複数枚用意し、使用シーンや成分説明を視覚化
- A+コンテンツ(Amazon)、楽天スーパーセールやお買い物マラソンへの参加
- 購入者レビューの獲得と返信対応による信頼構築
SNSを活用したブランド認知とユーザーエンゲージメント
SNSは、ブランドの世界観やメッセージを視覚的・感情的に伝えるのに適しています。特にInstagram、TikTok、X(旧Twitter)などは健康食品とも親和性が高く、以下の施策が効果的です:
- 商品の「あるある」やライフスタイルに溶け込む使い方を投稿
- フォロワーとのコミュニケーションによるエンゲージメント向上
- ハッシュタグキャンペーンでUGC(ユーザー生成コンテンツ)を促進
用語補足 – UGCとは
UGCとは「User Generated Content」の略で、ユーザー自身が作成した写真・動画・レビューなどのコンテンツを指します。第三者の声として、信頼性や拡散力を持ちます。
実店舗での体験型プロモーションと販促物の工夫
ドラッグストアやバラエティショップでは、「手に取って試せる」体験が大きな武器です。以下の施策が効果を発揮します:
- 試供品やサンプルの配布(「1日分パウチ」など)
- 商品棚のPOPで“使う理由”をわかりやすく訴求
- 店頭スタッフの説明補助シートやタブレット動画の設置
これにより、購買を後押しするリアルな接点をつくることが可能です。
顧客ロイヤリティを高めるリピート戦略
健康食品ビジネスにおいて、継続的な収益を生むためにはリピーターの獲得と維持が不可欠です。一度購入した顧客に再び選ばれるには、信頼感の醸成と実用的な支援の提供が求められます。ここでは、そのための具体的な施策を3つの視点で解説します。
定期購入プランと満足度向上施策
定期購入制度は、顧客にとっての利便性と企業側の安定収益の両方を実現できる仕組みです。たとえば、初回購入時の割引や送料無料の特典を設定することで、新規顧客の参入ハードルを下げることができます。また、定期コースの内容変更やスキップ機能、解約の柔軟さなどを整えることで、「縛られる」という心理的負担を軽減できます。さらに、商品発送前にお知らせメールを送るといった丁寧な対応は、信頼関係の強化に繋がります。
定期購入とは
一定のサイクルで商品を届けるサービス。継続的に健康効果を得るには最適な購入形態であり、企業にとってはLTV(顧客生涯価値)の最大化に貢献します。
ユーザーの声を取り入れた改善と商品開発
顧客の声は商品改善や新たな価値提供のヒントになります。購入後アンケートやレビューへのフィードバック対応を通じて、ユーザーが何を評価し、何に不満を抱いているかを可視化できます。これにより、リニューアルや新商品開発の方向性が明確になります。実際にユーザーの意見をもとにした改善点を公表すれば、「自分の声が反映された」という実感が信頼や愛着を深める要因となるでしょう。
ユーザーの声とは
商品に対するレビュー、問い合わせ、アンケート回答など、実際の体験を通じたフィードバックの総称。品質向上やマーケティング精度の向上に不可欠な情報資源です。
ヘルスサポートや健康情報提供による信頼関係の構築
健康食品を販売する企業として、ただ商品を届けるだけでなく、顧客の“健康的な生活”を支援する姿勢が求められています。たとえば、定期便利用者向けに栄養コラムや飲み方アドバイスを配信することで、実感値を高めると同時に顧客満足度も向上します。さらに、LINEやメルマガを活用したタイムリーな情報提供、または専門家によるQ&Aコーナーの設置なども有効です。顧客が「ここなら安心」と思える環境作りが、長期的なロイヤルティ形成につながるのです。
ヘルスサポートとは
健康維持のための食生活・運動・サプリメントの情報提供を通じ、消費者の目標達成を支援する活動。商品の価値を超えた信頼形成に貢献します。
今後の展望と課題への対応
健康食品市場は今後も成長が期待される一方で、法規制の強化や社会的要請の変化に対応することが企業の持続可能性を左右します。本見出しでは、規制と社会動向の二つの観点から今後注目すべきポイントを解説します。
消費者庁の規制とその対応策
機能性表示食品をはじめとした健康食品の広告・表示に関しては、消費者庁が厳格な基準を設けています。虚偽・誇大広告を防ぐため、科学的根拠の提示が義務化されており、違反があれば措置命令や課徴金のリスクもあります。
そのため、商品の開発段階から表示文言まで、法務や専門家と連携したリスク管理が欠かせません。また、広告制作においても景品表示法・健康増進法の理解が必要であり、スタッフの定期的な法規制研修や監修体制の整備が求められます。
景品表示法とは
消費者庁が管轄する法律で、商品やサービスの表示が不当でないかを規制するもの。誤認を与える表現は禁止されており、違反した場合は課徴金や公表処分の対象となります。
エシカル消費・サステナビリティとの連携戦略
近年、エシカル消費やサステナブルな取り組みへの関心が高まっており、健康食品業界においても環境・社会配慮が重要な選定基準になりつつあります。
たとえば、再生可能素材のパッケージ使用、フェアトレード原材料の採用、環境負荷低減への取り組みなどが、エシカルブランドとしての信頼感を高めます。加えて、公式サイトやパッケージ上でのSDGsに関するメッセージの発信も、共感を得る手段の一つとなります。
こうした社会的価値とビジネスを両立する戦略が、今後ますます重要となっていくでしょう。
エシカル消費とは
人や環境に配慮した消費行動のこと。公正取引・環境保全・地域支援などを重視する購買選択を指し、企業の社会的責任(CSR)とも関係します。
サステナビリティとは
「持続可能性」を意味し、地球環境・社会・経済の持続的発展を目指す考え方です。ビジネスでは環境負荷の低減、資源循環、社会貢献などが注目されています。
まとめ
この記事では、健康食品がなかなか売れない理由を深掘りしながら、売上アップに向けた具体的なアプローチを紹介してきました。
市場が成熟し競争が激しくなるなか、消費者のニーズや信頼をつかむためには、一つひとつの戦略を丁寧に設計することが重要です。
特に、次のような視点が鍵を握るため抑えておくことをおすすめします。
- ECモールやSNSなどの販売チャネルに応じた戦術を使い分けること
- 商品の魅力や特長(USP)をしっかり伝えるブランディング
- ユーザーの声を活かした改善と、リピートにつなげる仕組み作り
- 信頼される企業になるための法令対応やサステナブルな姿勢
こうした取り組みを重ねることで、お客様との関係が少しずつ深まり、自然と売上も伸びていくでしょう。
健康食品業界はこれからも変化を続ける分野です。時代の流れを読み取りながら、自社ならではの価値を磨いていくことで、長く選ばれるブランドへと成長させることができるでしょう。