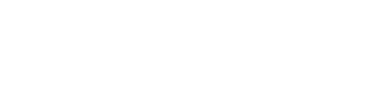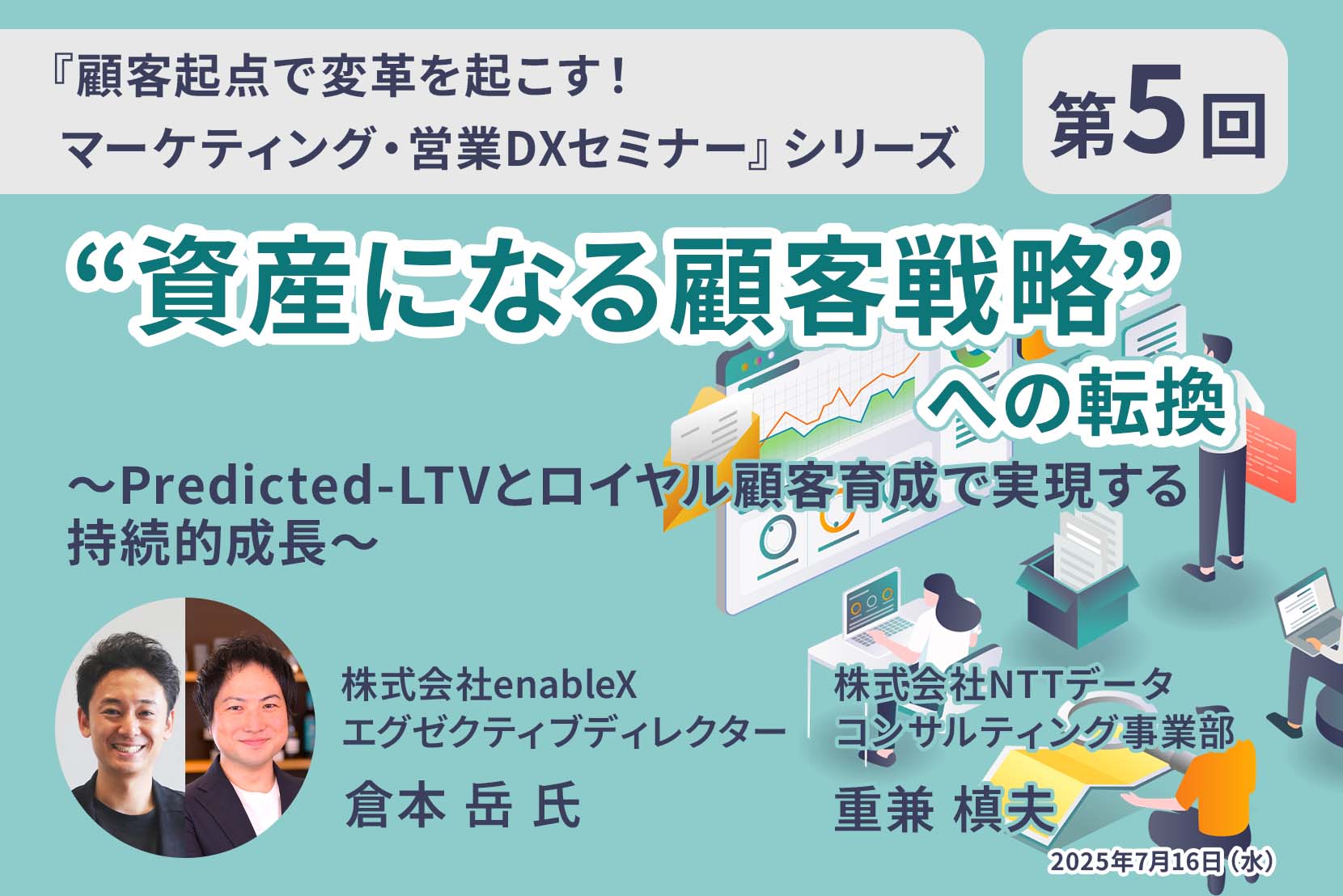自社のペットフードがECモールで売れないのはなんで?施策やターゲティングについて詳しく解説

かつてはペットフードの購入といえば実店舗が主流でしたが、近年ではECモールを活用する飼い主が増加しています。特にAmazonや楽天市場といった大手モールでは、利便性と品揃えが評価され、ユーザー数が急増しています。しかし一方で、「自社のペットフードがなかなか売れない」といった悩みを抱える事業者も少なくありません。
本記事では、ペットフードがECモールで売れにくい背景とその要因を明らかにしながら、商品設計・ターゲティング・モール内施策・外部集客といった多角的なアプローチについて解説します。販売拡大を目指す企業にとって、ぜひ参考にしてみてください。
ペットフード市場とECモールの販売動向
国内ペットフード市場の規模と成長傾向
日本のペットフード市場は、2023年に前年比11.9%増の4,754億円に達しました。この成長は、原材料や物流コストの高騰による価格改定が影響していますが、ペットオーナーの健康志向の高まりも一因とされています。特に、無添加や国産、ヒューマングレードといった品質訴求型の商品が市場を牽引しています。
また、プレミアムフードやスーパープレミアムフードといった高価格帯の商品への需要が増加しており、ペットを家族の一員と捉える意識の高まりが背景にあります。ペットの高齢化や健康志向の高まりに伴い、機能性フードや療法食の需要も拡大しています。
ECモールでの販売比率の推移
ペットフードの販売チャネルにおいて、ECモールの存在感が年々増しています。2022年のペット関連製品のEC市場規模は1,872億円と見込まれており、2027年には2,463億円に達すると予測されています。この拡大は、品揃えの豊富さや宅配の利便性などが支持されているためと考えられます。
特に、楽天市場やAmazonなどの大手ECモールが市場を牽引しており、消費者の利便性志向や多様な商品ラインナップ、ポイント還元などの施策が功を奏しています。また、スマートフォンの普及やインターネットの利用拡大により、オンラインでの購買が一般化していることも背景にあります。
ペットオーナーの購買行動とトレンドの変化
近年、ペットオーナーの購買行動にはいくつかの顕著な変化が見られます。
まず、健康志向の高まりにより、無添加やオーガニック、特定の健康効果を謳ったフードへの関心が高まっています。ペットの健康を重視する傾向が強まり、品質や成分、製造背景などを総合的に評価して商品を選ぶ傾向が強まっています。
次に、情報収集のデジタル化が進んでおり、SNSやレビューサイトを活用して商品情報を収集し、購買判断を行う消費者が増加しています。特に、InstagramやYouTubeなどのプラットフォームでの情報発信が影響力を持つようになっています。
さらに、利便性を求めて定期購入サービスを利用するオーナーが増えており、サブスクリプションモデルの導入が進んでいます。これにより、継続的な購買が促進され、企業側も安定した売上を確保できるようになっています。
これらのトレンドを踏まえた商品開発やマーケティング戦略が、今後のペットフード市場での成功の鍵となるでしょう。
ペットフードがECモールで売れない主な理由
価格競争と大手ブランドの強さ
ペットフード市場では、楽天市場やAmazonといった大手ECモールにおいて、すでに確立された大手ブランドが大きなシェアを占めています。これらの企業は、広告投資やポイント施策などのマーケティングに大きな予算を割いており、中小企業が同様の手法で競合するのは困難です。加えて、価格を重視する消費者層にとっては、安価で信頼性の高い大手ブランド商品が優先されやすく、価格競争に巻き込まれる形で差別化が難しくなっています。
商品差別化の不十分さと特徴が伝わらない商品ページ
多くの中小ペットフードメーカーが直面しているのが、商品の独自性を十分に訴求できていない点です。成分や製造背景にこだわっていても、その情報が商品ページで適切に伝えられていなければ、消費者にとっては大手製品との違いが分かりづらくなってしまいます。例えば、添加物不使用や原材料の産地、製造過程の安全性などは、適切な表現で構造化され、画像やアイコンとともに視覚的に示す必要があります。
レビュー・信頼獲得の施策不足
ECモールにおいて信頼構築の要となるのがユーザーレビューです。特にペットフードのように品質が重視される商品では、他の購入者の体験談が購買の大きな決め手となります。しかしながら、レビュー獲得のためのインセンティブ設計や、レビューを促す購入後のフォローアップ施策が欠けているケースが多く、結果としてレビュー数が少なく、商品ページの信頼性が低く見えてしまいます。
ターゲット(犬種・猫種・年齢別)の絞り込みが不明確
ペットフードは、ペットの種類、年齢、健康状態などによって最適な商品が異なります。
しかし、多くのEC商品ページでは、これらの絞り込みが不明確であり、購入者にとって選びやすい設計になっていないことが売上不振の一因となっています。
例えば、小型犬用、高齢猫用、アレルギー対策フードなど、明確にターゲットを絞り込んだ訴求が求められます。
これらの課題を解消するためには、戦略的なコンテンツ設計とユーザー視点に立ったマーケティングの再構築が不可欠です。
ECモール別に見るペットフード販売の戦略と強化ポイント
楽天市場
楽天はポイント施策やランキング、レビュー重視の文化が根付いているため、レビュー数と評価の獲得が最優先事項です。商品ページには比較表や成分訴求を明示し、特に「無添加」「国産」などのキーワードを活用すると効果的です。
- 楽天スーパーSALEや買い回りイベントに合わせたプロモーション強化
- RPP広告(楽天プロモーションプラットフォーム)の継続的運用
- レビュー投稿でポイント付与などUGC(ユーザー生成コンテンツ)獲得施策の実施
Amazon
Amazonでは検索ロジック(A9)に対応する商品タイトルの最適化が不可欠です。ブランド登録によりA+コンテンツを活用し、商品差別化を図ります。また、FBA利用による配送品質の向上も重要なファクターです。
- キーワード対策に基づいた商品タイトル・バレットポイントの最適化
- スポンサープロダクト広告とディスプレイ広告の併用
- 定期便やクーポンによる初回購入の後押し
Yahoo!ショッピング
Yahoo!ショッピングはキャンペーン依存が強いため、イベントカレンダーを活用した施策設計が鍵となります。PayPayボーナスとの連携が集客力の向上に直結します。
- ソフトバンク/Yahoo!会員向けクーポンの設定
- イベント(超PayPay祭等)への参加とタイムセール設定
- ストア評価・レビューの収集によるSEO強化
商品力・ブランドの再定義による改善策
成分・原産地・添加物情報の明示
ペットフードの品質を訴求するためには、成分や原産地、添加物の有無といった情報を明確に伝えることが重要です。消費者はペットの健康を第一に考えており、安心して与えられる商品を求めています。具体的には、以下のような情報を商品ページに記載することが効果的です。
- 主原料の種類と産地(例:国産鶏肉使用)
- 添加物の有無(例:合成保存料不使用)
- アレルゲン情報(例:小麦グルテンフリー)
これらの情報を分かりやすく、視覚的にも訴求することで、消費者の信頼を得ることができます。
パッケージ・ネーミングの見直し
商品の第一印象を決定づけるパッケージデザインや商品名も、購買意欲に大きく影響します。特にECモールでは、商品画像が購買判断の大きな要素となるため、以下の点を見直すことが推奨されます。
- パッケージに商品の特徴や利点を明記する(例:高タンパク質、低脂肪)
- ペットの種類や年齢に応じたデザイン(例:シニア犬用、子猫用)
- 商品名に特徴を反映させる(例:「ナチュラルチキン・グレインフリー」)
これにより、消費者が商品を一目で理解しやすくなり、購買につながりやすくなります。
ブランドストーリーや理念の可視化(エシカル・サステナブル等)
現代の消費者は、商品の背景や企業の理念にも注目しています。エシカルやサステナブルといった価値観を共有することで、ブランドへの共感を得ることができます。具体的な施策としては、以下が挙げられます。
- 企業の理念やミッションを商品ページや公式サイトで紹介する
- 環境に配慮した取り組み(例:再生可能エネルギーの使用、リサイクル可能なパッケージ)の情報発信
- 動物福祉への配慮(例:動物実験を行わない)の明示
これらの情報を積極的に発信することで、ブランドの信頼性と差別化を図ることができます。
ECモールでの集客力向上施策
商品タイトル・説明文のSEO最適化
ECモール内での検索結果において上位表示を狙うためには、商品タイトルや説明文のSEO対策が不可欠です。以下のポイントを押さえて、検索エンジンに評価されやすいコンテンツを作成しましょう。
- ターゲットキーワードを商品タイトルに含める(例:「無添加」「国産」「グレインフリー」)
- 商品説明文に詳細な情報を盛り込む(例:原材料、成分、対象ペットの種類や年齢)
- 見出しや箇条書きを活用して、読みやすさを向上させる
これにより、検索結果での視認性が高まり、クリック率の向上が期待できます。
モール内広告(楽天RPP・Amazonスポンサープロダクト)の活用
ECモール内での広告出稿は、商品露出を増やし、売上向上に寄与します。楽天市場では楽天プロモーションプラットフォーム(RPP)、Amazonではスポンサープロダクト広告が代表的です。これらの広告を効果的に活用するためには、以下の点に留意しましょう。
- キーワードの選定と入札価格の最適化
- 広告パフォーマンスの定期的な分析と改善
- 商品ページのコンバージョン率向上施策(例:レビュー数の増加、魅力的な商品画像の掲載)
広告と商品ページの改善を組み合わせることで、より高い効果が得られます。
商品レビュー・購入者写真の充実による信頼構築
購入者のレビューや写真は、他の消費者にとって信頼性の高い情報源となります。レビュー数や評価が高い商品は、購買意欲を刺激しやすくなります。レビューを増やすための施策として、以下が有効です。
- 購入後にレビュー投稿を促すメールやメッセージの送信
- レビュー投稿者へのインセンティブ提供(例:次回購入時の割引クーポン)
- 商品にレビュー依頼カードを同封する
これらの施策を通じて、レビュー数の増加と内容の充実を図りましょう。
クーポン・ポイント還元による初回購入ハードルの低減
初めての商品を購入する際、消費者は品質や効果に不安を感じることがあります。これを解消するために、クーポンやポイント還元を活用した施策が有効です。具体的には、以下のような方法があります。
- 初回購入者限定の割引クーポンの提供
- レビュー投稿者へのポイント還元
- 定期購入への割引特典の付与
これらの施策により、初回購入のハードルを下げ、リピート購入につなげることが可能です。
SNSや外部メディアとの連携による流入拡大
InstagramやTikTokでの使用シーン投稿
SNSは視覚的・感情的な共感を呼びやすいメディアであり、ペットフードの魅力を伝えるには最適なチャネルです。特にInstagramやTikTokでは、ペットの可愛らしい姿や食事シーンを通じて、商品の使用イメージを直感的に訴求できます。効果的な活用方法は以下のとおりです。
- 実際にペットがフードを食べる様子の動画や写真を投稿
- フィード投稿だけでなくストーリーズやリールも活用
- 「#無添加ペットフード」などの関連ハッシュタグを設定し検索性を高める
このような投稿は拡散力が高く、ターゲット層への自然なアプローチとして有効です。
インフルエンサーとの協業とレビュー発信
ペットジャンルに強いインフルエンサーと提携し、商品のレビューを発信してもらう施策は信頼性のあるプロモーション手段となります。インフルエンサーを選定する際には、以下のような点に着目しましょう。
- フォロワーの属性(ペット飼育層が中心であるか)
- 投稿のエンゲージメント率(実際の反応が高いか)
- 過去の企業案件との親和性(過度な宣伝色がないか)
彼らの発信を通じて、認知向上と購買意欲の喚起を同時に実現できます。
ペット向け情報サイト・YouTubeとの連携プロモーション
ペット関連の専門メディアやYouTubeチャンネルと連携し、製品紹介やタイアップコンテンツを制作することで、商品理解の深化とSEO面での効果が期待できます。たとえば以下のような手法が考えられます。
- ペットの健康・栄養に関するコラムで製品の特長を紹介
- ペット用品レビュー動画での紹介
- 獣医師監修の企画による専門性の担保
情報感度が高いユーザー層に向けて、信頼あるメディアを介した訴求を行うことで、ブランド認知と信頼性を同時に高めることが可能です。
購買率とリピート率を高める仕組みの構築
サブスクリプション・定期購入プランの導入
ペットフードは継続的に消費される日用品であるため、定期購入プランの導入は非常に有効です。一定のサイクルで商品が届く仕組みは、ユーザーにとって利便性が高く、企業側にとっても安定した売上を確保できるメリットがあります。
具体的には、以下のような設計がポイントになります。
- 飼育頭数や体重に応じた最適量の提案
- 変更・スキップ・解約が簡単な柔軟なシステム
- 定期購入者限定の割引やプレゼント特典の提供
定期購入はLTV(顧客生涯価値)の最大化に寄与する中核施策といえるでしょう。
LINE・メルマガでのタイミング通知とオファー配信
次回購入のタイミングにあわせて、LINEやメールマガジンでリマインド通知を送ることで、リピート率の向上が期待できます。特にパーソナライズされた情報配信は開封率・クリック率の向上につながります。
効果的な配信の例としては、
- 前回購入から20日後に「そろそろ残りが少なくなっていませんか?」という通知
- 飼っているペットの年齢や季節にあわせた商品提案
- クーポンやレビュー投稿キャンペーンの案内
といった内容が考えられます。
飼育履歴に基づくパーソナライズ提案
顧客の飼育履歴や購入傾向をもとに、フードの種類・量・新商品のおすすめなどを提案することで、信頼関係を築きながらアップセル・クロスセルが可能となります。
たとえば、以下のような提案が有効です。
- 「1歳になったので成犬用に切り替えてみませんか?」
- 「季節の変わり目には皮膚ケア成分配合のフードがおすすめです」
- 「おやつを追加でご紹介します」
パーソナライズによって、顧客の「選ぶ手間」を軽減しながら、より深い満足とロイヤルティを提供できます。
今後の展望と取り組むべき課題
ペットの健康志向・高齢化とフードの機能分化
日本におけるペット飼育数は横ばい傾向にある一方で、飼い主の健康志向の高まりやペットの高齢化が進んでいます。これに伴い、ペットフードには以下のような機能性が求められるようになっています。
- 関節サポート:シニア犬・猫向けにグルコサミンやコンドロイチン配合
- 消化ケア:胃腸が弱い個体向けにプレバイオティクス配合
- 皮膚・毛艶サポート:オメガ脂肪酸やビオチンを含有
このような多様なニーズに対応するためには、商品ラインナップの拡充に加え、パッケージや商品ページでの分かりやすい機能訴求が不可欠です。
また、健康を気にする飼い主向けに「添加物不使用」「グレインフリー」「低アレルゲン」といった表示の信頼性や根拠を明示することも重要な取り組みでしょう。
獣医師や専門家監修による信頼性の確保と差別化
機能性を訴求する商品であるほど、科学的・専門的な裏付けが信頼のカギとなります。そのため、以下のような施策が差別化につながります。
- 獣医師・栄養士の監修表記:専門家のプロフィールと共に掲載
- 第三者機関による認証:原材料や製造工程の安全性証明
- Q&Aコンテンツや動画での専門家解説:飼い主の不安を払拭
特に新興ブランドや認知度の低い商品にとっては、信頼性の裏付けはコンバージョンに直結する要素です。安心・安全への配慮は、ブランドの差別化にもなるでしょう。
まとめ
本記事では、自社のペットフードがECモールで思うように売れない要因を明らかにし、それに対する具体的な改善施策について解説しました。多様化する消費者ニーズと、競合が激化するオンライン市場においては、単なる商品展開だけでなく、戦略的なブランド設計と顧客接点の最適化が重要となります。
特に注目すべきポイントは以下のとおりです。
- 市場背景の理解:ECモールでの購入比率が年々上昇するなか、ユーザーの情報収集行動が複雑化している点に留意する。
- 商品差別化の強化:成分や製造背景の「見える化」や、商品パッケージ・ブランドメッセージの再設計が不可欠。
- 集客と信頼構築の両立:SEO対策や広告施策に加え、レビュー・UGCの活用で購買意欲を高める。
- ターゲット戦略の明確化:犬種・猫種・年齢別にターゲティングし、最適な訴求軸で商品を届ける。
- 再購入につながる仕組み作り:定期購入やパーソナライズ提案、リマインド施策によりLTVを向上。
今後のペットフード市場では、単なる物販から、飼い主との信頼関係に基づいた「健康パートナー」としての立ち位置が問われるようになります。時代の変化に応じた戦略で、長期的なファン形成と売上の安定を実現することが求められるでしょう。