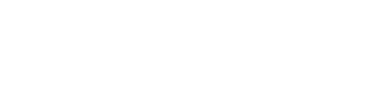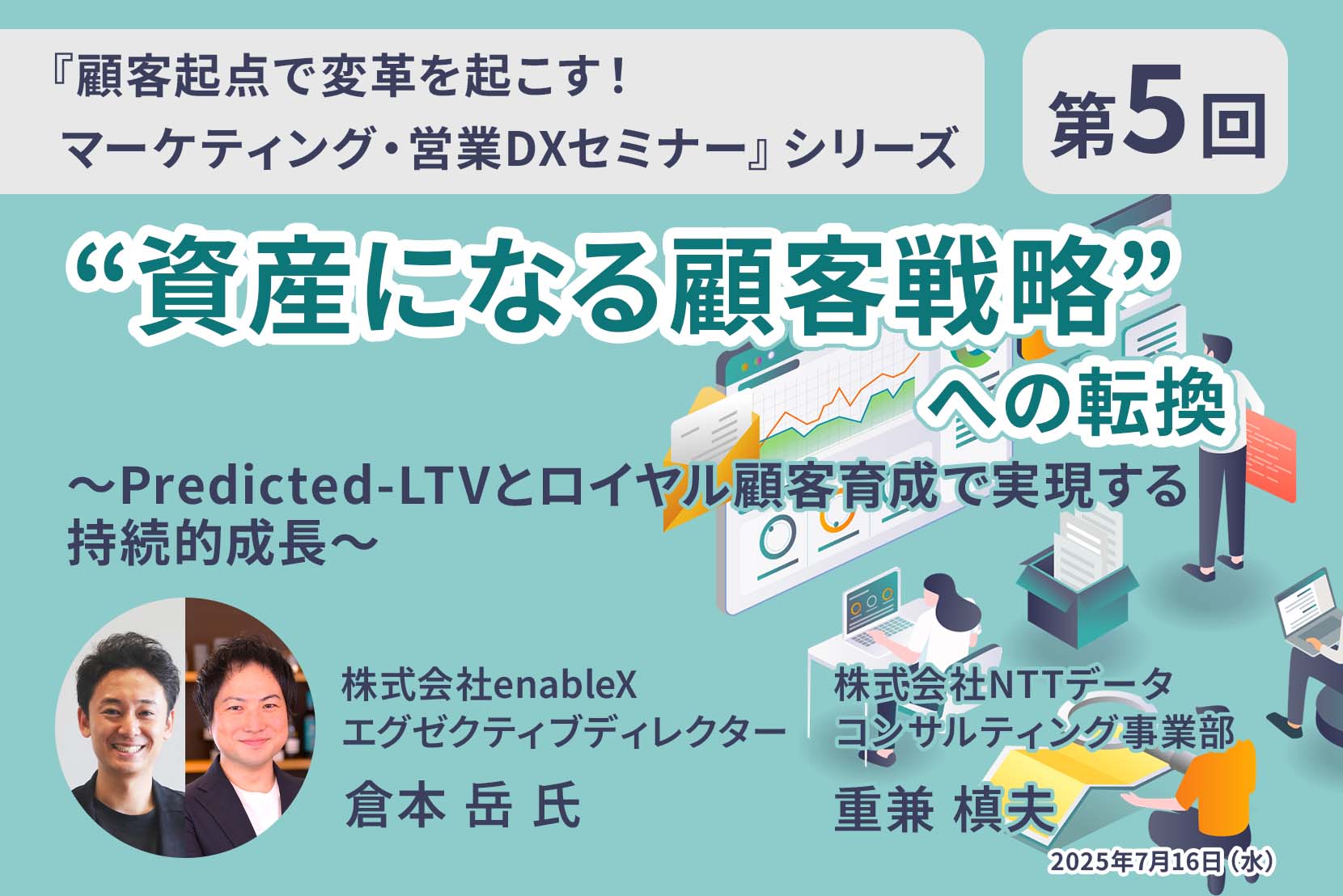調査・検討はどの程度行えばよいのか?

投資の検討と投資実行後の実行というに携わるという弊社の仕事柄、「どの程度の時間、費用を検討・調査に使うべきか」という疑問は常に持っている。そこで今回は定量的にこの質問に対して簡易なシミュレーションを行い、妥当な調査・検討文量を考えるヒントを提示したい。(時間がない方は最後のまとめだけ読んで下さい!)
前提として
- 全く検討などしない、やってから全てを考えればよい
- 実行前にあらゆる資源を活用し検討しつくしてから実行するべきだ
という両極端な主張は明らかに誤っている。そうとなれば定量的に妥当な検討文量を導出し、適切なバランスを見つける必要がある。
またどちらかと言えば私は投資を推進する立場に常にいたため、やや偏っている可能性はあることはご承知頂きたい。
投資金額に対する調査検討費用
例えば1億円のリスクが高い投資を検討しているとしよう。ここでは投資対象は自社での新規事業とする。さて、どの程度の金額を検討(投資可否の判断)にかけることが妥当なのだろうか。
仮に、5%として考える。つまり500万円を調査・検討に使えるということだ。これが例えば極端に考えて50%として5,000万円を調査・検討に使うならば1億円の投資を回収出来る難易度は格段に高いものになってしまうため、誤りだと分かるだろう。
この投資を検討している企業が大企業とすると500万円の中で何が出来るだろうか。これは実はかなり限定されたものになる。費用に関しては弊社の過去経験により概算値を示している。
例えば市場規模計算、顧客インタビュー(3件)、先行者インタビュー(3件)、デスクトップサーチといった情報収集活動で210万円。
収集された情報から競争戦略、販売計画、収益計画を導出し実行チーム内で合意形成を図るために300万円。
役員説明用の資料作成を50ページ、また役員からの追加質問(20問想定)に対する質疑応答で350万円。
合計860万円となり、当初想定の5%をオーバーした8.6%となる。
ここで投資可否を判断する側は
- 調査・検討にかけてよい割合を上げる
- 1投資あたりの金額を上げる
- 検討項目を絞り込む
というオプションから選ばなければならないことになる。
ちなみに上の例は極端なケースではなく3,000万円の投資判断のために1,000万円の調査・検討費用が費やされることは全く珍しいことではない。
また、こういった考えもある。もし上が実証実験の検討であるならばこれは1億円の投資判断ではなく、今後発生する5億円の投資判断も含むから860万円は正当化される、という考えである。
ただし、実際に事業というものは試しに参入してみると検討時とは比較にならない程多くの情報に触れることが可能になるため検討時の情報はほぼ役に立たないことになる。つまり実証実験の投資判断であっても単独の投資判断として扱って差し支えないと考える。
現実的には「検討項目を絞り込む」ことを推奨したい。
「調査・検討にかけてよい割合を上げる」を選択したとしても、そもそも参入前の情報というのは信頼性に乏しいのだ。後述する理由により例え検討予算を2倍に増やしたとしても投資成功確率の向上に寄与するとは考えづらい。
また「1投資あたりの金額を上げる」はどうだろう。つまり1つの実証実験のために費やす金額を上げれば数値上は5%の基準は守られることになるが、これも本来リスクを抑えるため小規模で実施する「実験」としての目的を失わせてしまう。
投資判断を実施する側が「この案件において本当に重要なことは何か、逆に後から考えればよいことは何か」という判断を出来ないのであれば検討予算は無限に増殖する。新たな取組をする際の検討資料に対して、ダメ出しをするほど簡単な仕事はない。
しかし、自分が発した質問1つ1つが調査・検討予算を過剰に増大させている危険性を認識するべきだ。3,000万円の投資案件に対して1,500万円の調査予算を費やすような状況になっているなら投資判断側にも重大な責任がある。
さらに言うなら、事業を実行したことがない人間のなんとなくの質問に回答する資料を作成する程、事業に対する熱意がある人間の意欲を削ぐ仕事はない。過剰な調査・検討予算を使わせようとしている危険性のみならず、非常に貴重な資源である「事業に対する熱意のある人間」をすり潰そうとしている危険性も認識するべきだ。
調査・検討量と効果が示す対数的な関係
例えば、インタビューを3件実施した際の効果と50件実施した際の1件あたりの効果は大きく異なる。これは想像していただければ分かるが、後半になればおおよそ同じような情報が得られるからだ。
調査・検討には費用対効果が高いピークが存在することになる。やればやるほど、よい投資判断が出来るということではない。
ある程度の調査・検討を実施した後に「この投資は成功するか」という質問に回答する唯一の手段は事業で実績を出すことである。調査・検討の意味は実行に対して薄れていく。
一方、調査・検討は幅広い範囲の情報を探索出来るという素晴らしい価値を持つ。事業を異なる領域で何個も同時並行で立ち上げることは難しくとも、調査・検討であれば可能となる。
つまり浅く広く見る、という状況であれば調査・検討が優位であり、特定のテーマが絞れた後であれば実行が優位となる。
小規模に事業を実行する、というのは追求するテーマが絞れた後であれば高精度でありコストパフォーマンスに優れた情報収集手段ともなる。
シンプルに書くなら、私がとある事業をやろうと考えている。これが成功するか否かを判断するためにインタビュー調査ばかりをやっている。こんなことはせず、そのアイデアを顧客に直接ぶつけて「買ってくれ」と言ったほうが遥かによいということだ。
時間の費用に対する考察
さて、今までは主に調査・検討に費やす金額という観点から見てきた(もしくは時間を金額に換算し考えた)。
一方、時間に関してはどう定量的に考えることが出来るだろうか。一度、案件を突き返すことで失われる時間が持つ価値をどう評価できるだろう。
例えば経営者というものが、任期内に投資案件を発見し、リターンを出す仕事であると非常に単純化して考えよう(実際はこれほど単純ではないが)。
ケースAでは投資案件を早期発見し、1年目に1億円投資を投資したとする。この案件は成功しその後、年間1億円づつ生み出すものとなったとする。
ケースBでは、投資案件発見が遅れ3年目に同案件に投資したとする。結果は同じく年間1億円のFCFを生み出し続けたとする。
ケースAのIRRは93%、ケースBでは62%。現在価値を無視し、任期中に生み出したFCFだけで比較すればケースA 3に対してケースBは1である。
さらに「調査・検討量と効果が示す対数的な関係」から投資判断を引き伸ばしたとしてもより良い投資判断が出来る可能性は乏しい。
現実的にはケースAではさらなる投資案件発見に成功する可能性が高い。実務に取り組んでいる中で発見される案件は良質な案件であることが多いからである。
時間に対しては「今検討を引き伸ばすコストはいくらです」とは端的に言い難いが、検討を引き伸ばすことでリターンを得る機会を失い、追加案件を発見する機会を失う割には、投資判断の蓋然性を上げる効果には乏しいケースが多い。
まとめ
非常に分かりづらい文章になってしまい恐縮であるが結論としてはシンプルである
- 投資金額に対して過剰な検討・調査予算を無自覚に使うべきではない
- 検討・調査予算は社員の時間を含めどの程度使っているのかは簡単に計算した方がよい
- 投資判断を行う責任を負っているならば「この案件において本当に重要なことは何か、逆に後から考えればよいことは何か」を判断できなければならない
- 過剰な検討・調査は希少資源である「事業に情熱のある人間」をすりつぶす
- 検討・調査よりも小規模な実行の方が情報収集としても有利になるタイミングは早期に訪れる
- 投資判断を引き伸ばすことで得られる効果は低い(検討停止という判断はOK)