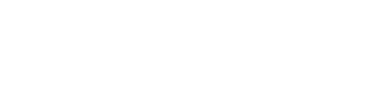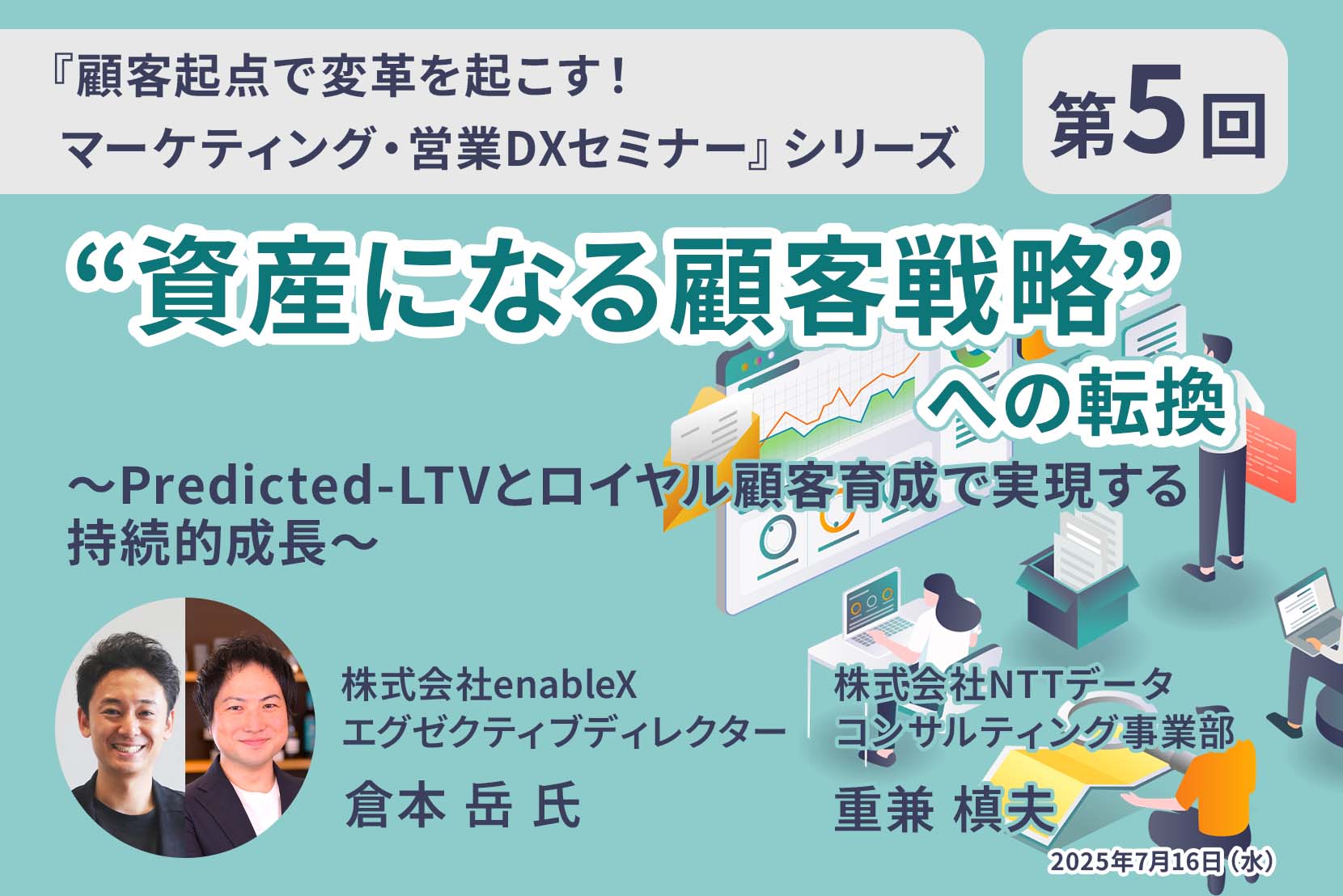AIネイティブなマーケティングプロセスで、業界の未来を切り拓く/真嶋氏インタビュー

博報堂、LITALICO CMO、トランスコスモスでは上席常務執行役員、クリエイティブ領域では、カンヌライオンズ、クリオ賞、The One Showの世界三大広告賞での受賞歴ありと、マーケティング業界の最前線を走り続けてきた真嶋氏。デジタルマーケティングの黎明期から現在のAI時代まで、業界の変遷を肌で感じてきた彼が、なぜ今enableXへの参画を決めたのか。AIネイティブなマーケティングプロセスの構築という野心的なビジョンと、業界が直面する本質的な課題について語っていただきました。
NTTから博報堂へ。放送ビジネスから広告の世界へ
―まず、真嶋さんのこれまでのご経歴について教えてください。
1998年に日本電信電話株式会社、いわゆるNTTに入社しました。最近NTTに正式に社名が変わっていましたが・・・。当時はまだ一社採用をしていたタイミングで、翌年の1999年に東日本、西日本、コミュニケーションズという形で分割されて、私は東日本の方に移りました。
NTT東日本では放送局向けのビジネスを担当しているチームに配属となり、スカパー!さんの顧客管理システムの開発プロジェクトにジョインしました。当時のスキームはNTT側がシステムを持ち、スカパー!さんにご利用いただく形で、大規模な開発プロジェクトに参加できる貴重な場でした。
そのプロジェクトと並行して、ブロードバンド時代のキラーコンテンツとして考えられていたビデオオンデマンドサービスのフィジビリティ検証にも取り組んでいました。H.264(動画の圧縮と伸張を行うための代表的な圧縮方式)が出てきて、初めて動画が軽く圧縮できるようになったタイミングだったので可能性を感じていたのですが、それでも配信のコストが高くて、ビジネスとしての成立が難しいと感じたんです。そこで、「やっぱりまだ広告モデルなんだな、このビジネスは」と考え、広告ビジネスを学びたいと博報堂に転職しました。

―博報堂ではどのような経験を積まれたのですか。
いつか代理店としての新規事業開発に関わりたかったのですが、その前に広告代理店としてのど真ん中を経験しなければと思い、制作営業の業務にトライしました。
入社したタイミングで、いきなり高級宝飾時計のブランドムービー制作の担当となり、まったく違う世界に飛び込むことになりました。そして、担当してすぐイタリアに出張。担当していたブランドの創業者が亡くなられたので、そのトリビュートブックを作りに行くというプロジェクトでした。入社してすぐにこのようなチャレンジの機会をいただけたことに、今でも感謝しています。
その後、HISさんのダイレクトなチラシ・新聞からテレビCMまで、一通りのメディアとクリエイティブを経験させていただきました。そして満を持して、ソニーチームに配属されました。
―ソニーでの仕事が、真嶋さんのキャリアの転機になったのですか。
そうですね。ソニーチームは基本的にセントラルメディア・バイイングでメディアの扱いがなく、クリエイティブを中心としたコミュニケーション・プランニングで勝負するチームでした。ソニーというブランドが当時はまだ国内で非常に強かったので、良いクリエイターに担当してもらえるという環境があり、博報堂のトップクリエイターたちと仕事ができたのは貴重な体験でした。
その時に「NTT出身なんだから、デジタルできるよね」という謎のブランディングが始まりまして(笑)。デジタル系へ関与が強くなっていくタイミングとなりました。優秀なクリエイターと組んで、ハンディカムのプロモーションで「Cam with me」という子育ての疑似体験ができるコンテンツを作り、カンヌで賞をいただくことができたのも良い思い出です。
その後は、ソニーマーケティングを5年ほど担当させていただきながら、ソニーコンピュータエンタテインメント、つまりPlayStationのメインエージェンシーのポジションを奪還し、PlayStation 4のローンチコミュニケーションを担当させていただきました。
また、そのローンチコミュニケーションと並行して、役員からメルカリさんの競合コンペに参加するように指示をいただき、初めてのTVプロモーションとなったコミュニケーションを担当させていただくなど、博報堂時代には数々の素晴らしいプロジェクトに参加させていただきました。
最終的にスタッフ部門に移り、クライアントに対峙してデジタルを推進していく部署を立ち上げにジョインしました。その後、その部署の責任者として部長になっていくというキャリアでした。
―その後、事業会社への転身を決められたのですね。
広く浅く、様々なことを代理店として経験したのですが、スタートアップとの関わりが強くなっていたこともあり、LITALICOという会社からCMOとして入社してほしいというオファーをいただきました。 そして、LITALICO では3事業のブランドリニューアルを行いました。
そのブランドリニューアルを終えたタイミングで次のトライをと考え、トランスコスモスでのDX推進へ進みます。
トランスコスモスでの挑戦。マーケティングDXの最前線で
―トランスコスモスではどのような役割を担われたのですか。
初めの3、4年は、デジタルトランスフォーメーション本部の副責任者として、コンタクトセンター、広告、サイト制作など、特に領域に囚われずにプランニングを行うチームを作り、そのリードをしていました。
その後、広告部門が伸び悩んでいたこともあり、広告部門の責任者として事業責任を持つ形で担当しました。裏側ではブランドオペレーションという子会社を作り、メディアにこだわらず、お客様のマーケティング支援をニュートラルに行う組織も立ち上げました。
最終的には、デジタルエージェンシー本部、ECX(EC系のShopify提供やフルフィルメント)の担当役員、そしてトランスコスモス全体のマーケティング本部長として、3つの部署と子会社を担当していました。

デジタルマーケティングの3つの進化段階。そしてAI時代へ
―これまでのキャリアの中で、マーケティング業界の変化をどのように感じてこられましたか。
マーケティング業界の進化は三段階に分けられると考えています。
第一段階は、プラットフォームの急成長期。デジタルがアナログに“プラスオン”される形で導入され、専門代理店が台頭しました。
第二段階は、デジタルを中心に統合的なコミュニケーションを構築する時代。マス広告とデジタルの境界がなくなりました。
そして現在は第三段階、AIによる構造変化の時代です。
―第3段階の特徴について、もう少し詳しく教えてください。
これまで大量の人員がデータ分析やレポートに費やしていた部分が、AIによって置き換わるタイミングにあります。その結果、人間は創造性や戦略といった本来の強みに集中できるようになると考えています。
個別最適が全体最適を損なう。業界が抱える構造的課題
―日本企業のAIやテクノロジー活用について、どのように見ていらっしゃいますか。
AIを「使っている」企業は増えていますが、「最適化できている」企業はまだ少ないと感じます。
業務単位では効率化しても、全体の工数や人件費が減っていない。つまり、AIネイティブなマーケティングプロセスを構築できていないのです。
要因としては、マーケティングの多様化があります。プラットフォームごとに最適化が進み、各担当者が真摯に取り組むほど、全体の整合性が崩れる。CPAを最適化してもLTVが下がるなど、部分最適が全体最適を阻害しています。
つまり、全体を俯瞰してオーケストレーションできる存在が不在なのです。
―AIネイティブなプロセスに至れない阻害要因は何だと考えていますか。
多様化したマーケティングというところが非常に大きいと思っています。
例えば広告で言うと、プラットフォームの数がかなり増え、それぞれのアルゴリズムに合った形で運用しなければいけない。そこの最適化に皆が注力してしまっているんです。あるいはSNSのオウンド運用など、それぞれの役割、それぞれのミッションに真摯に取り組むがゆえに個別最適化していくことが、全体最適を損なっている原因なんだろうと思っています。
CPAを良化させようとすればLTVはどうなるのか、といった話もそうです。どの視点、どこを重視するかで、意思決定の考え方は変わってきます。
―つまり、全体を俯瞰する存在が不在だということですね。
その通りです。きちんと全体を俯瞰し、そこにテクノロジーを入れながら、オーケストレーションする人の確保が、なかなか難しいということですね。
AIネイティブなマーケティングプロセスの構築へ
―enableXで実現していきたいことについて教えてください。
AIネイティブなマーケティングプロセスを作ることによって、より人間的な、創造力や戦略のレイヤーに人間が特化できる形で、お客様と一緒に共創できればと思っています。そのベースの上で、クリエイティビティの高いクリエイターを巻き込みながら、マーケティングコミュニケーションの質をより高めていくことができればと考えています。
―具体的には、どのようなプロセスをイメージされていますか。
まず、データ基盤をきちんと整えることが基礎になります。その基礎の上でAIを活用し、マーケティングプロセスの中でプランニングに活用。そして、そこからのレポート・分析を、またプランニングに繋いでいく。そのサイクルをきちんと作ってあげられたらと思っています。
―そうなると、現場で働く人の役割も変わっていきますね。
人がいらなくなることは実はないのだろうなと思いながらも、リスキリングをしてもらう必要があるだろうと思っています。
例えばGoogleのPerformance Maxや、Meta広告のAdvantage+など、自動化のプロダクトがどんどん出てきています。プラットフォーム最適化はプラットフォーム側にやってもらいつつ、それを超えた領域、つまりチャンネル全体を見たときにどう判断するべきかというところは、人間がやらなければいけません。
さらにそこに対してのクリエイティブや、ビジネスを俯瞰したときの関係性など、そういったところまで見ていく。今までよりも一歩引いた、一歩上流に行く形に、それぞれの人がシフトしていかなければいけないと思っています。

enableXだからこそできること。事業開発ファームの強み
―なぜenableXでそれを実現しようと考えられたのですか。
enableXは事業開発を担うファームであり、経営層と直接対話できる立場にあります。
現場に入り込むだけでは見えない課題を俯瞰し、「ビジネス成長のためにプロセスを刷新する」という対話が可能です。なので、enableXで考えました。
―組織づくりの観点では、どのように考えていますか。
マーケティングプロセスの刷新は、やはり目の前の業務に精一杯向き合っている人にはできないと思うのです。一歩俯瞰した立場で、私たちが入ることによって、その移行をサポートできるというところが大きなポイントです。
前職でも、マーケティングプランニングのプロセスを変える際、現場でやっている人たちではなく、別の体制のチームをきちんと作って、ハンズオンでそこを変えていくという取り組みをやっていました。そのやり方が最適化を迅速に実現できるという思いもあります。
ニュートラルで気軽に越境可能なマインドを持つ人材を求めて
―enableXでは、どのような方と一緒に働きたいとお考えですか。
キーワードは「ニュートラル」と「越境」です。
お客様の課題に対して手段を選ばず、最適なアプローチを柔軟に選び、最後までやり切る方と働きたいと思っています。AIネイティブなマーケティングは、まだ誰も成し遂げていません。
経験よりも「学び続ける意欲」「共に創る姿勢」を持つことが重要です。
―自分にできるだろうかと不安に思っている方もいるかもしれません。
トライをしていくのに重要なのは、今までの経験だけではなく、これからどう学んでいくか、これから一緒にどう作っていくかということだと思っています。
新しいことに興味を持ち、それを取り入れて、より良くしていこうというマインドが、一番重要なんじゃないかと思っています。それがしっかり持っている人であれば、キャッチアップのスピードは個々の違いはあると思いますが、それでもしっかりと作っていける仲間になれるんじゃないかと。
―最後に、enableXへの参画を検討している方へメッセージをお願いします。
マーケティングプロセスの変革には多様なプロセスが絡みます。それをすべて分かる人は、今の段階ではいないと思うんですよね。
だからこそ、一人ひとりの強みを活かしながら役割を広げられる環境があります。全体に対しての自分の役割ということを軸に、入社後により広げていただける環境だと思っていただけるといいなと思っています。
AIネイティブなマーケティングの未来を、一緒に作っていきましょう。