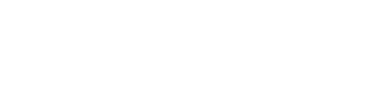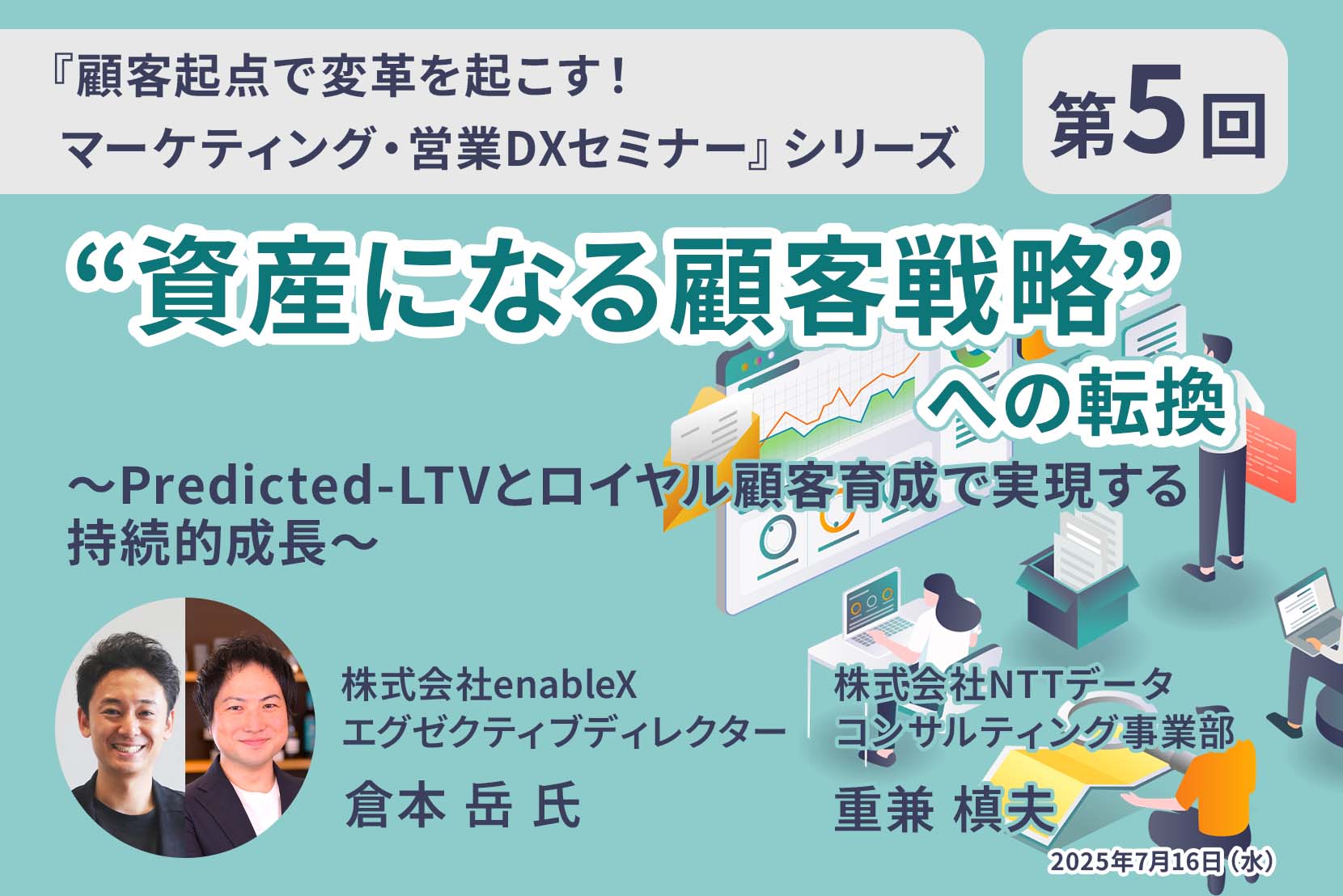AIテクノロジーと専門性の融合で、
事業創造の常識を塗り替える
-
 元ソニー執行役副社長 吉岡 浩氏が株式会社enableXの顧問に就任
元ソニー執行役副社長 吉岡 浩氏が株式会社enableXの顧問に就任弊社はソニー株式会社で執行役副社長等を歴任した吉岡 浩(よしおか ひろし)氏が顧問に就任したことをお知らせいたします。 enableXではこれまでビジネス・事業開発領域に特化した人材を数多く擁してきましたが、今後は技術面でもポテンシャルの高いAIエンジニアや研究者の内部登用・採用を積極的に進め、グローバルに事業を拡大していく計画です。 そうした中、エンジニアリングや研究開発の豊富な経験とグローバルな視点を持つ吉岡氏の参画は、技術人材の強化のみならず、AIの社会実装やグローバル組織の構築を推進する上でも大きな助けになると考えています。 吉岡 浩氏について 吉岡 浩氏は、京都大学工学部を卒業後、日本無線株式会社の研究所勤務を経てソニー株式会社に入社。エンジニアリング部門でビデオカメラのエンジニアとして活躍した他、事業開発、研究開発など多岐に渡る業務を経験されました。2001年には、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の社長に就任し、2003年には親会社であるソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズABのCVP(Corporate Vice President)としてスウェーデンに赴任し、携帯電話開発を統括し、グローバルな事業の拡大と業績改善に大きな貢献をしました。帰国後、ソニー株式会社にてオーディオ事業本部長やテレビ事業本部長など要職を歴任し、2009年には執行役副社長に就任しています。2012年末に退職後、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の社外取締役等多くの企業を支援しており、現在は同社の関連企業の社外取締役などを務めております。 プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000147732.html
-
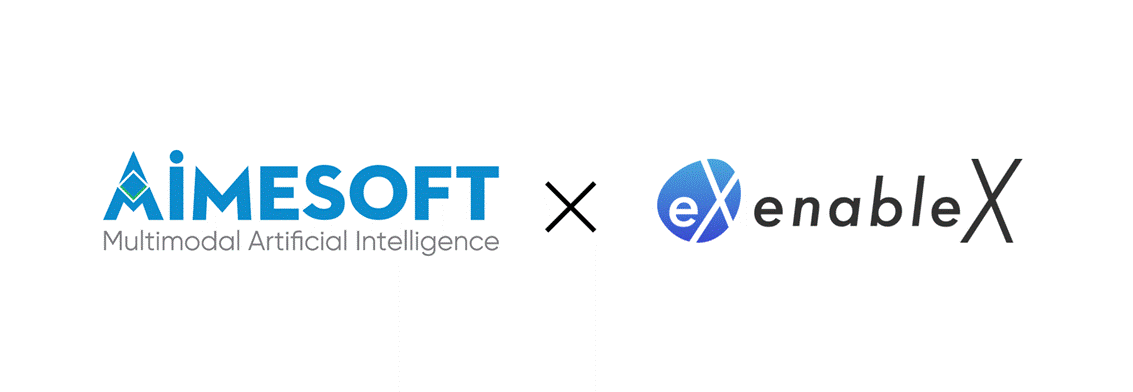 enableX、AimesoftとAI社会実装・顧客サービス提供に関する共同スキームのアライアンス締結
enableX、AimesoftとAI社会実装・顧客サービス提供に関する共同スキームのアライアンス締結弊社は、Aimesoft Joint Stock Company(本社:Yen So 1, Duong Hoa, Hanoi, Vietnam、代表取締役:グェン トアン ドゥク、以下「Aimesoft」)と、AI社会実装を促進していくためのアライアンスを締結し連携を強化してまいります。プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000147732.html Aimesoft社について 2018年設立。複数のアルゴリズム(⾳声処理、⾃然⾔語処理、画像処理、ビッグデータ、データマイニング、テキストマイニング)及びデータ種類を融合した、「マルチモーダルAI(Multimodal AI)」を独⾃開発。⼈間が視覚や聴覚から対象物を識別するのと同様に、画像や⾳声、⾔語、複数のモダリティで処理を掛け合わせることで、より⾼度な認識が可能にしています。すでに大手日本企業とも多数の協業実績があり、この技術をバーチャル受付システム、バーチャルヒューマンなどに適用。顔認証システム等、マルチモーダルAIに関する特許も取得しています。東京大学、パリ大学、米国の大学等出身のAI有識者が数多く在籍。Top 10 AI companies in Vietnam in 2024受賞 グェン トアン ドゥク氏について 東京大学博士(情報理工学)。数多くの論文での受賞実績・特許保有。企業でAI関連の研究・開発を主導。官民で複数のLLMをファインチューニング、事前学習段階から構築し実装した実績を有しています。高速GPU適用やインフラ技術実装にも精通。2018年にAimesoft(ベトナム)を設立し、 マルチモーダルAIの先駆者としてAI技術の研究・開発・社会実装を日本及び東南アジアで推進しています。
-
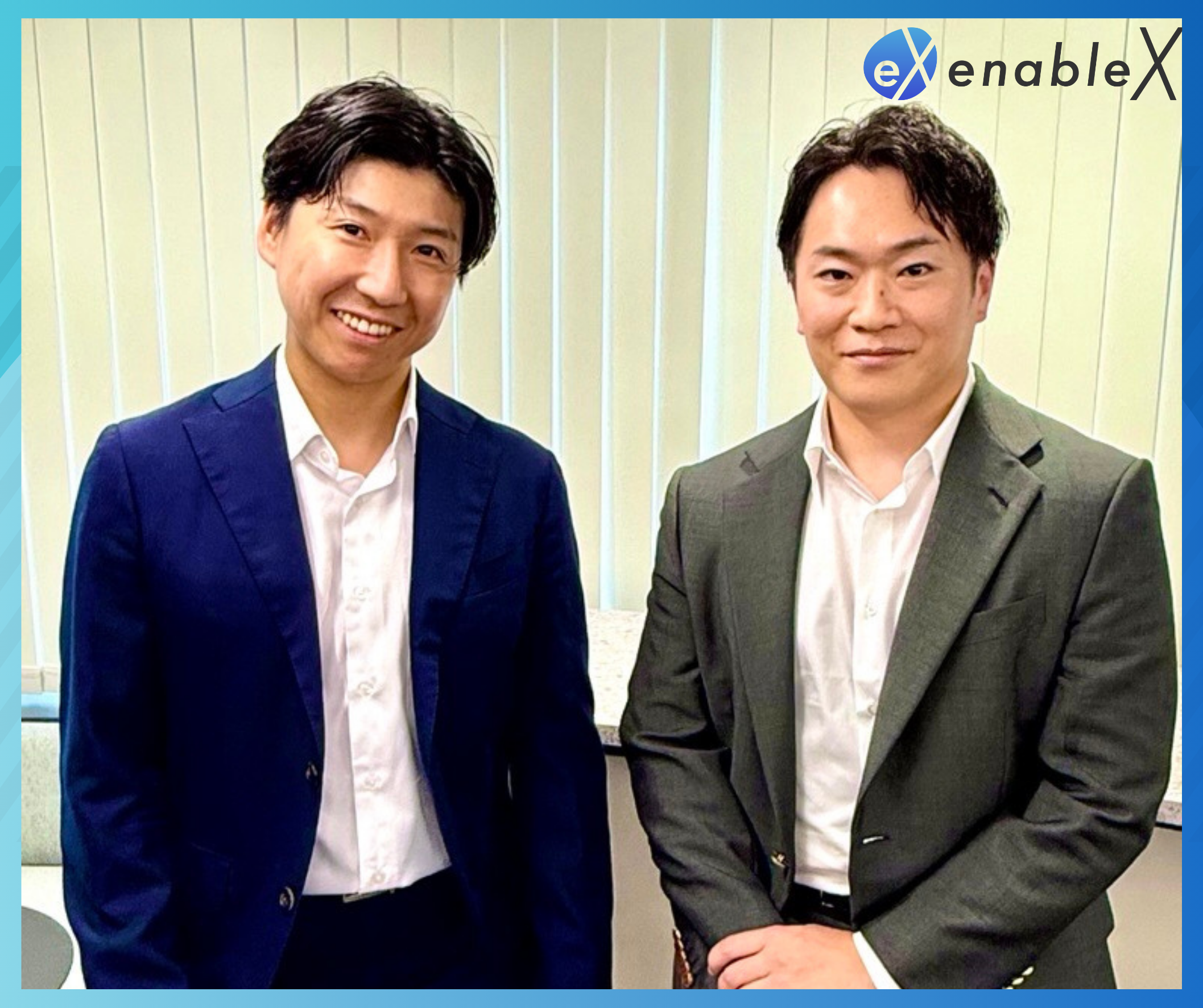 【M&A】事業創出支援のリーディングカンパニー、ストラテジーキャンパス社買収のお知らせ
【M&A】事業創出支援のリーディングカンパニー、ストラテジーキャンパス社買収のお知らせ「株式会社enableX」は2025年9月30日に株式会社ストラテジーキャンパスの全株式を取得し、完全子会社化することに合意したことをお知らせいたします。 買収の背景と目的 enableXは事業開発の専門集団として、「事業開発の在り方を変える」というミッションのもと、AI時代における事業開発の在り方を再定義し、事業開始わずか2年目にして取引規模20億円超を突破する成長を遂げています。 今回の買収は、enableXの成長戦略の一環として、以下の目的で実施いたします: 事業開発コンサルティング機能の強化 ストラテジーキャンパスが保有する300プロジェクト以上の事業創出実績と体系化されたメソドロジーを統合 大企業向け新規事業開発支援における圧倒的なノウハウの獲得 クロスボーダー体制の強化 グローバル企業との豊富な協業実績を活用した国際展開力の向上 海外エキスパートネットワークとの連携による提供価値の拡大 株式会社ストラテジーキャンパス 代表取締役社長 中村陽二 コメント この度、目標・価値観を共有出来るenableXへの参画を発表出来ることを大変光栄に思います。 体制強化を通じ、弊社が注力してきた「グローバル展開」および「M&A・出資を活用した成長」に関するサービスの幅、品質、キャパシティを大きく拡張することが可能となりました。今後はこれまで以上に「事業創出と成長を牽引するパートナー」として、皆さまの期待にお応えして参ります。 株式会社enableX 代表取締役CEO 釼持駿 コメント プロダクトライフサイクルが短期化し、事業環境が激変する中、企業にとって継続的な事業創出能力は非常に重要なものとなっています。今回のM&Aにより、両社の事業創出・グロースノウハウを融合させ、従来の常識を超えたスピードと精度で事業を構築する仕組みを築いて参ります。 期待されるシナジー効果 本買収により、以下のシナジー創出を見込んでいます: AI×事業創出の新たな価値提供 enableXのAI技術とストラテジーキャンパスの事業創出メソドロジーの融合 データドリブンな事業開発プロセスの確立 AIを活用した市場分析・事業機会発見の高度化 サービスポートフォリオの拡充 事業構想から実装・グロースまでの一気通貫支援体制の確立 グローバル展開を含む総合的な事業開発ソリューションの提供 顧客基盤の相互補完 両社の顧客ネットワークを活用した事業機会の拡大 大企業からスタートアップまで幅広い顧客層への価値提供 今後の展開 ストラテジーキャンパスは、enableXグループの中核企業として、これまで培ってきた事業創出の専門性を最大限に活かしながら、AI時代における新たな事業開発モデルの確立に取り組んでまいります。両社のシナジーにより、「事業開発=enableX」としてのブランド確立を加速してまいります。 株式会社ストラテジーキャンパスについて 名称株式会社ストラテジーキャンパス所在地東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階代表者代表取締役 中村 陽二事業内容戦略コンサルティング役員経歴代表取締役 中村 陽二 幼稚園・小学校をインド・ニューデリーにあるAmerican Embassy Schoolで過ごした後日本へ。東京大学工学部電気電子工学科卒業・東京大学工学研究科修了。大学院在学中にコンピュータサイエンス領域で行った研究発表が評価され、一般社団法人 情報処理学会(IPSJ)より2014年度コンピュータサイエンス領域奨励賞を受賞。 新卒でマッキンゼー&カンパニー入社。製造業、IT、オイル&ガス。成長戦略、M&A、JVに主に携わる。 マッキンゼー&カンパニー退社後、株式会社サイシード創業。人材関連企業を買収し、代表取締役として事業再生を実行。営業利益-3,000万円の状態から+4,000万円の状態に再生し売却。 売却先の企業で取締役に就任。2021年6月に東証グロース市場に上場。上場企業経営に取締役として携わる。 代表を務める会社においてAI事業を立ち上げ成長を牽引。事業開始6年で売上は20億円、営業利益は11億円に到達。2023年5月投資ファンドへ売却。 創業まもなく取締役として参画したプロジェクトカンパニーが2021年9月東証グロース市場上場。 売上500億円以上の企業を中心とした新規事業・投資アドバイザリーを、株式会社ストラテジーキャンパス代表取締役として多数経験。特に北米・欧州地域おける成長戦略策定、参入実務、M&Aを含む資本業務提携を推進。URLhttps://strategy-campus.jp/ プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000147732.html
-
 【サービス】enableXが実現するマーケ x AIの最前線
【サービス】enableXが実現するマーケ x AIの最前線株式会社enableXは、同社の最新技術と取り組みを紹介する3本の記事を公開しました。デジタルマーケティングにおけるAI活用の最前線から、データ分析の民主化、そして予測LTVマーケティングまで、企業のデータドリブン経営を支援する革新的なソリューションを詳しく解説しています。 公開記事一覧: 「顧客の未来価値を予測する」enableXが語るPredicted-LTVマーケティングの実践 URL: https://enablex-inc.com/insight/0000010/ 人口減少と市場縮小が進む中、顧客の将来価値(Predicted-LTV)を機械学習で予測し、集客と育成の分断を解決する新たなマーケティング手法を、釼持駿代表取締役CEOと倉本岳執行役員が解説 「データ分析の民主化を実現する」Snowflake Cortexから始めるenableXが挑むAIエージェント活用の最前線 URL: https://enablex-inc.com/insight/0000009/ データ分析業務の属人化と非効率性の課題を、AIエージェントとSnowflake Cortexを活用して解決するビジョンと実装への具体的なロードマップを倉本岳執行役員が紹介 「配信ミスゼロの世界へ」enableX社が挑むAI活用によるマーケティング自動化の最前線 URL: https://enablex-inc.com/insight/0000011/ FigmaからAdobe Campaignへのコンテンツ配信テストをAIで自動化し、配信ミスを防ぐ革新的なソリューションと、MCP(Model Context Protocol)を活用した次世代マーケティング自動化について倉本岳執行役員が解説 これらの記事では、enableXが「人+AIエージェント」の体制で実現する、データクレンジングから構造式モデリング、マーケティング施策の実行まで、包括的なデータ活用支援の具体例が紹介されています。同社は、生成AIとデータ活用を通じて、企業のマーケティング領域でのデータ活用を支援し、真のデータドリブン経営の実現を目指しています。 詳細は各記事リンクからご確認ください。
-
 【記事】事業開始2年目で取引規模20億円以上。enableXが証明する「事業開発の新常識」
【記事】事業開始2年目で取引規模20億円以上。enableXが証明する「事業開発の新常識」2025年6月に発表した3社のM&A実行の背景や今後のenableXが実現を目指すビジョンに関する記事を公開したことをお知らせいたします。 記事:AI時代の事業開発を再定義するenableXが描く成長戦略
事業開発ならenableX
革新的なAIテクノロジーと高度な事業開発の専門性で次世代の事業開発サービスを提供します
事業専門性とAIテクノロジーにより、
最適な人数で最高の結果を
グローバルに提供します
- CASE01
- CASE02
- CASE03
事業家が事業入り込む
コンサルではなく、実績を有する事業家・専門家が戦略から実行まで一気通貫
-
POINT01実経営を行ってきた事業家が「自社メンバー化」するレベルで深く入り込み、コミット
-
POINT02事業グロース機能を統合的に提供することで部分最適に陥らず、一気通貫の戦略・実行が可能
-
POINT03グローバル知見を豊富に有し、クロスボーダープロジェクトを一気通貫で実行
革新的テクノロジー
プロジェクトの省人化・高付加価値化
-
POINT01独自のAI技術を活用することで業務自体を省人化し、より効率的に、効果的に
-
POINT02弊社テクノロジーをお客様にも提供することで、DXを超えたDGX(Digital Growth Transformation)を実現
専門人材オンデマンド
5万人の専門人材DBで専門性の強化とリソース不足を即カバー
-
POINT011,700人/月が稼働する5万人が登録する人材プラットフォームを有しており、必要な専門家を配置可能
-
POINT02「人材が足りない」問題を、短期的に解消。長期雇用リスクを負わずに専門家を活用できる
グローバル・ワンストップで提供
実経営を行ってきた事業家や専門人材が
「自社メンバー化」するレベルでコミット 独自AIテクノロジーで省人化・効率化を徹底し、
高生産性チームが事業を共同推進

MEMBER
起業から上場・バイアウトの経験者と、先端テクノロジーに精通したグローバル人材が集結
-

釼持 駿
Shun Kemmochi代表取締役CEO
コンサルティングファーム、P&Gを経験。トップクラスのマーケティング知見を有し、経営戦略・事業開発・マーケティングにおけるコンサルティング実績を多数有する。事業家としても上場企業への事業売却を含む3社の起業・売却の実績を有する。投資家としても、出資・ハンズオン経営を行い、企業価値を向上させ、エグジットをさせるなどの実績を有する
-

中村 陽二
Yoji Nakamura取締役
マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社し主に製造業の成長戦略やM&Aに携わる。退職後、サイシード社を立ち上げAI関連事業を開始し、5年間でゼロから売上20億円営業利益11億円まで成長させる。サイシードを全研本社へ売却後、取締役として2021年東証マザーズ上場を経験。株式会社プロジェクトカンパニー取締役として参画、2021年東証マザーズ上場。 著書「インサイト中心の成長戦略」はベストセラー
-

周 涵
Zhou Han執行役員 エグゼクティブディレクター
マッキンゼー・アンド・カンパニーにおいて、AIやデジタル活用等のプロジェクトを担当。その後、AI事業に取り組むニューラルポケット株式会社にて取締役 COOとして、2020年8月に東京マザーズ市場へのIPOを達成。2023年からは、LLM開発を行う企業でもCOOを担当。ニューヨーク証券取引所上場企業である51Talk Online Educationグループのシニアアドバイザーや大手通信キャリアのデータ企画部門等大手企業の顧問も歴任
-

韓景旭
KyeongUk Han執行役員 エグゼクティブディレクター
米国系コンサルティングにて 製造業、商社、物流企業などのクライアントの海外進出や新規事業案件に参画後、2017年からはBtoB SaaS スタートアップの日本事業立ち上げを担当。2022年からは韓国育児用品ブランドの日本代表を務め日本事業にて数億円規模まで成長を牽引後、2023年からは韓国最大手VCのVenture Partnerとして日本投資およびポートフォリオの日本進出をサポート。
2024年からは日本企業向けの韓国進出サポート事業を開始し、複数の企業の韓国進出や韓国スタートアップとの協業を実現。 -

小村 淳己
Junki Komuraエグゼクティブディレクター
アクセンチュア/KPMG/ロベンダルマサイにおいて、管理職とAI企業の執行役員歴任。デロイトでは、AI研究組織の立上げ、NRIでは、新設AIコンサルティング部で事業創出・サービスデリバリー。DX案件は、SCM・ERP領域で数十億~数百億円規模PF構築のPJ構想~推進、年二桁億円の定量効果創出。AIファームでは、事業開発×コンサル事業を立上げ。年20件程度のお客様向けのAI案件組成しBiz・Tech活動を主導。電気工学&経営学修士(MBA)、JDLA Engineer資格&Generalist応用脳科学プラクティショナー
-

坪井 康彦
Yasuhiko Tsuboiディレクター
デロイトトーマツ、BCG出身のデジタルプロダクト・マーケティングのスペシャリスト。デザイン思考を起点に、戦略策定からプロダクト開発・オペレーション変革まで一気通貫の変革プロジェクトを複数推進。Web最適化・UX設計領域において、John Allsopp氏やUX DAYS TOKYO主催・菊池崇氏らと連携した活動にも従事し、ビジネスとクリエイティブをつなぐデジタル変革の基礎素養を形成。直近はアイデミーの取締役としてM&Aをけん引
-

山崎 雄太
Yuta Yamasaki執行役員 エグゼクティブディレクター
2013年にFacebookへ入社。マネージャーとしてコールセンターの管理を担当する傍ら200社以上の広告主にFacebook広告の支援を行う。 2014年には3億円の広告費を20億円まで伸ばしたことで、 アジアNo1の営業成績を残す。 2015年2月よりシンガポールに異動し、パートナーマネージャーとして広告代理店との協業事業の推進及び、東南アジアの新規パートナーの開拓を担。
2017年よりNetflix Japanに入社、デジタルマーケティングの責任者を担当。 2018年より、起業し他業界へのGenAIを活用したマーケ支援を実行 -

真嶋 良和
Yoshikazu Majimaエグゼクティブディレクター
博報堂(クリエイティブ領域/デジタル推進)、LITALICO(CMO、3事業部のリブランディング)、トランスコスモス(CX領域全般)と、代理店/事業会社という枠に囚われないマーケティングCX領域に関する幅広い経験を有する。クリエイティブ領域では、カンヌライオンズ、クリオ賞、The One Showの世界三大広告賞での受賞歴あり。トランスコスモスでは上席常務執行役員として、CX事業統括副責任者・デジタルエージェンシー本部長を務め、2021年就任以降100億円超の事業成長を実現。同時に子会社BrandOperationでCEOコンサルティング事業を統括
-

今 佑介
Yusuke Konディレクター
大手SIerにてWebシステム開発を担当し、その後数社を経てベストティーチャーではオンライン英会話サービスのCTOとして、開発‧PM‧採用を統括。2016年よりフリーランスとして技術顧問‧コンサルティング‧システムデザインを実施しながら株式会社UZUMAKI CTOとして、DeNA「Pococha」 やMIXI「みてね」など大規模サービスのSRE領域を担当。現在はenableXでディレクターを務める
-

倉本 岳
Takeshi Kuramoto執行役員 エグゼクティブディレクター
大手教育会社において、教育事業のマーケティングに従事。 退職後、国内ブティックファームにおいて大手上場企業向けにDX戦略や人材開発、マーケティング戦略プロジェクトをリード。 その後、コンサルティングファームの立ち上げに経営参画し、事業拡大を推進。上場企業への売却を達成している
-

長谷川 寛一
Hirokazu Hasegawaマネージャー
投資銀行部門にてカバレッジ・社債引受業務に従事。電力、鉄道、NTTセクター担当
KPMG FASにて、M&Aや事業再生の財務DDおよび企業価値算定業務に従事。シリーズB以降の支援からターンアラウンドまで幅広いプロジェクトに参画
退職後、関東での障がい者向けグループホーム事業を展開。事業を拡大し、バイアウトを実現 -

越智 誠
Makoto Ochiシニアマネージャー
サムスン電子日本法人、EYストラテジー・アンド・コンサルティングなどにおいて、事業・予算管理、新規事業構想策定などに従事する。 直近では、EC事業を展開する事業会社の経営企画として、全社の予算策定や中長期計画策定、新規事業立ち上げや事業グロースの業務を推進する。注力事業グロースプロジェクトにおいて 対予算比200%達成を達成する
-

荷福 裕行
Hiroyuki Nifukuマネージャー
ソフトウェア開発、インフラ等、ITに関する広い範囲でエンジニアとして従事してきたバックグラウンドがあり、国内のコンサルティングファームでは、ソフトウェア・ハードウェアに関する理論、基礎、応用技術等の知識をベースに、開発(下流)から要件定義・管理業務(上流)までをリード
-

吉岡 浩
Hiroshi Yoshioka顧問
ソニー株式会社エンジニアリング部門でビデオカメラのエンジニアとして活躍した他、事業開発、研究開発など多岐に渡る業務を経験。2001年には、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の社長に就任し、2003年には親会社であるソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズABのCVPとしてスウェーデンに赴任し、携帯電話開発を統括し、グローバルな事業の拡大と業績改善に大きな貢献。2009年には執行役副社長に就任。2012年末に退職後、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の社外取締役等多くの企業を支援
-

萩野 貴拓
Takahiro Hagino技術顧問
2014年 株式会社ビズリーチに入社し求人検索サービス、研究開発部門(現AIグループ)の立ち上げに従事
現在は先端技術を活用した製品の企画およびアプリケーション開発をリード。技術書の執筆やDLTの研究会の発起、オープンソースコミッタとして活動を行いながら、技術顧問やCTOとして大企業からグロース企業まで幅広い業種、業界での支援実績を持つ
事例紹介
case-
マーケティングBPS 事業開発ラボ 通信業界
若年層とのデジタルタッチポイント拡大
若年層の顧客基盤拡大を行うために、全社BXを構築し、その中で新規のデジタルチャネルの企画・開発・グロースを全方位的に支援。取得した顧客データを元にしたマーケティングにより回線契約促進を実現できており、立ち上げ2年で3,000万PV、50万人以上の会員化を達成しています
-
SI業界 クロスボーダー 事業開発ラボ
blockchain事業立ち上げ・アライアンス構築支援
ブロックチェーン技術を活かして、市場にまだ無い新しいプロダクトの企画・開発・PoCをコンソーシアムを組成して行い、PoCの成功を達成しております
-
FMCG業界 マーケティングBPS 事業開発ラボ
加熱式たばこユーザーとのデジタル接点強化
競合ユーザーの獲得を促進するデジタルサービスの企画・実行改善・運用を全方位的に支援。会員数の大幅な拡大を実現し、喫煙者に最も使われるデジタルサービスに成長させることができています
-
エンタメ業界 SI業界 デジタル事業変革
次世代システム基盤 構想策定のご支援
某社の情報提供サービスを支えるシステム基盤の今後の在り方について、方針・ロードマップ策定をご支援。弊社の技術的知見をもとにこれまで踏み出せなかったクラウド利活用など、モダナイゼーションへの取り組みの後押しを行いました
-
自動車業界 事業開発ラボ
BEVを活用した電力事業にかかる新規事業プロジェクト
大手自動車メーカー様におけるBEVを活用した新事業の創出に向け、構想策定から事業立ち上げまでを伴走型で推進しました
-
自動車業界 AIテクノロジー
工場内安全衛生リスクのAI自動識別PoC
工場内で日々発生する危険行為に対して、AI(画像解析)にて自動的にリスクを抽出する取り組みを推進しました
-
飲料業界 マーケティングBPS 事業開発ラボ
ジョブ調査~実行支援によるバリューアップ
若者向けリキュールブランドのマーケティング戦略開発と実行支援を行い、最終的には事業会社への売却によるエグジットを達成しました
ウェビナー
WEBINARホワイトペーパー
WHITE PAPERインサイト
INSIGHT-
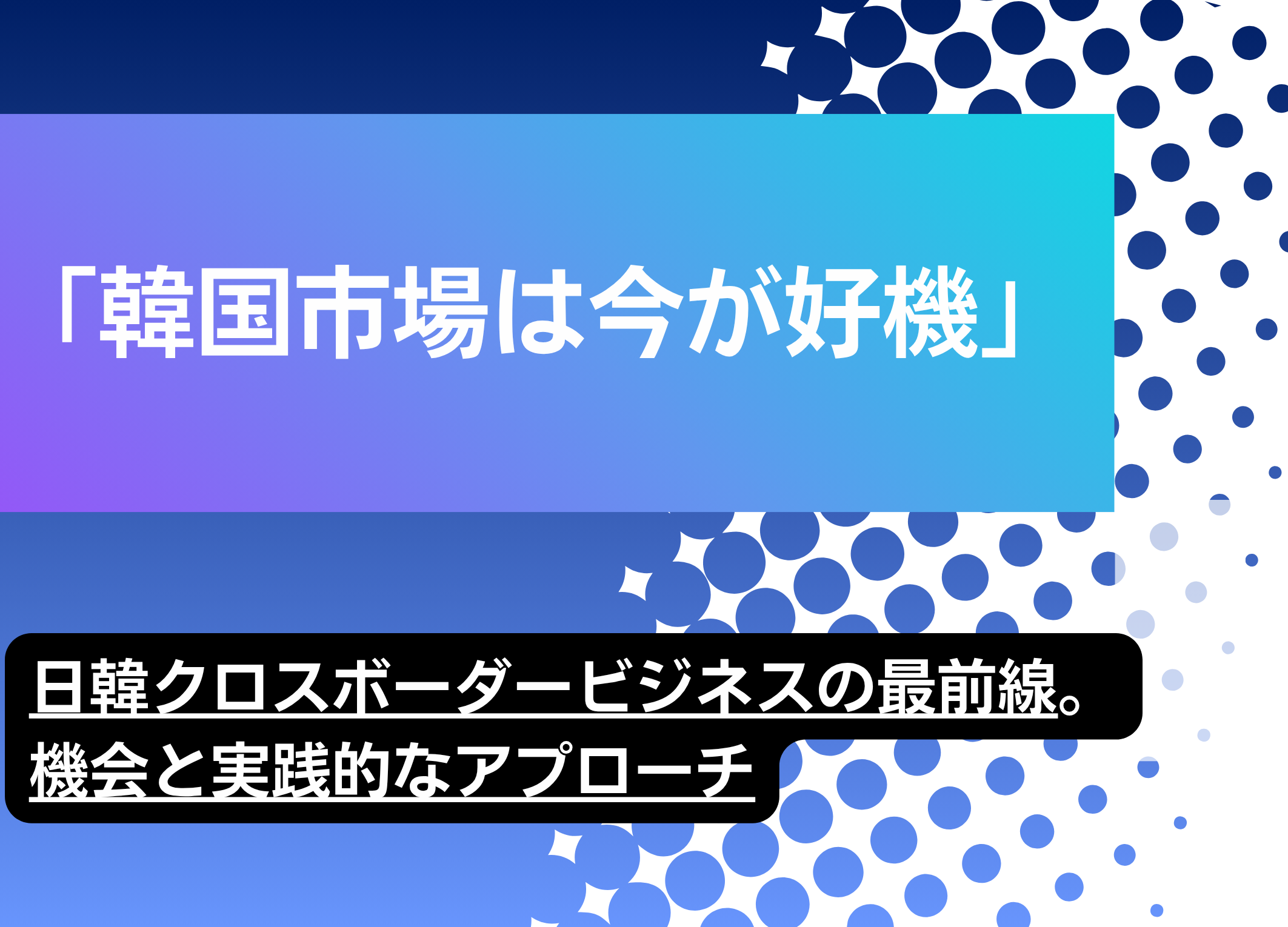 「韓国市場は今が好機」enableX韓執行役員が語る日韓クロスボーダービジネスの最前線
「韓国市場は今が好機」enableX韓執行役員が語る日韓クロスボーダービジネスの最前線日本企業にとって韓国市場はどのような可能性を秘めているのか。また、韓国企業の日本進出をどう支援すべきか。enableX執行役員の韓氏が、両国のビジネス環境を知り尽くした視点から、クロスボーダービジネスの機会と実践的なアプローチについて語った。 韓国市場の「今」を読み解く ——まず、現在の韓国市場の状況について教えてください。 韓氏:韓国市場は、一見とても良いようにみえています。KOSPIという韓国の株価指数は4,000ウォンを超え、数年前の2倍近くまで伸びています。不動産価格も高騰しており、ソウルの江南エリアでは、マンションを購入するのに3億円から5億円が必要という状況です。 外形上は好景気に見える一方で、若者の失業率は高く、賃金も伸び悩んでいます。ここに興味深い消費トレンドが生まれているんです。 ——どのようなトレンドでしょうか? 韓氏:不動産が高すぎて家が買えない。韓国では結婚する際に男性が家を用意する文化があるため、家が買えないということは結婚もしづらいという選択につながります。 その結果、若者たちは「未来への投資」ができない代わりに、「今の自分」にお金を使うようになりました。ブランド品や外車といったラグジュアリー品の消費が活発化しています。韓国はグローバルで見ても購買力の高いラグジュアリー市場として成長しているんです。 B2C市場の3つの機会 ——日本のB2C企業にとって、具体的にどのような機会があるのでしょうか? 韓氏:大きく3つの領域があると考えています。第一に、ラグジュアリー・嗜好品市場です。先ほどお話しした若者の消費行動の変化により、百万円から二百万円単位の比較的手の届くラグジュアリー品への需要が高まっています。 第二に、インバウンド市場です。韓国から日本への旅行客は年間700万人以上で、平均2.37回とも言われていて、日本を訪れるリピーターが非常に多い。購買力があり、複数回来てくれる、そして近いから来やすい。これは日本のインバウンド業界にとって非常に魅力的な市場です。 ——リピーターが多い理由は何でしょうか? 韓氏:今、最も購買力の高い30代から40代の韓国人は、子どもの頃から日本のコンテンツに親しんで育った世代なんです。私自身もそうですが、1990年代に北野武の『花火』が韓国で初めて上映された日本映画でした。その後、岩井俊二の『ラブレター』や、『スラムダンク』『ドラゴンボール』など、日本の文化が身近になった世代が今お金を持っている。 だからUSJの任天堂ワールドに行ったり、ワンピースのショーを見たりと、日本のコンテンツと関連した体験を求めて訪日しています。 ——第三の機会は? 韓氏:日本の食文化です。韓国も米が主食で、醤油・味噌文化があり、食事が非常に近い。韓国ではコース料理のことを「おまかせ」と言うくらい、日本の食文化が浸透しています。 実際、日本で修行した寿司職人が韓国で店を出すケースも増えていますし、居酒屋チェーンの鳥貴族も韓国に進出して、高級路線で展開しています。さらに、日本の化粧品ブランド「SHIRO」がソウルのソンスのエリアに路面店を出すなど、日本のB2C企業が韓国市場で活発になってきています。 B2B市場のポテンシャル ——B2B企業にとってはどうでしょうか? 韓氏:B2B市場も非常に大きな可能性があります。特に注目すべきは3つの領域です。 まず、コンテンツ制作のリソース市場です。韓国のデザイナーやエンジニアは、2000年代から日本のゲーム業界で活躍してきました。当時は人件費が安く、腕の良いデザイナーを雇えたため、Cygamesなどのゲーム会社の成長を支えたと言われています。 ——現在も同じ状況なのでしょうか? 韓氏:今は少し変わってきています。中国やベトナムに外注していた動画制作が、現地の人件費上昇とクオリティの課題から、「それならクオリティが担保できて近い韓国の方がいい」という判断になってきているんです。 実際、東宝や東映が韓国で制作スタジオを立ち上げていますし、今年12月にはソニーミュージックが韓国で5〜6年前から開催しているアニメゲームフェスタがあります。日本のコンテンツ業界は韓国を重要な制作拠点として見ています。 ——他の領域についても教えてください。 韓氏:第二に、エンジニアリングリソースです。韓国のエンジニア採用を専門とするKORECのようなサービスが登場していますし、日本のSI市場には昔から韓国人エンジニアが多く参入しています。第三に、B2B SaaS市場です。これは日本のスタートアップにとって特に興味深い機会です。 B2B SaaS企業が韓国を目指す理由 ——なぜ韓国がSaaS企業にとって魅力的なのでしょうか? 韓氏:日本のスタートアップは今、大型上場でないと機関投資家が入らない状況です。しかし、日本市場だけで300億円、500億円の評価額を出せる企業はそう多くありません。 そこで海外展開が必要になるのですが、アメリカは競合が強すぎる。東南アジアはB2B市場そのものがまだ立ち上がっていない。その中で、韓国は現実的な選択肢なんです。 ——具体的な成功事例はありますか? 韓氏:Datadog(データドッグ)というサービスは、グローバルで一人当たりの利益率が最も高い市場が韓国だそうです。 これは財閥系企業に一度導入されると、系列会社全体に広がるという特性があるからです。 また、セールスフォースとノーションも、グローバルで最も成長率の高い市場が韓国です。日本のSaaSでも、ジョブカンが韓国でうまくいっているという話を聞いています。 ——なぜ今、韓国でSaaSが伸びているのでしょうか? 韓氏:韓国はB2B市場がまだ成熟しておらず、CRMやSFAといったツールの普及率が低いんです。これまでの韓国の営業は関係値ベースで、科学化されていませんでした。 しかし、Z世代が台頭する中で、関係値だけではセールスが難しくなってきている。SFAのようなツールが必要とされる環境が整いつつあるんです。実際、チャネルトークはSMB向けに年間経常収益(ARR)50億円を達成し、エンタープライズまで展開すればARR100億円は狙えると言われています。 enableXの強みと支援の形 ——日本企業が韓国進出を検討する際、enableXはどのような支援ができるのでしょうか? 韓氏:私たちの強みは大きく3つあります。まず、チャネルトークでの立ち上げ経験です。韓国のスタートアップでは、日本で成功している企業はほとんどなく、その中でチャネルトークは代表的な成功事例です。そのため、韓国企業から日本進出の相談を受けた際、多くがチャネルトークの人脈を通じて私に紹介されます。 第二に、コンサルティングバックグラウンドです。特に韓国では「ブランド」が重視されるため、マッキンゼー出身者が多いenableXの経歴は大きなプラスになります。第三に、既存の大手エンタープライズ顧客を持っていることです。 ——日本企業側から見た価値は? 韓氏:B2C企業に対しては、チャネルトークの顧客がほとんどB2C企業であるため、そのネットワークを活用できます。市場構造の理解、現地パートナーとのマッチング、マーケティング戦略の立案まで、両国での実務経験を持つ人材は極めて少ないため、そこが私たちの差別化ポイントになります。 B2B企業に対しては、ローカルパートナーの発掘、イベント開催、インプリメンテーション支援など、現地の商習慣を理解した上でのサポートが可能です。 韓国企業の日本進出支援 ——逆に、韓国企業の日本進出はどのような状況でしょうか? 韓氏:韓国は起業の数が日本の10倍くらい多いんです。若者の失業率が高く、大企業以外で成功するのが難しい社会構造のため、起業せざるを得ない。しかし国内市場が小さいため、海外展開が必須になります。 日本市場は近い、政治的リスクが少ない、そして今は日韓関係が過去最高に良好です。そのため、日本進出を考える韓国企業が増えており、韓国政府も補助金を積極的に出しています。 ——どのような企業が日本市場に関心を持っていますか? 韓氏:B2C企業では、化粧品スタートアップが特に注目しています。APRILSKIN(エイプリルスキン)が時価総額1兆円近くになり、韓国のVCは化粧品に積極投資しています。d’Alba (ダルバ)など、資生堂がベンチマークするような企業が日本市場に出てこようとしています。 B2B企業では、SaaS企業が日本のDXの遅れに注目しています。日本は一度導入されるとなかなかやめない市場特性があり、これは韓国スタートアップにとって魅力的に映っています。 新たな展開:M&Aとオープンイノベーション ——最近の動きについて教えてください。 韓氏:実は今、韓国企業の日本企業買収のニーズが出てきています。先日、韓国の音楽関連企業から、日本のライブハウスやミュージックフェス、芸能事務所を買いたいという相談がありました。 また、日本の大手化粧品メーカーの役員の方とお話ししたのですが、アモーレパシフィックを徹底的にベンチマークしたいとおっしゃっていました。興味深いのは、アモーレパシフィックもその日本の大手化粧品メーカーを気にしているという点です。 ——お互いがベンチマークしている? 韓氏:その通りです。例えば、韓国のHyundai(ヒョンデ)は毎年、野村総研にトヨタの研究レポートを依頼しています。お互いへのベンチマーク関係を理解している私たちは、両方の企業をつなげることができる。これは大きな価値だと考えています。 オープンイノベーションという文脈でも、例えば韓国の化粧品スタートアップを集めて、日本の大手企業とのマッチングイベントを開催するといった展開も可能です。 不動産市場という新たな可能性 ——他に注目している分野はありますか? 韓氏:実は、不動産が最も大きな機会だと考えています。さきほどお話ししたように、韓国では不動産が高すぎて買えません。一方、日本の不動産は相対的に手頃で、韓国人は不動産投資が大好きなんです。 最近、私のいとこから「周りで日本の不動産に興味を持っている人がいるけど、どう思う?」という相談を受けるくらい、関心が高まってきています。規制が入る前に実績を作っておくことが重要だと考えています。 クロスボーダービジネスの未来 ——今後の展開について教えてください。 韓氏:日韓のクロスボーダーM&Aは確実に増えると見ています。実際、ケース数も増加傾向にあります。 例えば、韓国には日本のお菓子工場を買いたいスタートアップがあります。トヨタ紡織が今年3月にSK系列のバッテリー会社に20〜30%投資するなど、製造業を中心にサプライチェーン安定化のための投資も活発化しています。 ——最後に、読者へのメッセージをお願いします。 韓氏:日韓のビジネス環境は、今が最も良好な状態にあります。お互いの市場に対する関心も高まっており、政府の支援も手厚い。このタイミングを逃す手はありません。 重要なのは、両国の市場特性と文化を理解した上で、適切なパートナーと組むことです。私たちenableXは、両国で実務経験を持つ稀有なチームとして、お客様のクロスボーダービジネスを成功に導くお手伝いができると確信しています。 B2CでもB2Bでも、M&Aでもオープンイノベーションでも、日韓のビジネス機会を最大化したい企業の皆様と、ぜひお話しできればと思います。 プロフィール:韓景旭 株式会社enableX 執行役員 アーサー・ディ・リトル・ジャパンに入社後、 製造業、商社、物流企業など合計15社の幅広いクライアントの案件に参画 2017年からはBtoB SaaS スタートアップの日本事業立ち上げを担当 2022年からは韓国育児用品ブランドのPoledの日本代表を務め日本事業の短期立ち上げを実現 2023年からは韓国最大手VCのAtinum InvestmentのVenture Partnerとして800億円規模ファンドの日本運用をサポート。 2024年からは日本企業向けの韓国進出サポート事業を開始し、複数の企業の韓国進出を支援
-
 デンソーウェーブ・ビジネス開発室が実践する新規事業開発とenableXの活用
デンソーウェーブ・ビジネス開発室が実践する新規事業開発とenableXの活用■ 株式会社デンソーウェーブ・ビジネス開発室 |活用事例インタビュー 2022年からenableX(旧ストラテジーキャンパス社)は、デンソーウェーブのビジネス開発室のご支援を始め、主に新規事業に関するサポートをさせていただいています。 デンソーウェーブは、モノづくりの現場で培ってきた、産業用ロボットや自動認識の技術や知見・経験を活用し、さまざまな分野で革新的なソリューションを提供されています。 もともと技術開発を強みとしていましたが、特に近年では市場のニーズを的確に捉え、新たな事業機会を創出するための取り組みにも力を入れていて、その一環として、ビジネス開発室を立ち上げ、社内外のリソースを活用しながら、新規事業の開発を進めていると伺っています。 当初、技術視点で社内リソースを活用した新規事業に取り組んでいましたが、マーケット起点でより幅広い領域のビジネス開発を進めるにあたり、外部との連携や市場の視点を取り入れることが重要と考え、当社の支援を活用いただきました。 当社は、単なるフレームワークの提供にとどまらず、実務に即した支援を強みとしています。ビジネス開発室の皆様がどのように当社の支援を活用し、新規事業の創出に取り組んでいるのか。その過程で得た学びや成果について、インタビューを通じて詳しくご紹介します。 新規事業開発において、実際に行動し、試行錯誤を重ねることが成功への鍵となります。本記事では、ビジネス開発室が直面した課題や、当社との協働を通じて得た気づき、事業開発の実践的なプロセスについて深掘りしていきます。 PDFファイル URL:http://enablex-inc.com/wp-content/uploads/2025/10/Interview_densowave.pdf デンソーウェーブ・ビジネス開発室 星名一平氏 ■ デンソーウェーブ・ビジネス開発室における新規事業創出への取り組み −− 本日はよろしくお願いいたします。 デンソーウェーブは、モノづくりの現場で培ってきた、産業用ロボットや自動認識の技術や知見・経験を活用し、革新的なソリューションを提供されていますよね。 特に近年は新規事業開発にも力を入れられておられ、その中で当社をご活用いただいています。 お話をお伺いするのをとても楽しみにしていました。 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 −− 早速ですが、新規事業を本格的に立ち上げる動きはいつごろから始められたのでしょうか。 私が所属するビジネス開発室は2012年よりスタートしており、当社のコア技術を起点にイノベーション創出にチャレンジし始めました。 2018年頃からBizDev機能を強化し、マーケット起点・顧客起点にシフトしていったイメージになります。当初は技術探索が中心でしたが、次第に課題起点のアプローチへと進化しました。 −− ビジネス開発の新規事業の業界や領域はどのように定められているのでしょうか。 設立当初から業界・領域にとらわれず、全領域を対象にしています。 直近では、エネマネやインフラ、セキュリティの領域を注視しています。 私が入社した2020年当時のメンバーは5名程度で、改めて、ビジネス開発室としてMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を明確にする合宿を実施し、「社内外のリソースを問わず、既存の枠組みを超えて、新しい課題を見つけていく。」というミッションを掲げて、事業を進めています。 −− なるほど。現在当社をご活用いただいていますが、外部の企業を活用しようとなった経緯を教えていただけますでしょうか。 当社が技術を強みとした企業となるので、自社だけでは新規事業も技術視点に偏ってしまい、新しい視座が得にくいという課題がありました。 また、固定化されたメンバーではアイデアも枯渇していく感覚もありました。 そこで、外部との連携を深め、新しい発想を取り入れる必要があると考え始めました。 実際、オープンイノベーションの取り組みを進め、外部のネットワークとつながることで新たな視点を得ることができたと実感しています。 −− 特にメーカーであると、新規事業の発想も技術・商品起点になってしまいますよね。 「0 → 1」の新規事業に取り組む際、新しい領域を調査する「人員・部隊」が必要となり、これを内製化するかアウトソースするかが論点になってきますが、知見がないと初めから内製化は難しいですよね。 また、「アウトソース」には外部委託だけでなく、スタートアップにマイノリティ出資なども含まれてきます。 私のおすすめの方法としては、「内製化」と「アウトソース」の両方に取り組むことです。 「アウトソース」する際、自社で一定知見がなければ、どのようにコンサルを使えば良い変わらないですし、出資先もわかりません。 とてもよくわかります。 私たちもはじめは社内だけで行っていたのでわからないことばかりでした。 一方、実際にビジネス開発室として、新規事業に取り組んでいるからこそわかることがあると実感しています。 また、全てを外部委託してしまうと、社内にナレッジも蓄積されず、あまり良くない意味で外部企業に依存してしまうと感じてしまいます。 −− そうですよね。では、enableX(旧ストラテジーキャンパス社)をご活用いただき印象的だったことはありますでしょうか。 単なる「フレームワーク」に当てはめるコンサルティングではなく、「事業の根本的な考え方」や「実務に即した行動」を重視している点が非常に印象的です。 フレームワークは属人化を防ぎ、一定の再現性を確保できる良さがありますが、事業会社の現場では「行動」が最重要となります。 フレームワークを活用した戦略・計画が行動をともなっていないと、戦略・計画の意味をなしていないとも感じています。 その点、enableX(旧ストラテジーキャンパス社)は、実務で成果を出すことを重視されているコンサル会社で、このサポートがあったから前進出来ていると実感しています。 −− 私たちは如何に実務で成果が出せるかに重きをおいているので、そのように仰っていただきありがたいです。 また、世の中のトレンドとしても、フレームワークだけが独り歩きしてしまっている雰囲気がありますよね。 私はコンサルティング会社から事業会社を経験し、事業会社で「行動」が重要であると実感しましたので、現在のenableX(旧ストラテジーキャンパス社)のコンサルティングのスタイルにいたります。 フレームワーク自体はとてもわかりやすく、社内外の説明などでも使い勝手が良いんですが、それに縛られると「フレームワーク症候群」になりかねないとも感じています。 −− 「フレームワーク症候群」にハマってしまう方も多いですよね。 その要因の一つとして、「正解」を追い求めてしまう方が多いのではないかと考えています。 フレームワークを活用すると、みんなが理解しやすく「正解らしいこと」にたどり着けますので。 そうですね。 実際私も新規事業を進めるにあたり、フレームワークから入り、エッセンスを拾えて満足していた時期がありました。 「正解」に関しても、仰られる通り、多くの方は答えが欲しく、フレームワークに飛びついてしまいがちですが、実践するにあたり中身が足りないと気づくことが多いかと思います。 ■ コンサルティング会社の活用 −− ビジネス開発室では、自社内で新規事業を推進するにあたり、情報収集はどのようになされていたのでしょうか。 「まちなか探索レポート」という取り組みを行っており、実際に街に出て気づいたことをレポートし、従来考えたことがなかった視点を部内で共有しています。 また、新規事業の機会探索をしている業界のリーダーへインタビューを行い、業界のリアルな市場の感覚やインサイトを得るようにしています。 あとは、机上の議論となりますが、「もし〇〇業界から、△△がなくなったら、事業にどのような影響が起きるか?」や「特定の業界のサプライチェーンを川上から川下でマッピングし、当社としてどのような参入余地があるか?」などから考えることも行っていました。 −− なるほど。様々な施策に取り組まれていたんですね。 また、各業界の有識者へのインタビューは情報の鮮度や解像度が高くとても有益ですよね。 インタビューイーはどのように設定されていたのでしょうか。 知人を介して、属人的なコネクションを活用し、インタビューをさせていただいていました。 −− インタビューは紹介経由が有効ですよね。 初対面の方に正面からインタビューを申し込んでも、中々受け入れていただけませんので。 当社のようなコンサルティング会社をどのように探されていたのでしょうか。 コンサルティング会社を探していたチャネルはウェビナーです。 また、事業創造のための伴走パートナーとして、コンサルティング会社を活用する目的でいました。 そして、ウェビナーを介し、有名な大手ファームやデザインファームなどを含め、複数のコンサルティング会社とお話させていただきました。 enableX(旧ストラテジーキャンパス社)を活用させていただくまでは、デザイン思考を得意とするコンサルティング会社を活用させていただいていました。 デザインファームのご支援は新規事業を立案する「型」を学ぶ点でとても有益でした。 一定学習は行えたと考え、より実践的な伴走を求めて活用させていただくこととなりました。 学んだ型も実践的な支援のおかげで活かされており、私達の新規事業のステージも上がったと実感しています。 −− ありがとうございます。 コンサルティング会社の伴走支援に期待していることはどういった内容でしょうか。 コンサルを受ける企業側のステージやステータスにもよるかと思います。当時のビジネス開発室が求めることは事業課題を突破できる「現場感覚を持った鋭さ」でした。 貴社は、豊富な知見と実務経験があり、現場の感覚を持たれているのはもちろん、幅広い業界にネットワーキングが有り「現場感覚の鋭さ」を提供いただけています。 −− 机上や論理だけでなく、「現場感覚」は事業を動かす上で重要ですよね。 はい、多くのコンサルティング会社の事業伴走は、「形の綺麗さ」にこだわっている印象があります。 一方、enableX(旧ストラテジーキャンパス社)は形の綺麗さもあるんですが、現場を理解しているからこその「力技」や「気合い」なども合わせて、現場にしっくりくる形で実際の数字にも現れるご支援をいただいています。 また、アウトプットまでのスピードも早く、現場が円滑に回れているのもとてもありがたいです。 −− 事業を立ち上げた時は、だいたい「綺麗さ」ではなく、「力技」や「スピード」が必要になってきますよね。 はい。事業には論理だけでは動かせないことが多くあります。 また、貴社からは「力技」に加え、「インサイト」の大切さも学ばせていただきました。 新規事業のアイデアは複数浮かびますが、実際に事業として拡大し得るのかなどを考える際、「インサイト」が頼りになると痛感させていただきました。 −− 「インサイト」は重要ですよね。新規事業としてあり得そうなアイディアは大量にありますが、全ての調査は行えません。 なので、過去の知見などから「インサイト」を導き出し、絞り込んでいくことが大事になってきます。 初期のインサイトで一定領域を定め、軽くデスクトップリサーチを行い事業の仮説を立てると、領域に精通されている方にインタビューを行うなど、机上の調査よりも実務・行動に重きをおいたアプローチはとてもしっくりきました。 −− 調査対象の領域の中で実際に働かれている方は、だいたい正しい感覚を持っていますので、デスクトップサーチで悩むよりも、早い段階で有識者に聞いた方が効率良く進められると考えています。 ■大企業に「0→1」新規事業は必要か。 −− 新規事業には「0 → 1」と「1 → 100」の2つがあると思います。 ビジネス開発室で、新規事業に取り組まれている中で、新規事業の「0 → 1」と「1 → 100」の進められ方の違いは、どのように捉えられていますか。 「1 → 100」の新規事業は、既存事業の延長とも捉えることもでき、一定社内リソースを活用して進めることができます。 一方、「0 → 1」は社内リソースがほとんど使えず、ビジネス開発室のメンバーや外部リソースを活用することとなり、「1 → 100」と比較すると進めにくいことも多いなという印象があります。 また、1つの考え方・観点として、自社のリソースや社外ネットワークを考慮した上でとなりますが、一定の規模の企業は「0 → 1」をしないという選択肢もあるかとも考えています。 −− なるほど。私も大企業は「0 → 1」に取り組むべきか、辞めるべきかを考えたことがあります。 現在の私の考えとしては「取り組むべき」と考えています。 「0 → 1」に取り組むことで、事業領域の可能性が広がることはもちろんですが、既存事業の拡大を考えた際、少し隣の領域に参入する時でも「0→1」と同じ動きが必要となり、「0 → 1」を熟知していると上手く参入できると考えています。 −− 新規事業では、パートナー企業と一緒に進める場面もあるかと思いますが、パートナー企業についてはどのように考えられていますか。 新規事業を進める上でパートナー企業はとても重要で、enableX(旧ストラテジーキャンパス社)は、様々な業界に強いコネクションを形成されておられ、自社では手配出来ない協業や商談をいくつも実現いただけています。 例えば、エンタメ領域の新規事業を策定するに当たり、大手エンタテインメントグループをご紹介いただき、その企業はパートナー企業でありながら、顧客側の視点もあるのでとても助かっています。 新規事業を策定する上で、顧客の反応が最も大切と考えていますが、次いでご紹介いただいた企業のような顧客パートナー企業が大切と考えています。 −−幅広い業界における強いコネクションは、 enableX(旧ストラテジーキャンパス社)の強みの1つとしてあります。 実際、事業を進めるにあたり、顧客の立場でもあるパートナー企業のサポートは大きいですよね。 はい。今回のエンタメ企業もですが、いきなりビジネス開発室が直接アプローチしても、中々取り扱ってくれなかったと思います。 貴社が、エンタメ企業とビジネス開発室の事業構想を示していただけたから、エンタメ企業も向き合っていただけたと考えており、この流れは今後も続けていければと考えています。 −− パートナー企業に振り向いてもらうために、魅力的な事業構想は大事ですよね。 ■ 社内説得とプロダクト起点の実績づくり −− 新規事業にリソースを投下する際、社内説明で気をつけられていることはありますか。 新規事業として1円でも実績を残すことに重きをおいています。 実績があると、行動が客観的な事実として残り、社内にも説得しやすくなります。 「こうなると思うんです」ではなく「こうなると予測していたんですが、実際はこうなりました。」の方が100倍良いです。 −− 社内説明に実績は大切ですよね。 他のお客様からも、社内説得をどうすればいいかと聞かれることが多いのですが、今までみてきた成功例で共通することは「数字の力」と「発言者が権限を持っているか」の2つが複合的に合わさっているかが重要と考えています。 説明する人の立場や今までの信頼関係などが、聞いている側の納得度に繋がりますよね。 また、挙げていただいたことに加えて、実際にプロダクトを作って見せることも重要かと考えています。 −− プロダクトもそうですよね。 では、リソースが限られる中、完璧なプロダクトを作ることは難しいと思いますが、意識していることはありますか。 社内にプロダクト開発を得意とする方が多く在籍しているので、プロダクトごとに各領域のプロに相談することが多いです。 −− 新規事業にも活かせる社内リソースの活用は大事ですよね。 社内に協力者がいることで、新規事業の進め方が大きく変わってくると実感しています。 −− 社内の方からサポートいただけるように良好な関係を築いていくことは重要ですね 社内の関係性やネットワークは、コンサルティング会社のような外部の企業では、構築したり改善しにくい部分がありますので。 −− 本日はお時間いただき、貴重なインタビューの機会をありがとうございました! 引き続き、デンソーウェーブのご発展とご活躍を楽しみにしています。 □ 株式会社デンソーウェーブとは バーコード・QRコードリーダ、RFIDリーダの開発・設計・販売を手掛けるAUTO-ID事業、産業用小型ロボットの開発・設計・販売を手掛けるロボット事業、セキュリティコントローラ・プログラマブルコントローラの開発を担う制御機器事業、生産現場のIoTを提供するIoTソリューション事業の4つの分野で、産業界の生産性向上に寄与する製品をお届けしています。 会社名:株式会社デンソーウェーブ 所在地:愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番 代表者:代表取締役 相良 隆義 設立日:1976年6月 会社情報URL:https://www.denso-wave.com/ 革新的なAIテクノロジーと高度な事業開発の専門性を駆使することで、最適な人数で最高の結果をグローバルに提供する、事業開発ファーム 会社名:株式会社enableX 本社所在地:東京都千代田区麴町3-5-17 晴花ビル 4階・7階 代表者:代表取締役CEO 釼持 駿 設立日:2022年9月 会社情報URL:https://enablex-inc.com/
-
 M&Aで事業を拡大させるマクビープラネットのグループ戦略|マクビープラネットの経営層が語る企業経営
M&Aで事業を拡大させるマクビープラネットのグループ戦略|マクビープラネットの経営層が語る企業経営■ 株式会社Macbee Planet 代表取締役社長 千葉 知裕氏 近年、企業成長の手段としてM&A(企業の合併・買収)が注目されています。 特に、急成長を遂げる企業にとって、短期間で事業領域を拡大し、競争力を高める手段としてM&Aは極めて有効です。その代表的な事例の一つが、デジタルマーケティング業界で存在感を増す「マクビープラネット」の戦略です。 マクビープラネットは、電通グループや博報堂グループといった業界の巨大プレイヤーと対等に戦うため、戦略的なM&Aを推進し、グループ全体の成長を加速させてきました。 本記事では、マクビープラネットの経営層へのインタビューをもとに、同社がどのような視点でM&Aを捉え、実行してきたのかを深掘りしていきます。 M&Aを単なる規模拡大の手段ではなく、業界再編や企業価値向上のための重要な戦略と捉えるマクビープラネットの経営哲学に迫ります。 ※ 役職などは取材時点となります。(取材日:2024年10月10日) PDFファイル URL:http://enablex-inc.com/wp-content/uploads/2025/10/Interview_MacbeePlanet.pdf ■事業成長としてM&A戦略 −− 本日はよろしくお願いいたします。 マクビープラネットはデータを活用したマーケティング分析サービスを提供されていて、2023年には同業種でデジタルマーケティングサービスを提供されているネットマーケティングを買収されたことも記憶に新しいですね。 お話をお伺いするのをとても楽しみにしていました。 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 −− マクビープラネットは、積極的にM&Aを行っていますが、会社の戦略としてM&Aを意識されているのでしょうか。 マクビープラネットの事業戦略として、M&Aは強く意識しています。 広告代理店業界は、電通グループ・博報堂グループといった古くからの巨大な競合がいる中、マクビープラネットは後発で規模も小さい企業です。 大手企業と対等に向き合っていくために、短期間で成長し、今ないピースを取りに行くことを意識して積極的にM&Aを行っています。 −− 電通グループや博報堂グループと対等に渡り合っていくには一定の規模が必要になりますよね。 M&Aを意識されたのはいつごろからでしょうか。 本格的にM&Aを意識し始めたのは上場後からです。 上場当初から大型M&Aを行いたかったのですが、初めはマクビープラネットの規模も小さく大型案件は狙えませんでした。 なので、初めは比較的規模が小さい案件を見ていきながら、大型M&Aができる組織体制を構築していきました。 −− 小規模なM&Aを検討されていた主な目的は、将来に大型案件をするための組織体制作りだったのでしょうか。 目的として、将来大型案件を行うための組織作りもありましたが、あくまでも主目的は当時のマクビープラネットの企業ステージに応じた事業成長でした。 もちろん組織体制作りといっても、M&Aのためだけではなく、会社としてのコーポレートの組織体制を整えており、M&Aも含めた企業成長を考えていました。 −−なるほど。では、23年1月に行われたネットマーケティングのM&A(M&A金額54億円)はいつごろから検討されておられたのでしょうか。 ネットマーケティングのM&Aを検討し始めたのは、上場時の2020年にさかのぼり、上場当初から一番M&Aしたい企業がネットマーケティングでした。 当時の時価総額はネットマーケティングが120億円、マクビープラネットが60億円と、到底買える会社ではありませんでした。 そして、お互いの時価総額のタイミングを見計らいながら、良いタイミングで一気にM&Aに乗り出しました。 −− 上場初期からネットマーケティングのM&Aを検討されていたんですね。 ネットマーケティングのどのような点を魅力的と考えておられたのでしょうか。 広告業界には電通グループ・博報堂グループといった大きな双璧がいて、彼らと対等に戦っていくためには如何に速く規模を拡大できるか、が重要と捉えていました。 そして、マクビープラネットがサービスを展開するデジタルマーケティング領域の競合となる企業は、当時はネットマーケティングともう1社ほどしかありませんでした。 マクビープラネットの従業員や顧客企業の相性も考慮した上で、ネットマーケティングをM&Aの対象と考えていました。 また、顧客企業の相性の中にも、マクビープラネットが欲しいお客さんをネットマーケティングがお付き合いされていたことも魅力的に感じていたポイントです。 −− なるほど。打倒、電通グループ・博報堂グループの意図でM&Aを検討されたんですね。 一方、ネットマーケティングからすると競合企業であるマクビープラネットからM&Aされることに懸念があったのではないでしょうか。 そこが、今回のM&Aで配慮していた大きなポイントの1つでした。 私たちがネットマーケティングをM&Aする目的は、広告業界を変えていくことです。 ネットマーケティングとマクビープラネットの2社が合わさることで、業界再編できることをネットマーケティング CEOの靱江さんに伝えていました。 なので、M&Aの目的が、競合企業をM&Aし、ただ単に事業を大きくしていくことではないことをきちんと伝え、純粋に業界を変えていきたい気持ちを丁寧に会話していました。 −−競合企業のM&Aは捉えられ方を誤解されてもおかしくなく、純粋に思いを伝えることが大事ですね。 そうですね。競合企業なので、変に誤解されないようにしっかりと対話することを心がけていました。 また、M&A後にネットマーケティングとマクビープラネットに上下と思われる関係を作りたくなかったので、HD体制を取り2社の事業が横並びになる体制を取っています。 言葉も丁寧に扱い、子会社という言葉を使わずグループとし、一丸となって事業に向き合える環境を徹底しています。 −− 競合企業が同じグループになると、企業カルチャーや組織運営の違いなどから社員同士の動き方や現場への落とし込み方などに、難しさはあるのでしょうか。 MAVEL(旧:マクビープラネット)とAll Ads(旧:ネットマーケティング)の社員同士の特段小競り合いなどはありません。 (マクビープラネットは、ネットマーケティングを完全子会社化した後、持株会社体制への移行を進め、2023年11月1日付で完了。この移行に伴い、Macbee Planet準備会社は「MAVEL」に改称、ネットマーケティングは「All Ads」に改称。参考:URL) また、HDにはエンジニア部門、コーポレート部門、MAVELとAll Adsにはそれぞれ営業部門があるなど、MAVELとAll Adsとで、共通して活用できる部門はHDに配置しています。 また、21年にAlphaをM&Aしましたので、Alphaのエンジニアをそのままエンジニア部門として活躍いただいています。 −− M&Aした各企業や各人が適材適所で取り組まれているんですね。 ■成長を支えるエンジニア部門の組織エンゲージメント −− マクビープラネットでは、エンジニア部門の人たちはどういったモチベーションで働かれている方が多いのでしょうか。 エンジニア部門で働かれる方々は、自分のスキルやキャリアを磨くことがモチベーションとして働かれている方が多いと思います。 一般的に営業部門であると、社内の営業同士が同じお客さんに対してアプローチし、どっちが受注したかどうかなどが分かり、いがみ合いが生まれる可能性があると考えています。 一方、エンジニアはお互いが個人のスキルをリスペクトし合い、業務も他の方と比較するよりも、価値が出ているかを重視して働かれている方が多いと思います。 また、エンジニアのモチベーションを上げるためのマクビープラネットの取り組みとしても、エンジニア自身の能力が市場でどの程度通用するのかを把握するため、や新しい知見を得ていただくためにも、海外の先端事例などを共有する勉強会も催したりもします。 −− なるほど。では、グループ会社としてエンジニアの求心力をより高めるの工夫は、どのようになされているのでしょうか。 CTOの露木が非常に優秀で、エンジニアの方々は露木を中心に業務にコミットしており、エンジニア部門の組織構造も露木を中心としたピラミッド組織を取っています。 一方、逆に求心力がCTO頼りになってしまっていることも課題です。 また、HDにエンジニア部門を置いているので、事業やプロダクトとの距離が遠く、エンジニアが直接、事業・プロダクトの向上に100%コミットできる組織体制になっていないことも課題として挙げられます。 −− CTOの露木さんを中心にエンジニア部門が構成されているんですね。 エンジニア部門が事業・プロダクトから離れている組織構造ですが、プロダクトに対して責任を持っているのは別の部署となるのでしょうか。 いえ、プロダクトの開発の責任はHDのエンジニア部門が持っており、事業部は別の切り口で事業別(アフィリエイト事業、リスティング事業など)に責任を持っています。 一方、組織構造上、エンジニアはプロダクトの開発にフォーカスしているため、事業に対するコミットが薄くなってしまっています。 なので、組織的な課題としては、プロダクトを開発から拡大まで一貫して管轄するリーダーがいないところが、現状の課題と捉えています。 理想的には、各事業部(MAVEL、All Adsなど)に専属のエンジニア組織を置き、プロダクトの開発から事業拡大までコミットすることが事業成長の観点では良いとも考えています。 −− 一長一短で悩ましい問題の中、今後のエンジニア部門の組織体制はどのようにお考えでしょうか。 現状の組織体制の課題として、エンジニア部門と事業部を紐づけるための橋渡し役が不足していると考えています。 上記の課題をM&Aと紐づけて考えてみると、エンジニアの会社をM&Aし、エンジニアの組織と顧客基盤が得られたとしても、既存事業との接続は埋め合わせできないことが明確な課題として残ります。 なので、M&A先の理想的な企業としては、広告業界の経験がある事業開発部門やエンジニア部門を携える企業をM&Aしたいと考えています。 −− エンジニア部門と事業部をうまく繋ぐ、事業開発のニーズは高いですよね。 マクビープラネットの環境下で事業開発に求められる人材は、どのような素質や能力が必要と考えておられますか? マクビープラネットに必要な事業開発の形態は様々あると考えていますが、以下の2つの要素を重視しています。 1つ目が、多数の経営資源を組み立てられる能力。 2つ目が、業界歴があり、市場環境やデータ、現場からの声などから「将来こういうことが来るよね」と予測できる能力。 ブレイクスルーするためには、上記の2つの要素をうまく連携させる必要があると考えています。 −− 挙げていただいた2つの要素は非常にレベルが高いですが大事ですよね。 具体的にどのような経歴を持つ人が当てはまるなどの像はありますか。 事業開発として、コンサル出身の方は上手く稼働いただけると考えています。 先ほどお伝えした通り、マクビープラネットの現状の課題は、プロダクトを開発から拡大まで一貫して管轄するリーダーが不在で、エンジニア部門と事業部門を紐づける橋渡し役が不足していることが課題となります。 コンサルワークの1つとして、自らリーダーシップを取り、様々な分野の人をまとめ上げていくところにあると考えていますので、コンサル出身の方はフィットすると考えています。 また、社内の色々な方と関わり、事業をより深く理解しているという観点からも、中小規模の広告代理店やデジタルマーケティング企業で、経営企画を担われてきた方なども上手く稼働すると考えています。 −− 確かにコンサルや経営企画出身の方はマクビープラネットにフィットしそうですね。 一方、コンサル出身の方が事業会社に来るとコンサルっぽさをぬぐう必要があると考えていますが、その点はいかがでしょうか。 コンサルっぽさを消していただくのは確かにそうです。 みんなを巻き込んで事業を推進することが必要であり、事業会社でみんなが事業に向き合っている中で、理想を語る評論家になってしまうことは避けなければいけません。 また、もちろん1人採用するだけで、現状の課題を解決することは不可能だと考えていますので、チームを組成して取り組んでいきたいと考えています。 一方、チームアップの構想もまだまだ仮説段階であり、現時点は上記のような組織を作っていきたいなという段階です。 −− M&AはM&A前のPowerPointやExcelなどの構想上では上手くいきますが、会社の既存のリソースとマッチしないことも多数あると考えています。 マクビープラネットのエンジニア部門を見ると、CTOの露木さんを中心にうまくPMIが行えているかと思いますが、CTOは求心力を持つためにどのようなことをなされていたのでしょうか? CTOの露木は、Slackなどを活用して、情報共有が円滑に行える仕組みを作っていて、はじめは露木が調べたことや仕事の気づきなど積極的にみんなに共有していました。 また、社内でエンジニアの発表会をやってもらうことで、色んな人に認知してもらうことなども積極的に取り組んでいます。 また、通常業務外で合宿なども行い、露木を中心にチームアップされています。 マネジメント能力だけでなく、エンジニアとしての能力やスキルの観点からも、新入社員で露木の能力を知らない人は、「露木さんはすごいらしい」というイメージを持たれている方が多いです。 イメージで終わらせるのではなく、露木は自らの発言や働き方を見せることで、露木のエンジニアとしての能力・スキルを知ってもらうことも、意識して行なっています。 −− やはり自ら仕事に対する姿勢や能力を見せることは大切ですよね。 私自身も28歳の時に、平均年齢が40歳の企業をM&Aし、はじめは「若者が何ができるのか」という目で見られていましたが、自ら行動して見せることでみなさんの理解も得られた経験があります。 ■企業文化の融合と経営体制の進化 −−ネットマーケティングをM&Aされる前とM&Aされた後で、どのようなギャップがありましたか。 事業面ではM&A前後で大きなギャップは感じませんでした。 一方、良い意味でギャップがあったことに驚きました。 というのもM&A時、マクビープラネットは創業から7~8年程度で中途社員で構成された企業でしたが、ネットマーケティングは創業から20年近く経つ企業で、企業の歴史が違っていました。 ネットマーケティングのフロントのレベルの高さもちろんですが、コーポレートを含めた組織の力の強さを実感しました。 なので、M&Aによって企業としてのコーポレート・ガバナンス体制の強さを得られたことは、良い意味でのギャップでした。 −− 組織や事業が拡大する中で、コーポレート・ガバナンスを整えるのは重要となりますよね。 M&A後に具体的なコーポレート・ガバナンスで変更したこととしてどのようなことがありましたか。 現在のマクビープラネットのコーポレート・ガバナンス部門のトップを、ネットマーケティングで同じ役割を担われていた方に担当してもらっています。 彼は管理統制にとても長けており、彼の力もあり上場市場のプライムへの鞍替えも行えたと思います。 −− なるほど。一方、M&A先の方がコーポレート・ガバナンス部門のトップを担われることに、マクビープラネットとして懸念されたことはありませんでしたか。 元々、マクビープラネットの経営層は私(千葉)も含め、CTOの露木や執行役員経営企画本部長の川上なども中途入社で役員・執行役員になっている人も多く、特段な懸念はなかったです。 組織体制に限らずですが、マクビープラネットの企業カルチャーの強さとして、より上手くいく方法は積極的に取り入れることで、どんどん変化していき、良い意味で「色」がないことが強さだと考えています。 様々な企業をM&Aしていますが、内部で変に争うのではなく、環境に合わせて変化し続け、グループ全体で伸びていればそれで良い、という考え方で日々向き合っています。 −− 環境に合わせて常に変化し続けているので、M&Aによる組織的な変化もアップデートと捉えられているんですね。 では、マクビープラネットには様々なバックグラウンドを持つ方々が在籍されていますが、成長を遂げられた要因をどのように分析されておられますか。 マクビープラネットの代表取締役社長が創業者の小嶋から千葉に代わったことが、成長を加速するターニングポイントと捉えています。 もちろん、小嶋が代表取締役社長を務めていた時が成長が鈍かったという意味ではなく、マクビープラネットの成長フェーズが変化したという意味合いです。 M&Aで企業をM&Aする際に、小嶋が考えていなくとも、M&Aされる企業からすると、オーナー企業の傘下になるなど、ネガティブに捉えてしまう方もおられるかと思います。 一方、創業者でない千葉が代表取締役を担うことで、一緒にマーケット・業界を変えていくという思いに賛同いただき、環境に合わせて組織や事業なども柔軟に変化していきやすいです。 また、千葉は人材の能力を引き立てることが上手く、様々なバックグラウンドを持つ人が在籍する中で、千葉を中心に各人が得意な能力を発揮できる組織になっているかと思います。 −−マクビープラネットのM&Aを含めた企業成長には千葉さんの存在が大きかったんですね。 マクビープラネットは短い期間の間で、M&Aの多数行っているので、企業カルチャーなどで組織を統率していくことは難しいと考えています。 なので、あくまでも個々の才能を最大限発揮させることを重視しています。 また、M&Aした企業から経営陣を含めた方を迎え入れ、力を十分に発揮いただくためにも、会社として活躍できる環境を整えることを心がけています。 ■競争優位を生む収益モデルと組織戦略 −− 競合企業であるサイバーエージェント社や電通グループ・博報堂グループなどと対比した際、自社の強さをどのように捉えられているのでしょうか。 サイバーエージェント社や電通グループ・博報堂グループは、顧客企業からの報酬体系として、成果報酬よりも固定報酬や手数料報酬を中心に設定していると思います。 一方、マクビープラネットは、成果報酬のみでいただいており、そこが他社と比較した際の一番の違いであり、強みと考えています。 成果報酬と固定報酬の違いをコミットする対象で考えると、固定報酬は成果物を作ることにコミットし、成果報酬は施策の結果にコミットしています。 これは、顧客企業の最終的な売上に対する責任を顧客企業と代理店のどちらが持つか、の違いだと考えています。 マクビープラネットがリスクの高い成果報酬に踏み切ることで、顧客企業はリスクを軽減し投資できます。 結果にコミットするためにリスクを取ることが、マクビープラネットの強みであり、他社との差別化要素と捉えています。 −− なるほど。自社のサービスに自信があるからこそできることですね。 組織面では、他社と対比した際、自社をどのように捉えられているのでしょうか。 サイバーや電通グループ・博報堂グループと比較した際、まず第一に組織規模が全く異なります。 ※ マクビープラネット:159人(連結:2024年4月時点)、サイバー:7,720人(連結:2024年9月時点) 電通グループ:71,127人(連結:2023年12月時点)、博報堂グループ:15,910人(連結:2024年3月時点) 一方、少し尖った表現になりますが、大手企業の広告代理店などは、「人が多い」のではなく、「人が余っている」という認識でいます。 人が余っている組織では、その分の仕事を作る必要があり、否応にも事業領域などを広げる必要も出てきます。 マクビープラネットは一人当たりの生産性や事業領域にこだわることを前提に採用や組織体制を考えているのが、他社と比較した際の組織規模の違いとして現れてると考えています。 −− 各々が生産性高く働ける環境は大切ですよね。先ほども個々の強さを発揮できる環境づくりと仰っていましたが、社員の方々がモチベーション高く仕事に取り組むために心がけていることはありますか。 社員の方々にモチベーション高く働いてもらうためにも、役職・役割を上げられる機会を提供することです。 現状、マクビープラネットは、まだまだ小規模な組織であり、企業としても成長しているので、ポストも空いています。 また、今後もM&Aや採用を行なっていく中で、ポストを用意するためにも、企業として成長し続ける必要があります。 −− では、各人がやりたいことに対して、手を挙げると仕事ができる環境なのでしょうか。 はい、もちろん能力や信頼があることが前提にはなりますが、各人がやりたいことは積極的に取り組める環境です。 また、各人に子会社を設立して、経営をしていきたいという思いがあればできる、それもできる環境であります。 子会社の設立はグループ全体として事業を伸ばすことが主目的ですが、人材育成や人材の引き留めの観点も大きいです。 その際、各人のやりたい思いはマストで、既存事業とは被らない領域であることも必要があると考えています。 また、グループ会社の社長は、その会社の予算もですが、グループ全体を含めた予算を把握する必要があるので、事業計画を作れるかもグループ会社の社長に求められる要素となります。 −− 各人の能力や思い次第で、やりたいことが実現できる環境は素晴らしいですね。 −−マクビープラネットのグループ会社での採用はどのようになされているのでしょうか。 最近は、子会社を作ることも多く、現時点でグループ会社が8社います。(2024年9月時点) 全てグループ会社の採用を本社では行えないので、各グループ会社で分担して採用活動を進めており、グループ会社ごとの採用に関する予算も設けています。 −− HDとグループ会社の棲み分け、グループ会社のマネジメントはどのようになされているのでしょうか。 結論として、適当なバランスで対応しています。 HDとグループ会社を完全に分けて事業を進めていく判断もあるかと思いますが、そのような形式はとっていません。 本体の事業部であると柔軟に動けない場合もあるので、子会社化し各人が裁量を持って事業を運営しています。 −− やはり、HDの部長と子会社の社長は人材育成や組織マネジメントの観点で異なりますでしょうか。 一般的に人の成長の面で、本社の部長よりも、子会社の社長の方が成長すると言われていますが、それは人によると感じています。 一方、子会社の社長になると、その人の人間性が明確に出てきます。 例えば、本社の部長であると、変に自分の城を築き、殻にこもってしまう人が一定数います。 子会社の社長であると自分の城を作ろうとしなくとも、社長であることで自分の城が作れているので、子会社を伸ばすための動きにフォーカスされると感じています。 ■M&Aによる顧客基盤の拡張戦略 −− マクビープラネットの顧客基盤の強みはどういったところにあるのでしょうか。 マクビープラネットの顧客基盤は、証券業界で強く、証券会社であるとほとんどの企業と取引があり、提供サービスの幅も含め、競合他社には負けない自負があります。 もし証券業界の顧客企業の内、中堅企業の数社が他社にリプレイスされたとしても、マクビープラネットのバイイングパワーが強く、形勢は傾かないです。 例えば、アフィリエイトの支援をしている顧客企業が、リスティング広告をしたいとなると、マクビープラネットにご相談いただき、仮にマクビープラネット単体で対応できなくともグループ会社を紹介しマクビープラネット圏内で顧客企業をサポートできます。 これはマクビープラネットの顧客基盤としての証券業界の話に限ったことではなく、広告業界の顧客基盤においては他の業界も同様です。 デジタルマーケティング業界で事業を確立するには、各業界で面を取り、寡占化することが最も重要となります。 −− 業界の寡占度合いで決まるんですね。では、顧客企業からマクビープラネットのサービスが薄い領域を依頼された際はどのように対応されるのでしょうか。 マクビープラネットのグループ内でも対応できる企業がない場合は対応が厳しいですが、ほとんど対応できると言っても過言ではないです。 対応領域を広げるためにも、M&Aを行ってきており、元々マクビープラネットとネットマーケティングは同じデジタルマーケティング業界ですが、異なった領域を扱っていたので対応できる領域はかなり広いです。 −− コンサル業界も似た構造で、経験がない領域の依頼を顧客から受けても、グループ企業やパートナー企業の領域内であれば対応できるので、領域を広げることは重要ですよね。 コンサル業界も似た構造なんですね。 24年6月にPRクラウドテックをM&Aし、デジタルマーケティングの「認知領域」も対応できているようになり、顧客企業から獲得の相談もいただけるようになりました。 PRクラウドテックをM&Aする前は、デジタルマーケティングの「獲得領域」に特化していましたが、PRクラウドテックのM&Aにより「獲得領域」の潜在客を増やすための「認知領域」も対応できるようになっています。 −−なるほど!対応領域が広がるごとに顧客企業との関係性が強くなっていき、企業規模の拡大につながるんですね。デジタルマーケティング業界とM&Aはとても相性が良いですね。 まさに、デジタルマーケティング業界とM&Aは親和性がとても高く、マクビープラネットを違う業界で例えると、エンタメ業界のGENDAのモデルに近いと思います。 デジタルマーケティング業界に属している企業が持っているサービスは素晴らしいものが多いです。 一方、顧客企業の大きな課題を解決するためには、単一のサービスだけでは難しい場合が多いです。 なので、マクビープラネットのグループ会社に入っていただくことで、共に顧客のより大きな課題を解決できるという座組です。 ■ビジョンと繋がりが事業を動かす −− PRクラウドテックは創業当時から業績は順調だったのでしょうか。 PRクラウドテックは創業当初から業績は順調だったと聞いています。 というのも、PRクラウドテックの代表を務められている中島は、元々リクルートや楽天に在籍され、ベクトルでCSOも担っておられました。 中島がPRクラウドテックで、独立されてからも元々の経営者のリレーションがあり案件をいただいていたようです。 −−事業を推進する上で、人とのつながりは大事ですよね。 はい、中島が持たれている人脈はマクビープラネットの経営層の人脈とは異なりとても心強いです。 中島はITバブルのころ、CYBIRD (サイバード)で過ごされておられ、USENの宇野さんなどとも仲が良く、「千葉さんがUSENの人と話したいなら、宇野さんに言っておくよ」なども気軽に仰っていただけます。 また、マクビープラネットの経営層の人脈もそれぞれ異なっており、広い業界・領域をカバーし合えています。 −−経営陣の繋がりも活用し事業の領域を広げられているんですね 潜在顧客の経営陣と会話される際、何か心がけていることはありますか。 デジタルマーケティングなどの専門的な知識だけでは経営者とは対等に会話できず、当たり前のことではあるんですが、相手企業の立場を理解し、経営目線で会話することをいつも心がけています。 一方、会話する内容としては、マクビープラネットの強さであるデジタルマーケティング領域とつなげ、PRや顧客獲得は経営マターになりやすいので、それらに関する課題をヒアリングするようにしています。 たまに経営者との会話の中で、デジタルマーケティングのコアな話になることもあります。 私(千葉)がデジタルマーケティングの現場から少し離れているため、会話についていけないと感じた際は、上段の論点にもっていき、次の商談につなげることも心がけています。 −−他社との提携や共同提案などには取り組まれているのでしょうか。 提案の幅を広げるために、共同提案に取り組もうと思っていますが、実際の取り組みまで至るケースは限られます。 博報堂グループとの取り組みであると、Hakuhodo DY ONEと共同で取り組みを行っています。 博報堂グループは、アフィリエイト広告の分野で、マクビープラネットに相談をいただいており、マクビープラネットとしても提案の幅が広がり、また博報堂グループの顧客基盤と接点も持ちたいので取り組んでいます。 −− 新しい領域や新規事業に取り組む際、M&Aと自社内での立ち上げ、の大きく2つあるかと思います。マクビープラネットでは2つのすみ分けはどのようになされているのでしょうか。 マクビープラネットで新規事業や新しい領域でやりたいことが多いんですが、自社で立ち上げる際、事業や子会社の責任者になる人が限られることが課題となっています。 また、社内で責任者になれる人がいても、既存の業務でパツパツな方が多いです。 なので、M&Aは事業と合わせて、既に成立している組織も合わせて取り込めるので、とても有益と考えています。 先にお伝えした通り「デジタルマーケティング」×「M&A」はとても相性が良く、投資対効果も高いです。 これからも企業の組織環境や外部環境なども含め、M&Aと自社立ち上げを検討していきたいと思います。 −−M&Aした会社の方々がマクビープラネットで働き続けるモチベーションはどういったところにあるとお考えでしょうか。 M&Aの対象となる企業に対しては、「私たちが描いているビックピクチャーに対して、一緒の船に乗りませんか?」と説くことが多いです。 先ほどもお伝えした通り、ネットマーケティングをM&Aした際には、経営陣や従業員の方々から「一緒に経営・事業を行うことで、何か大きなことができるのではないか。」と、ワクワク感を買ってもらい、それがモチベーションになっていると思います。 一方、M&A対象の会社が創業社長の方で、「自分の考えでやっていきたい」と考えられている人は合わないなと感じています。 また、世代や人にもよると思いますが、特に未上場会社の経営者は上場会社で経営することに憧れを持たれている方は一定数おられると考えています。 −−ビックピクチャーに対して、グループ会社で一丸になられているんですね。 また、私自身も上場企業の役員を経験しましたが、役員になる前は上場企業の経営に憧れていた内の一人です。 そうですよね。 より一層事業にアクセルを踏むためやご自身の成長のためにも、他の経営者がいる中で、経営をしていきたいという経営者も一定おられると感じています。 PRクラウドテックの中島は、他にも事業を行っておられ、その事業もマクビープラネットに巻き込んでシナジーを生み事業を進めていきたいと考えております。 −− 上場前にベンチャー・キャピタル(VC)が入ると、高値で売却する必要があると思いますが、M&Aを行う立場としてその観点はどのように考えておられますか。 適正価格でM&Aすること&経営層や社員に還元するためにも、ディール価格を少し抑えて、M&A後のインセンティブを高く設定することを心がけています。 一方、上記の考えを多くのVCが参加するセミナーで話したことがありますが、VCの方からは顰蹙(ひんしゅく)を買ってしまいました。 とは言うものの、VC・PEが入っている企業のM&Aを狙う際は、対象企業やVC・PE、自社のためにも買い方を工夫する必要があり、いずれの組織も利益がある方法を模索しています。 ■企業統合における評価設計・報酬設計 −− HDやグループ会社別に給料テーブルやインセンティブ設計はどのように運用されておられるのでしょうか。 個人的に従業員に関しては、ストックオプション(SO)なども有効と考えるものの、ボーナスの方が強く機能しているとも考えていますが。 給料テーブルやインセンティブ設計は、グループ内で複数存在しています。 グループが増えていくにつれて、考えるべきことも多く、難しくなっています。 ネットマーケティングをM&Aした当初は、統合することを目指して動いていましたが、杓子定規にやってもうまく行かないことが多いです。 なので、現在はM&Aや企業統合をなされている他社などに事例をヒアリングして、日々試行錯誤しています。 −−グループが増えると一律に規定するのは難しいですよね。 全員が納得のいく給料テーブルや評価制度は設計できないと思いますので。 他社へヒアリングされている中で、何か気づきなどはございましたでしょうか。 ヒアリングは、LINEやYahoo!、カルタHDなどM&Aを繰り返してきた会社で、各社のアイディアや経験を参考にさせていただいています。 給料テーブル・インセンティブ設計の観点で、ヒアリングさせていただいた企業の中でも、上司よりも部下の方が年収高いことが平気で起きているとお聞きし、そうだよなと共感していました。 また、上司は部下の年収が高いことも知っており、その状況を許容する人しか組織にいないとのことでした。 マクビープラネットグループに今後も複数の会社が入ってくるとより複雑になるので、グループや各社の元々の制度や設計を残しつつ、ドライに判断する場面も出てくるかと考えています。 −− 部下が上司よりも高い給料であることは、他の企業でも発生していますよね。 今までの当たり前では通用しなくなっているとも感じています。 そうですね。 一方、個社別に給料テーブルやインセンティブ設計は違えど、マクビープラネットグループで社員共通の譲渡制限付株式(RS)を発行するなど、全社一丸となる取り組みは行っています。 −− なるほど。全体的にM&AのPMIにおける組織設計は難易度が高く、無理やり統一しても上手くいかないことが多く、悩ましいですよね。 M&Aでマクビープラネットグループに参画いただく会社が、なぜマクビープラネットグループで一緒にやっていただけるのかを常に意識しています。 お金の面では、マクビープラネットグループは決して高くない金額をM&Aの対象企業にオファーしており、お金以外のキャリア・やりがいなどを目的に参画いただけると考え、私たちも業界を覆していく仲間と意識しています。 また、PMIでは、参画いただく経営者がマクビープラネットグループに入る理由・目的を社員に伝え、納得してもらえることが重要と考えています。 −− そうですね。経営者の理由に納得度・説得度を増すために、あえて一番高い価格でM&Aしないということもありますよね。 それもあると思います。 どうしても高い価格でM&Aしてしまうと、従業員の経営陣に対する見え方が変わってしまうのも、人の心理だと思います。 ■金融機関を味方につける財務戦略 −− ネットマーケティングのM&A時に、フルローンで実行されたのは素晴らしいですね。 なぜフルローンを選ばれたのでしょうか。 フルローンにした理由は、自己資金が潤沢にあるわけでもなく、今後も成長していくために自己資金を確保し、投資の可能性に重きを置いていました。 −−金融機関とのコミュニケーションで意識されていたポイントはあるのでしょうか。 日頃の金融機関とのコミュニケーションを大切にしていて、銀行の担当者も杓子定規ではなく、よりよいM&Aのスキームなど親身になって、我々の味方として考えてくれていました。 また、今後資本調達などする際、その銀行を利用させていただくことも約束していました。 その中で、口約束の企業もありますが、日々の取り引きの中で、マクビープラネットの経営陣であると、やってくれるなと信頼もいただいていたと思います。 他にも企業のM&Aを検討していた時、他社がマクビープラネットの3倍の企業価値を算定しM&Aを実施し、M&Aでは負けてしまいましたが、結果として高値掴みとなってしまっていました。 このM&Aが結果的に、銀行からマクビープラネットのデュー・デリジェンス(DD)の信用度が高まり、より信頼いただけるようになり、今も「マクビープラネットがDDしたM&A案件なら安心して貸付しやすいです。」と仰っていただいています。 −− M&Aの借入にはコベナンツは何か入っているのでしょうか。 M&A対象企業がグループ会社を維持することや金利に対する収益の割合など一般的な範囲で厳しい条件は特段入っていない形です。 日々、銀行の重点クライアントになることを意識して取り組んでいます。 −−日頃の金融機関とのコミュニケーションで意識されているポイントはあるのでしょうか。 銀行や証券会社の担当者と持ちつ持たれつの良い関係性を作ることを意識しています。 金融機関のマクビープラネットの担当者も私たちからの融資が増えると、金融機関内の評価も上がり、担当者も頑張っていただけるし、マクビープラネットとしても大変助かります。 また、例えば人は褒められると嬉しいし、出世意欲が強い人も一定数いるかと思います。 その中で、細かいですが、金融機関の社長が来訪された際に、担当者と良い関係性であることを話すと、社長や担当者も喜んでいただけ、より良い関係性が築きやすいです。 −−やはり、ビジネスの根幹は、人対人の信頼関係が重要になってきますね。 本日は学びが多いインタビューをありがとうございました。 引き続きマクビープラネット のさらなる成長を応援させていただきます! □ (株)Macbee Planetとは Macbee PlanetはLTVマーケティングという消費者のLTV(顧客生涯価値)を予測して広告を最適化し、広告主の成長を支援するコンセプトにより急成長中の会社です。 成果報酬型のインターネット広告で同等規模のネットマーケティング社の買収に合意し規模を拡大。LTVマーケティングのリーディングカンパニーとして市場を開拓。 会社名: 株式会社Macbee Planet 所在地:東京都渋谷区渋谷3-11-11 代表者名 代表取締役社長 千葉 知裕 証券コード:7095 設立日:2015年8月25日 事業内容:成果報酬マーケティング事業 会社情報URL:https://macbee-planet.com/ □ enableXとは 革新的なAIテクノロジーと高度な事業開発の専門性を駆使することで、最適な人数で最高の結果をグローバルに提供する、事業開発ファーム 会社名:株式会社enableX 本社所在地:東京都千代田区麴町3-5-17 晴花ビル 4階・7階 代表者:代表取締役CEO 釼持 駿 設立日:2022年9月 会社情報URL:https://enablex-inc.com/
-
の統合型事業の事業戦略と成長モデル.jpg) ナイル(Nyle Inc.)の統合型事業の事業戦略と成長モデル
ナイル(Nyle Inc.)の統合型事業の事業戦略と成長モデル「ホリゾンタルDX事業」と「自動車産業DX事業」による新たな価値創造 ■ ナイル株式会社 代表取締役社長 高橋 飛翔氏 ナイルは、DX支援やマーケティングを手がける「ホリゾンタルDX事業」と、自動車リース事業「カルモくん」を展開する「自動車産業DX事業」の二つの事業を運営しています。 一見異なる分野に見えますが、ナイルは両事業を有機的に結びつけることで、独自の成長モデルを築いてきました。 ホリゾンタルDX事業で培ったデジタルマーケティングやデータ活用のノウハウは、自動車産業DX事業の拡大を支え、一方で自動車リース事業を通じて得た市場知見がDX事業の精度を高めるという好循環を生み出しています。 さらに、M&A戦略や事業開発を通じて、新たな市場機会を創出し、両事業の成長を加速させています。 本記事では、ナイルがどのように二つの事業を統合し、それぞれの強みを活かしながら新たな市場を開拓しているのかを掘り下げていきます。 PDFファイル URL:http://enablex-inc.com/wp-content/uploads/2025/10/Interview_NyleInc.pdf ナイル株式会社 代表取締役社長 高橋 飛翔氏 ■ 事業運営の特徴とパートナー企業との協業戦略 −− DXやマーケティングなどを提供する「ホリゾンタルDX事業」と自動車リースの「カルモくん」を提供する「自動車産業DX事業」を運営する上で、2つの事業の大きな差分はどういったところにあるとお考えでしょうか。 自動車産業DX事業は、プロダクトを作り込むという観点で、「ホリゾンタルDX事業」よりも市場をより深堀りしていることが、事業を運営する上で大きな差分と考えています。 ホリゾンタルDX事業におけるコンサルティングビジネスは、顧客のマーケティング課題やDX課題に対し適切な助言を行い貢献していく事業であり、顧客数が限定的(数百社)な中で、顧客に合ったものを如何に提供していけるかが重要となります。 一方、カルモくんの場合は、月間で数百件の顕在顧客がいて、リード顧客で言うと月間数千件にも上ります。 自動車を持ちたい方は絶対数が多い分、ニーズが多様化しており、どこからプロダクトを作るべきかを考え、どのような顧客ターゲットに対して、どういった便益を届けていくかを考えていく必要があります。 −− なるほど。顧客層の違いからプロダクトの作り込みが変わってくるんですね。 はい。また、自動車業界は制約や法規制が多くあり、提携先のカーリース事業者、ローン会社などで、既定のオペレーションに新しい内容を追加することは中々に難しいです。 プロダクトを作成する際、どういったターゲットに対して、どんな商品を出すか、各提携先のパートナー企業に対して、どういったメリットを提示するかなどを考えていかないと進みません。 また、自動車業界の歴史は長く、レガシーな企業と一緒に取り組んでいくことにも難しさがあります。 −− やはり、歴史が深いだけ新しい取り組みを推進するのは難しいんですね。 仮にパートナーのディーラー企業の事情を考慮せずに、「顧客のニーズから○○のような機能・サービスがあればいいじゃん。」で進めることは難しいのでしょうか。 機動的に動くのはとても難しいです。 パートナー企業へ「○○のような機能・サービスがあったらいいですよね」と提案することもあるのですが、やはりすぐには取り組めないと言われることは多いです。 −− なるほど。では、カルモくんの事業を立ち上げていく中で、自動車業界やディーラーとの接し方は徐々に理解されていったのでしょうか。 パートナー企業と接する中で、徐々に自動車業界やディーラーの時間軸がわかってきました。 また、事業を進めていく中で、先方にプランを提示すると、「それは○○といった理由でできません。」などとフィードバックをいただくごとに、各社の考え方や特色が整理されていき、刺さるサービスや進め方なども理解していきました。 −− パートナー企業と新しい取り組みを進めていく際、ナイルとパートナー企業のどちらから起案・発信されることが多いのでしょうか。 新しい取り組みを起案するのは、圧倒的にナイルからの発信が多く、ナイルからが9割、パートナー企業からが1割ほどです。 −− パートナー企業と新しい取り組みを協議し、ブラッシュアップされていく中で、先方からどのようなリクエストがあるのでしょうか。 サービスに対する実現可能性などをフィードバックいただくことが多いです。 例えば、まだ実現できていないんですが、「解約違約金のかからないカーリース」のサービスを作りたく、今まで何度も提案し議論してきています。 なぜ「解約違約金のかからないカーリース」を作りたいかというと、途中の解約金・違約金をなくすことで、お客様はカーリースを前向きに検討してもらえるようになるからです。 一方、「中途解約の違約金がかからない。」=「その分の費用が月額に反映される。」ことになりますので、月額に費用が反映された再、今の顧客層に対して逆に売りづらくなってしまう面もあります。 また、パートナー企業からは、既存のオペレーションに加え、新しいオペレーションを追加することとなり、売れる確証性がないサービスに対しては本格的に取り組むことが難しいとフィードバックいただいています。 −− 一般的にも、大手企業と新しい取り組みをする時は、事業に対する確証性や時間軸の違いが生じることが多いですよね。 そうですよね。 一方、時間軸でいうとナイルでは半年で変えられることが、パートナー企業との取り組みでは約2~3年になりますが、パートナー企業に対して、新しい取り組みについての交渉を繰り返していくうちに、先方の理解や動きなども徐々に変わってきていると思います。 比較的早くご対応いただいた例としては、当社向けに提供していただいているリース料金の価格表のフォーマットは変更いただいています。 また、紙の誓約書を完全にオンラインで完結する取り組みは、5年間かけての事例となり、今年(2025年)に変更いただける予定となります。 −− 大手企業のリース会社からすると、ナイルとの提携を通じた新規事業は、先方にとって戦略転換など、何か意義はあるのでしょうか。 大手企業からすると、ナイルとの業務提携によって業績が伸びることには大きな意義は感じて頂けていると思います。 一方で、ナイルとの提携を通じて全社の風土などを変えるなどの影響力を持つまでにはかなり大きなハードルがあると思います。 ■ 事業の意思決定スキームと経営体制の変化 −− ナイルにおける各事業の意思決定の座組や仕組みは、どのようになっているのでしょうか。 ナイルでは、各事業で事業戦略ボードを設定しており、事業部内で意思決定されたものが事実上、企業としての決定事項となる座組で運営しています。 事業の現場で起きていることを機動的に意思決定することを大切にしているので、各事業戦略ボードのメンバーも意図的に変えており、意思決定の座組も各事業に適した形に柔軟に変更しています。 固定メンバーで行ってしまうと、事業の主役でない人が事業の方向性を決めることとなり、判断が遅くなったり、正確性や解像度の低下に繋がります。 例えば、ビール事業に携わっている人が、食品事業に口を出すと、やはり良い意思決定をできないし、食品事業の現場の方々も嫌な思いをすると思います。 −− 現場からの視点を考えると、事業に関りがない人が意思決定には入らない構造は大事ですね。 また経営を多極分散型でやるための取り組みとして、「Nギアス」という経営制度を設けていました。 「Nギアス」は執行役員が増えた2022年から始めた制度で、経営テーマを9つのテーマに分類し、各執行役員がテーマに入り、各ボードの中で機動的に意思決定をするという仕組みで、社長の私が担っていた意思決定を執行役員に委譲しました。 −− 執行役員が各事業のボードメンバーになる仕組みで運用されていたんですね。 制度は上手く機能しているのでしょうか。 現在は「Nギアス」の制度は廃止しています。 今から「Nギアス」を振り返ると、事前の制度のヨミは半分正しくて、半分間違っていました。 ヨミが間違っていた部分として、執行役員のレイヤーと役員のレイヤーに能力や経営経験に差があったことが挙げられます。 ボードメンバーの能力に差がある分、機能している事業戦略ボードと機能していない事業戦略ボードが存在していました。 執行役員が担うレイヤーがグダグダになると、その事業のガバナンスが効かなくなり、事業戦略ボードが機能しなくなります。 −− なるほど。ボードは事業に携わる深さや意思決定の経験、各人の素養などに差が出ますよね。 現在はどのように運営されているのでしょうか。 私と一部の役員が全事業をみるようにしています。 例えば、事業にボードメンバーが5人いる際、2人は固定メンバー、3人は現場メンバーという構成で運営しています。 固定メンバーの2人は、現場ほど事業に触れる機会がないものの、企業全体を把握している観点などから議論や意思決定を行っています。 「Nギアス」を通して学んだこととして、多極分散に振りすぎると逆の効果が出てしまうこともあります。 なので、一部の解像度が高いメンバーが横ぐしで事業ボードを管理し、残りの事業ボードを現場の手触り感があるメンバーに担ってもらう多極分散型で行う運営体制に落ち着いています。 ■ 採用と組織運営の変化 −− 企業の立ち上げ初期にメディア・コンサルを展開されていた時と「自動車産業DX事業」も展開されている現在とで、採用する人や採用プロセスに変化はありましたでしょうか。 新たに事業領域が増えるにつれて、採用したい人の要件は変化していき、今は事業部別に採用要件を定義しています。 また、職種や報酬体系、役割は、人事領域の役員と他数名の役員が集まり、職種と役割に対する報酬は妥当かを議論する場を設けていて、全社的に不透明に給料差が出ないようにしています。 −− 役員陣で採用者の報酬体系の妥当性などを検討されているんですね。 その会議では、採用者の会社へのカルチャーフィットなどもみるのでしょうか。 採用者の会社へのカルチャーもですが、主にバリューマッチをみています。 採用者の報酬体系として、オファー面談シートに、職種や役割、給料に合わせた入社3カ月後・6カ月後・12カ月後に担っていただきたい業務レベルを記載しています。 面談シートに記載ある業務レベルができるまでは報酬はフラットとなり、それ以上の業務レベルになると昇給昇格するシステムになっています。 現状の内定受諾率は80%と高く推移しており、経営層と採用者の給料や報酬体系に対する認識齟齬が起きず、入社されてからも変に給料や報酬体系で問題になることはなく、上手く機能しているかと思います。 −− 採用時点でその方の期待値も伝えられているんですね。 内定者が80%と高く推移されていますが、採用者からはどのような反応が多いでしょうか。 この報酬体系のシステムは、合理的に作られているので、採用者から報酬体系に対する納得度も高いです。 特にサービス業で働かれていた方は、報酬体系がブラックボックスになっていることに悩まれている方が多く、このシステムに対する反応は良い方が多いです。 −− ナイルの立ち上げ当初に入社されてきた方と現在入社されてきている方では、モチベーションにどのような違いがありますでしょうか。 ナイルの立ち上げ当初に入社されてきた方は、事業の「0→1」にモチベーションを高く持たれている方が多かったです。 立ち上げ初期のメンバーの中には辞めた人も、まだナイルに在籍している人もいます。 在籍している人は変わっていく環境の中でうまく適応し、過去をアンラーニングして新たなやり方に順応していく人がほとんどですね。逆に立ち上げのやりがいを大事にする方はやめてより立ち上げ期に近い会社に入社しているように思います。 −− 企業のフェーズごとに従業員のマッチ度合いも変わってきますよね。 そうですね。これは仕方がないことと私の中では許容しています。 もちろん、従業員には各々の人生があり、ナイルでマッチしなくとも他に良い場所があると考えていて、各人の決断や判断に干渉しないようにしています。 −− 現在入社されてきている方のモチベーションはいかがでしょうか。 創業当初と違って、「0→1」のヒリヒリ感はないですが、今あるモノでどのように事業を大きくするか、どのように働くかを考えることに楽しさを見出せる方が多いです。 現在入社されてきている方は、一定規模の人数で業務をすること、既に一定の売上ある事業であることなどを認識されて入ってきているので、業務内容に対する認識違いなどもほとんどありません。 ■ マーケティング戦略と内製化の強み −− 他社のカーリース事業では、マーケティングを外注している企業が多いと考えています。 一方、ナイルのカーリース事業のマーケティングは、自社のマーケティングのノウハウ・ナレッジを活用されており、他社との差別化要素はどうのようにお考えでしょうか。 カーリース事業のマーケティングを自社で行うことによる差別化要素は多数あります。 例えば、マーケティングにかけられる人的リソースが、外注する場合と自社で行う場合に大きく変わります。 外注であるとマーケティング会社に預けた広告費用の割合から当てられる担当者の人数を決めることが多いです。 例えば、お客様の広告予算が1,000万円/月で粗利20%を想定すると、マーケティング担当者の一人月の単価が50万円/月程度となるので、付けられる人数は1人程度となります。 広告予算が5倍の5,000万円になったとしても、マーケティング担当者の人数は5人です。 一方、ナイルの場合は、カーリース事業の広告予算や業務量に合わせて担当者の人数を柔軟に変えられ、根本的に人月の考え方の違いが差別化要素となります。 また、外注すると依頼主と外注先との間の会議や社内稟議の調整など、コミュニケーションコストや間接的工数が生まれてしまいます。 これは内製化することで発生せず、マーケティングの細かなチューニングなども機動的に行え、外注することとの差別化要素となっています。 −− マーケティングにかけられる人員数やコミュニケーションコストなどの観点で、内製化の強さが出てくるんですね。 反対に「自動車産業DX事業」をやっているからこそ「ホリゾンタルDX事業」が強まることもあるのでしょうか。 もちろん「自動車産業DX事業」が「ホリゾンタルDX事業」に与える良い影響も多くあります。 「自動車産業DX事業」に取り組むまでの、メディア・マーケティングに関するサービスはSEOやコンテンツマーケやサイト改善にとどまっていました。 事業として自動車リースに取り組むためには、上記のメディア・マーケティングの施策は当然行った上で、インサイドセールスやリードナーチャリングなどにまで領域を広げる必要があります。 コンサルティング領域も、深く幅広いバーティカルなコンサルティングが行えるようになりました。 また、「ホリゾンタルDX事業」の事業紹介でも、「自動車産業DX事業」で培ったリードナーチャリングのノウハウを「ホリゾンタルDX事業」に活かされていると事業の強みとしてお伝えしています。 −− コンサルティング事業・マーケティング事業だけでなく、自社で商材を扱っていることはお客様にとっても説得力が強くなりますよね。 事業で得られた知見の社内での共有はどのようになされているのでしょうか。 サービスに対するフィードバックを共有する部門をまたいだ共同会議や各人の知見が他の事業でも活かせるように、部門の兼務も推奨しています。 ずっと同じ領域でしていると、考え方が凝り固まってしまうことや、仕事に対するモチベーションの簡単でも一定の領域でレベルが高くなると他の事業に行きたいという人もいます。 一般的には兼務はあまり良くないと言われますが、一定程度組織になじめており、業務に対して新しい刺激を欲していて、既存の業務で結果を出していれば、兼務は良いと考えています。 −− ナレッジを共有するためにも兼務も推奨されているんですね。 また、部門をまたいでサービスのフィードバックを共有することも大切ですよね。 企業規模が大きくなるにつれ、物理的にもお客様の声が共有しにくくなります。 なので、私たちは、意図的にセールスとマーケティングの共同会議は行っており、お客様からのフィードバックを反映させていて、その内容をパートナー企業にも共有しています。 −− 意図的にフィードバックを共有する仕組みは大事ですね。 カーリース事業でマーケティングを内製化しているから生じるデメリットはあるのでしょうか。 マーケティング担当者からすると携われるサービスが限られますので、キャリアプランが設計しにくいことがあります。 また、事業が停滞してしまうとキャリアも停滞してしまいます。 他には、内製化していると受託と違い、顧客企業など外部の方と接する機会が限られてしまい、社内の慣れている方だけのやり取りとなり、自己成長に真剣に取り組める人でないと気が緩みやすいということもあります。 −− マーケティングの担当者は、顧客企業とのやり取りの中で、成長する部分もありますよね。 気が緩むこともあるとのことですが、どのようにして引き締められているのでしょうか。 そこはマネージャー次第だと思います。 社内にシビアにフィードバックできて、自分にも厳しいマネージャーであれば十分に部やチームの気を引き締められると考えています。 一方、マネージャーの社内でのポジションやキャラが、ゆるいものであると引き締めるのは難しいと考えています。 −− なるほど。では、カーリース事業のマーケティングを担当するとなると、担当者の役割や目標はどのように決められるのでしょうか。 カーリース事業のマーケティングチームは、広告全体と各媒体に目指す指標があり、各人の目標というよりもマーケティングチーム全体で目標が設定されています。 ■ 事業成長のターニングポイント −− カルモくんのサービスローンチから6年ほど経ちますが、事業に大きな転換タイミングなどはありましたか。 大きな転換点は、日本で初めて11年という長期の自動車リースをローンチできたタイミングです。 それまでの最長は9年でしたが、ずっと前からパートナー企業にも期間を伸ばしたいことを伝え続けていました。 すると、ある時、パートナー企業の方から「リース期間の延長を検討しますか。」とお伝えいただき、月額を下げるなど試行錯誤することで11年のリースが実現できました。 −− パートナー企業に伝え続けて実現されたサービスなんですね。 リース期間の延長はお客さんへのヒアリングなどで欲しいと言われていたのでしょうか。 いえ、お客さんから直接は言われていないです。 リース期間を延長し、9年リースで月額を下げて提供していても、価格が高いと言われていました。 それならばと、11年リースであると月額がもっと下げられるので、サービスの作成に至りました。 −− ローンチされてからのお客様からの反響はいかがでしたでしょうか。 11年リースの反響は高く、現在はリース契約の約6割が11年リースで契約いただいています。 −− すごい盛況ですね。他にお客様からのヒアリングから付加したサービスなどはありますか。 アフターサービスもお客様からのフィードバックから付けたサービスとなります。 立ち上げ当初はアフターサービスがなく、サービスを展開していく中で、お客様から「メンテナンスサービスなどはないのでしょうか?」とお聞きいただくことあり、立ち上げから約1年でアフターサービスを提供し始めました。 −− アフターサービスもお客様からの気づきだったんですね。 ローンチ当初から事業・サービスの改善・改良はどのようになされていたのでしょうか。 ローンチ初期は、カーリース事業はあまりうまく行っていませんでした。 実際、サービスを2018年2月にリリースしましたが、初めての契約が2018年4月なので、振り返ってもスロースタートだったと思います。 ローンチ当初は、お客様からの質問やフィードバックの全てが我々が備えていないものばかりで、お客様の声を聞いて必要ならばすぐ開発していきました。 大手企業では市場にローンチして、一定期間の経過をみてから次の手を考えるなどの教科書通りの動きもありますが、ベンチャー企業はそうはいかないことが多いです。 やはり、日々、お客様からの声や意見と社内で仮説として考えていることを加味して、事業をアジャイル的に瞬発力を使って、細やかにチューニングしながら進めて行くことは意識してやっていました。 −− アジャイル的に事業を推進されていたんですね。 ローンチ後2ヶ月間売れなかった時から、成長軌道に乗った要因はどういったことろにあるとお考えでしょうか。 成長軌道に乗った要因には、いろんなものがあります。 例えば、「営業メンバーのセールスオペレーションの改善」や「契約が取れそうな時にどのように契約を処理するかのバックヤードのオペレーションの改善」、「広告・マーケティング施策」など、全てが成長軌道に乗る要因となっています。 なので、どれか単一の事象がというよりも、その時々に必要なこと全部をやり切ったことで、事業が軌道に乗っていったと思います。 −− なるほど。では、ローンチ当初の低空飛行期間では、「根本的にサービスがイケていないのでは?」などと懐疑的に思うことはなかったのでしょうか。 「サービスがイケてないのか?」と思うこともありましたが、反対に「上手くいく」という思いも強く持っていましたので、続けられていたと思います。 −− 自分たちのサービスを信じるのは大切ですよね。 ローンチ当初の固定費用はどの程度かかっていたのでしょうか。 固定費は賃借料と人件費のみで、従業員が5~6人でしたので、月200~300万円程度でしたので、コストの面はなんとか踏ん張れていました。 ■ M&A戦略とその狙い −− 24年7月にパティオをM&Aされましたが、どういった意図でM&Aされたのでしょうか。 車をオンラインで買う消費者は少数派であり、オフラインのリアルな面を持っていた方が集客面や既存のオンラインのカーリース事業でも相乗効果があると考え、M&Aに至りました。 また、自社でもオフラインでディーラー事業を行っていた時期もありました。 自社での経験も経て、自前では中々上手くいかないと理解し、M&Aしかないと考えました。 −− 自社でディーラーのリアル店舗事業を展開されていた時期があるんですね。 自社では上手く行かなかったポイントはどのようなところにあるのでしょうか。 上手く行かなかったポイントは「仕入れ」です。 ディーラー事業の要となるのは「仕入れ」で、オークションや店頭で仕入れるにしても、物凄くノウハウが必要になり、車がどの程度の価格で売れるかなどの目利きは長年の蓄積からくる職人芸です。 ディーラー事業が上手くいくかどうかは「仕入れ」に尽きると思います。 −− ディーラー事業では、仕入れが最も重要なポイントなんですね。 ディーラー事業の集客は、特段な問題はなかったのでしょうか。 集客は、大手プラットフォームである「グーネット」や「カーセンサー」などを使いこなせれば上手く行えていました。 −− 集客は仕入れほどの課題にならないんですね。 では、リアル店舗のディーラーのM&Aを検討され始めたのは、いつ頃からでしょうか。 上場前は上場審査があったので、M&Aは行えなかったので、上場した直後から探し始めました。 M&A先は自分たちで探していて、パティオを知った経緯は、大手のM&Aプラットフォームのサイトで、初めてアポを入れた企業がパティオでした。 パティオのM&Aを検討されていた企業は、ナイルの他に4社ほど競合企業がいましたが、交渉の末M&Aにいたりました。 −− M&Aの候補となる企業はご自身たちで探されていたんですね。 パティオのリアル店舗事業は、既存のカルモくんのオンラインカーリース事業とどのように関わっているのでしょうか。 パティオとカルモくんの事業は、連携して進めています。 例えば、パティオで仕入れた在庫をカルモのオンラインデータと連携させて、リースとして販売もしており、その逆もあります。 他社の在庫を販売するよりも、自社の在庫を売った方がグループとして拡大できます。 また、パティオとカルモくんの事業をまたいだクロスセルも行えています。 例えば、パティオのリアル店舗では、人が限られることから車を販売したお客様に、その場でメンテナンスサービスなどの案内を行うことは難しいです。 一方、パティオでご購入いただいたお客様に、定期的にカルモくんのメンテナンス・修理サービスをご案内することで、顧客との接点も増え、受注件数も伸ばせます。 −− 以前、成長速度を担保するには、自社でアセットを抱えないことが大切と仰っていましたが、リアル店舗事業で在庫を抱える不安はございませんでしたか。 やはり、在庫を抱えることは事業を進める上での要モニタリング事項であるべきかと思います。 在庫として300日以上抱えているものなどは元本割れのリスクが懸念されるので、ルールを作り何カ月抱えているものは損切でも売る仕組みを整備しています。 −− パティオとナイルは事業の面で、リアルとオンラインで異なり、カルチャーも違ってくるかと思いますが、どの程度企業カルチャーや人事制度は統合されているのでしょうか。 企業カルチャーは異なりますが、ナイルの企業カルチャーに揃えてしまうとM&Aしたことの意味が薄れてしまうと考えています。 パティオはパティオの企業カルチャー、ナイルはナイルの企業カルチャーとして、お互いに敬意を払って企業を運営しています。 ナイルとパティオの関係は、連邦国家のように「グループ間で合理性のあることは協業して進めていく。」という握りがあるだけです。 例えば、パティオは創業から28年間同じ経営者が経営をされていたので、ナイルから見て合理的でないこともあります。 客観的に考えて、合理的でないことは、取締役としてナイルから私(高橋)を含めた2名が入っているので、パティオの方々と一緒にアップデートしていっています。 −− M&Aを実行されてから、難しいと感じられたところはありますか。 M&A後は特段難しいと感じることはなく、今のところ出来過ぎるくらい円滑に事業を進められています。 −− 上手く進められているんですね。 M&Aのデュー・デリジェンス(DD)の時から、パティオとコミュニケーションがとりやすいかなどは見られていたのでしょうか。 DDの際、パティオの人や組織がナイルとマッチするかはみていましたし、反対にナイルの人や組織がマッチするかも見てもらっており、当時の代表の方とも密にコミュニケーションをとっていました。 また、カーセンサーやグーネット、Googleのパティオの口コミもみていましたね。 一方、パティオの社員の方々がITツールをどの程度使えるか、社員の方々のモチベーションなどは実際にM&Aするまではわかりませんでした。 −− M&A前は情報の取り扱いがセンシティブなので、現場の社員の方とは実際にお会いするのは難しいですよね。 そうなんですよね。 なので、覆面調査として、お客さんとしてパティオの店頭に行き、従業員の方々がどのような方かをみたりしていました。 また、M&Aを実行するまでわからなかったことで、最もドキドキしていたことは、新しい代表の方についてでした。 M&Aを実行するまでは、創業者の前代表の方から、新しい代表にM&Aの話をするのは、M&Aを確定した時にして欲しいと条件として言われていました。 創業者のその意図としては、先に新代表と話して、万が一社内に広まると現場が混乱してしまう可能性があるからでした。 −− 新しい代表の方と会話せずにM&Aを決断されたんですね。 新しい代表の方がどのような方かわからないリスクはどのように乗り越えられたのでしょうか。 本当にドキドキでしたが、最悪のケースになった場合、創業者に再度戻ってもらえたらいいかと考えて、M&Aに踏み切りました。 一方、M&A前に想定していた最悪ケースと真逆で、新しい代表の方が非常に能力もあり人格も良い方で良かったです。 −− なるほど。M&Aは実際にやってみないとわからないことが多くありますよね。 ■ ナイルのポジショニング戦略 −− 自動車業界の中で、様々なポジショニングが考えられるかと思いますが、ナイルのポジショニングはどのようにお考えでしょうか。 自動車業界の小売の領域はやり切りたいと考えています。 今興味ある領域は、業販(B2Bの自動車売買)や下取り買取などです。 −− 自動車の小売なんですね。自動車以外の他の産業は想定されていますか。 目下は、自動車産業でやり切ろうと考えています。 自動車産業は、圧倒的にTAMが大きいので、簡単に取り切れるものでもありません。 自動車産業でまだまだやり切れていませんし、投資回収も行えていないので、利益回収をしていきたいです。 −− 「ホリゾンタルDX事業」の成長戦略はどのように考えられておられますか。 「ホリゾンタルDX事業」は、商材の幅を広げ、B2B向けの法人支援のソリューションをひたすら作っていこうと考えています。 また、一般的にSEOは過小評価されていると思っていて、私たちはSEOのコンサルティングにも注力しています。 検索のボリュームの観点で、SEOはマーケティングオートメーション(MA)やチャットボットよりも圧倒的にSEOの方が多いです。 消費者は検索する際、現状はSNSかSEOくらいであり、SEOを窓口にして顧客にサービスを提供することは、マーケティングの観点で非常に良いと考えています。 一方、SEOだけでは顧客企業の中期的な成長に貢献できるのは限定的なので、SEOをフックにして様々なソリューションを提供していくことで、顧客企業の中でナイルのプレゼンスを上げていきたいと考えています。 −− 私もSEOは過小評価されていると考えていました。 私の友人にSEO事業を売却した人がいるんですが、その方に「もう一度事業をするなら?」と聞くと、「トラフィックも落ちていないので、もう一度SEOメディアを立ち上げる。」と言っていました。 新しいマーケティング手法に注目が集まりがちですが、B2C・B2BのSEOはまだまだいけると考えています。 中村さんも同じ考えなんですね。 SNSはマッチする領域がかなり限定的だと考えています。 例えば、Instagramは、ファッションやエンタメ、化粧品などの領域では効果的ですが、自動車は売れません。 一方、現時点ではSEOはどの領域の会社でも無関係にはいられません。 −− そうですよね。マーケティングの領域ではどのようなラインナップを増やしたいとお考えでしょうか。 企業向けに生産性を高めるための生成AIを活用した領域は注目しています。 また、実行支援の領域も興味があります。 一部のコンサルティングファームと似たモデルになりますが、人を派遣して顧客企業の仕事をサポートする領域に参入できればと考えています。 −− 実行支援の領域にも目を向けられているんですね! 派遣型のビジネスは社員の採用と教育など組織力が問われる事業になるかと思いますので、今後また違ったナイルの姿をみられるのが楽しみです! □ ナイルとは 会社名:ナイル株式会社(英文名 Nyle Inc.) 所在地:東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F 代表者:代表取締役社長 高橋 飛翔 設立日:2007年1月15日 会社情報URL:https://nyle.co.jp/ 会社名:株式会社enableX 本社所在地:東京都千代田区麴町3-5-17 晴花ビル 4階・7階 代表者:代表取締役CEO 釼持 駿 設立日:2022年9月 会社情報URL:https://enablex-inc.com/
-
 TWOSTONE&Sons の強さの源泉:やり切る組織力と事業成長戦略
TWOSTONE&Sons の強さの源泉:やり切る組織力と事業成長戦略■ TWOSTONE&Sons 代表取締役 COO 高原 克弥 氏 TWOSTONE&Sonsは、エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニーです。 TWOSTONE&Sonsでは、優れた組織力を活かして事業を推進し、その組織力は「やり切る力」を基盤に構築され、営業力やマーケティング力といった「強さ」として現れています。 創業当初の試行錯誤を経て、自社の得意領域を明確にし、既存事業や新規事業の成長を加速させています。 本記事では、組織力の本質的な強さ、事業運営の哲学、新規事業における挑戦と失敗、さらには責任者に求められる素養について、どのようにして持続的な成長を実現しているのかを紐解いていきます。 PDFファイル URL:http://enablex-inc.com/wp-content/uploads/2025/10/TWOSTONEsons.pdf TWOSTONE&Sons 代表取締役 COO 高原 克弥氏 ■ TWOSTONE&Sonsの強さの根源 −− 本日はよろしくお願いいたします。 (株)TWOSTONE&Sonsは、国内でエンジニアプラットフォーム事業を中心に多数の事業を展開され、2023年6月にホールディングス体制に移行し社名を(株)Branding Engineerから(株)TWOSTONE&Sonsに変更されたことも記憶に新しいですね。 お話をお伺いするのをとても楽しみにしていました。 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 −− 早速ですが、初めにTWOSTONE&Sonsの強さの根源を紐解いていきたいと思い、高原さんが考えるTWOSTONE&Sonsのコアとなる能力はどのように認識されていますか。 当社の本質的な優位性は、データベースとして優秀なフリーランスエンジニアを常に集められていることだと捉えています。 また、そのデータベースを最大限に活かし、調理し切れる「組織力」も、私たちの強さだと認識しています。 そして、そのデータベースを活かした組織力を紐解くと「マーケティング力」「営業力」に現れていると考えています。 組織力を高めるためにも、実力があり成長意欲が高い人材が活躍できる環境を提供することが重要だと考えていて、グループ会社の役員に任命するなど、当社グループという場を活用することでキャリアの幅が広がり、深さも追求できる組織設計にしています。 また、10社以上あるグループ会社の中でも互いに競い合い、個や全体として組織力を高めていっています。 インセンティブの面でも、給料としての対価だけではなく、株式やストックオプションなどを提供することで、事業に向き合うパッションを高めるインセンティブ設計を取り入れています。 −− 組織力を高めるためにインセンティブ設計にもこだわられているんですね! 上場企業において、インセンティブとして、株式やストックオプションを当社のように積極的に出している企業は限られていると思います。 株式やストックオプションを持つことで自分が活躍した分だけお金として還元されることが原動力となり、社員の事業への日々のモチベーションも高められていると思います。 また、インセンティブに限らず株式を活用した調達やM&Aに取り組まれていない企業も多いと感じています。 −− なるほど。事業としての組織力の強さはどのようなところにあるとお考えでしょうか。 共同代表である当社代表取締役CEOの河端も言っていることですが、エンジニアマッチング事業を実務レイヤーに落とし込むと、どの企業も本質的には違いがないと考えています。 その環境の中での差別化要素として、「やり切る力」が当社の事業としての「組織力」の強さであり、それが「営業力」や「マーケティング力」として現れていると考えています。 一見、表面的には単一に見えるサービスでも、段階ごとに詳細に分解し、「やり切り要素」を細かく洗い出します。 その「やり切り要素」をどれだけやり切れるかを全グループ会社のオペレーションレイヤーまで徹底して行っています。 なので、経営の立場からは、オペレーションレイヤーに対して、「これをやり切るぞ!」というシンプルなメッセージで伝えることを心がけています。 −− 「やり切る力」からくる「組織力」、そして組織力から成される「営業力」「マーケティング力」が強さなんですね。 そうです。 例えば、クライアントから案件に対して、何か提案して欲しいと相談をいただいた際、数日や数時間後に提案するのではなく、相談をいただいてから何分以内に提案する、など全員の当たり前の基準を高め、徹底的にやり切る組織を作っています。 また、受注率を高めるために、お客さまが資料請求されてから次の動作に移るまでのスピーディな架電も徹底しています。 なので、資料請求から架電までの時間を1秒でも短縮するために何を「やり切るか」を常に考えており、経営からオペレーションレイヤーへ目標を伝える際には、一貫してシンプルな目標を伝えるようにしています。 スピーディなコールがしっかりと徹底されているかを確かめるために、上長がお客さんとして資料請求し、目標時間以内に電話が来るかの確認もしたりしています。 −− エンジニアのデータベースはどのように捉えられているのでしょうか。 当社が多数の事業を立ち上げる中で、エンジニアのデータベースは、様々なモノ(事業・サービス・プロダクト)を作り出す事業開発力と捉えています。 。 ■ M&Aを含めた組織力とその戦略 −− 「やり切り力」が最終的な差別化要素になっているんですね!では、強い組織を作るにあたり、どのような評価制度を運用されているのでしょうか。 人事評価として「やり切れること」が当たり前になるような評価制度をとっています。 少し違和感があるように聞こえるかもしれませんが、人事評価では結果しか見ていません。 結果は出しているが、「やり切れていない人」は評価されない制度になっています。 人事評価で役員陣で会話する内容としても、「〇〇は十分やり切れているか。」なども論点として上がっています。 −− TWOSTONE&Sonsは多数の事業を展開されていますが、事業やサービスの企画はどのようになされているのでしょうか。 正直に企業としての「企画機能」は「営業」や「マーケティング」と比較して弱いと捉えています。 なので、今でもマンパワーとして役員陣やボードメンバーが企画を担っており、良い事業やサービスがあれば、河端か私と事業の責任者を選定し形にしています。 −− 企画はボードメンバーが担われているんですね。TWOSTONE&Sonsはエンジニアマッチング事業の企業を中心にM&Aも積極的に行っていますが、PMIで重視されている要素などはあるのでしょうか。 グループインする企業の弱みの改善は難しいので、強みを数倍に伸ばすことをPMIでは心がけています。 また、多くの競合SES企業を上回る採用や営業ができるように、そこを中心に強みで伸ばしていくことを考えています。 例えば、実際にグループインしたA社は、CEOの採用のグリップ力が強く、初回面談からの内定承諾率は以上に高かったんです。なので、初回面談の数を増やすことにリソースを全振りし、採用数を伸ばしました。 また、リソースを1つに集約すると、他でほころびも出てきますが、そこは強みをみんなで補完しながら事業を進めています。 企業に何か突出した強みやスゴイことがあっても、リスクを考慮しやり切れていない企業は多数あると考えています。 私たちは、「出来ないことはできない」と割り切り「確実なモノにリソースを張り、今ある強みを高める。」ことを意識し、事業を推進しています。 −− グループインする企業の強みや弱みは、グループイン以降に見えてくるのでしょうか。 いえ、グループイン前から企業の強みや弱みは大体わかり、「〇〇を伸ばせば企業価値が高められる。」などと当社内で仮説を持っています。 また、企業単体で強みを伸ばせない時は、既存のグループ会社や当社のコアとなるエンジニアのデータベースなどと掛け合わせることで、事業を拡大することもあります。 −− では、TWOSTONE&SonsがあまりM&Aを検討しない企業の領域や特色などはあるのでしょうか。 M&Aを検討しない領域でいうと、企画力や市場環境やニーズに合わせて細かくアジャストする機動力が求められる領域は当社の優位性が発揮できないため、検討しない領域となります。 例えば、D2Cなどは検討する領域とは逆サイドの領域になります。 私個人としてはD2C領域は好きなので、実際に創業時は当社でもD2C領域に参入していたことがあります。 一方、事業拡大を考えるに当たり、組織力として現在の強み(マーケティング力・営業力)とD2Cに求められる企画力・機動力を両立することは厳しいと考え、D2C領域からは撤退しました。 しかし、既存の事業や組織と分けて、事業を推進すれば企画力・機動力を強みとした新しい事業も拡大できると考えています。 また、D2C事業に関して、今となっては笑い話になりますが、D2C事業に参入していた時期が上場準備をしていた時で、海外商品を扱っていました。 しかし、商品の管理が適切ではないことを証券会社に指摘され、上場時期が遅れたこともありました。 −− 自社の組織力を客観的に捉えて、事業領域も選定されているんですね。 現在、従業員数が500名以上おられますが、従業員が増えるにつれ組織の強みを捉えにくくなったり、コントロールしづらくなるなどはありませんか。 組織規模が大きくなるにつれて、逆に強みがわかりやすくなり、コントロールもしやすくなりました。 その理由として、事業を絞ったことにあると思います。 特に創業当初などは、当社の強みを把握できておらず、事業を手あたり次第なんでもやっていて、例えば不動産なども手掛けてました。 −− 組織が拡大されるにつれて「強み」を把握されていかれたのですね。 そうなんです。 事業を進める中で、冒頭でもお伝えした通り、当社の得意領域(=強さ)が、「やり切る力」からくる「組織力」、そして、その組織力から生み出される「営業力」と「マーケティング力」であると理解し始めました。 「マーケティング力」だけでは頭でっかちになりやすく細かなことが徹底できず、「営業力」だけでは筋肉質過ぎて一点突破は得意ですが、戦略や計画が間違った方向性であると上手くいきません。 「営業力」と「マーケティング力」のどちらかを強みとしている企業は多数あると思います。 当社は「営業力」と「マーケティング力」の両方が強みで、掛け合わせられることが私たちの優位性だと考えています。 ■ TWOSTONE&Sonsの新規事業に対する考え −− 今後、さらに組織や事業を成長させるための、新たな取り組みなどはどのように考えられておられますか。 組織や事業を成長させるために、あまり新しいことはやらない方が上手くいくと考えています。 取り組む内容として、BetterよりMustを徹底しています。 新しい施策や取り組みを行う際は、提案者や企業と十分に議論した上で、当社としてMustな事象にまで落とし込めなければ取り組みません。 −− 組織やオペレーションの面で、新しいことではなく、既にあることに集中されているんですね。 マーケティング会社を経営している私の知人も同じことを言っていて、その会社でもABテストはほとんど行わないらしいです。 やった方が良いこと(≒Better)は無限に出てくるので、費用対効果が合いにくく、Betterなことではなく、やらなければやばいことになること(≒Must)を見分けることが大切と仰っていました。 色々なことを取り入れると、スピーディなコールなどの大切なことが疎かになり、やらない言い訳も出てくるので生産性の観点でも良くないと考えています。 −− 新規事業や企画は役員陣が取り組まれているとのことでしたが、社員からボトムアップで立ち上げられることはあるのでしょうか。 新規事業や新しい企画を、社員のアイディアをボトムアップで取り上げ、立ち上げることはほとんどないです。 従来まで取り組んでいたことはありますが、結局立ち上がらなかった事業が多く、役員陣が新規事業や新たな取り組みを企画しています。 −− ボトムアップの形式は取られていないんですね。では、河端さんや高原さんはどのように新規事業や企画のアイディアを得ているのでしょうか。 河端や私は、友人や経営者同士の飲み会など外部の人との会話の中で、事業のタネをみつけることが多いです。 新規事業を始める基本スタンスとして、当社の強みである「営業力」か「マーケティング力」のどちらかに他社が苦戦されている領域があれば、当社が参入しゴリっとやれば行けるだろうと考えています。 −− 経営者など日々事業に向き合われている方は、今々の業界や領域の課題やトレンドを最前線でみられているので、参考になることが多いですよね。 新規事業として参入し、上手くいかなかった事業などはありますか? 小さい規模の事業まで含めると、上手くいかなかった事業は山ほどあります。 例えば、今では撤退していますが、過去には先述の通り不動産事業にも参入したことがあります。 不動産領域は、参入前に事業の成長ドライバーとなる要素は、「マーケティング力」だと考えていました。 一方、不動産領域への参入後、事業の成長ドライバーは「不動産の仕入れ」であることがわかり、「マーケティング力」が活かしきれないことがわかり撤退しました。 −− 参入前の当初の成長ドライバーの仮説が実態と異なっていたんですね。 そうです。 撤退するに至ったのは、領域の特性を見極めず勝ち筋がないまま参入していたところにあります。 領域ならではの特性がある中勝ち筋が見つけられなかったため、当社が得意としていたマーケティングが全く使えず、不可能とは言わないまでもあらゆるところに課題がある状況でした。 ゲームで例えると、無課金の半そで短パンの装備で強敵に挑んでいるような感覚でしたね。 課題が無数にある中で、新しい領域をそこまでしてやる意味がない、という結論に至り撤退しました。 −− TWOSTONE&Sonsで参入しないと決めている領域はあるのでしょうか。 継続的に儲かる事業ではなく、一発ドカンと儲かる事業、例えばインフルエンサーマーケティングなどは参入しません。 短期的には利益を得られるかもしれませんが、事業が3年間安定的に伸びる事業でなければ、オペレーションや組織も混乱してしまうので、中長期的な健全な企業経営を優先しています。 また、リスクの観点から、先方の後払いが生じる事業は、先方の不良などにより、売上が立たないことや収益化が遅れる可能性があるため参入しないです。 −− 着実に儲ける事業に絞られているんですね。では、事業の撤退基準などはあるのでしょうか。 着実に数年で伸びると判断した事業に参入していますが、1~2年で初期の仮説通りの伸びが得られなかったり、ブレイクスルーが見えない場合は撤退します。 要するに、事業に参入し、わかりやすい勝利の方程式(「〇〇〇をこうやって、△△△すれば事業は拡大する。」)が見えてこない際に撤退しています。 −− 事業の立ち上げの際、誰がどのような体制で取り組まれるのでしょうか。 河端か、私(高原)のどちらかと責任者(1名)で立ち上げています。 事業立ち上げで、重要になってくるのは、責任者選びで、「能力」はもちろんですが、どれだけ「パッション」を持っているかをみています。 「能力」は言わずもがなですが、その業界・業種の経験やノウハウが必要となります。 「パッション」に関して、新規事業は最初から方程式が見えれば良いんですが、伸びがわかるまで時間がかかります。 なので、事業の可能性がみえるまで如何にくらいつけるか、その「パッション」が責任者に最も重要な要素になります。 ■ 事業責任者に必要な素養 −− 責任者には「パッション」を重視されているんですね。パッションある人の採用や会社に在籍し続けるために、どのようなことを意識されているのでしょうか。 どのようにすれば、パッション溢れる人材が採用できたり、会社に居続けてもらえるかは、正直なところまだ明確にわかりきれていないです。 一方、ホールディングスが全面に出るのではなく、事業を伸ばすことの面白さをみんなでシェアし、競い合い称え合える環境が大事だと考えています。 自分で起業するよりも、やりたい事業ができる環境があれば、その人にとっても当社での仕事が楽しいと思い、居続けてくれると考えています。 いろんな意味でタフな人であれば、河端や私を含めた役員陣も価値観をシェアしやすく、お互いにより高め合えると思っています。 また、それぞれの事業が拡大してさえいれば、それ以外のところは自由となっています。 逆に事業が拡大していなければ、従業員の給料も伸ばせないし社会的意義も意味がないとも思っています。 −− 一般的に新規事業は利益が生まれるまで、コストセンターとなり、既存事業の方からクレームなどが起こる場合もあるかと思いますが、どのように対応されていますか。 当社の新規事業は、お金を使う新規事業はやらないので、既存事業の人から「自分たちが生んだ利益を食いやがって。」などといったクレームは出てこないです。 また、新規事業が伸びる方程式が見えてからもですが、費用は人件費以外、最低限しか投下していない事業が多いです。 −− TSSファンド(旧:BEファンド)はどのような背景で設立されたのでしょうか。 河端や私が友人や経営者同士の飲み会など外部の人との会話の中で、面白い事業の案件が入ってきて、伸びるから当社でやってみようとなり、出資プロジェクトである「TSSファンド」を設立しました。 −− 新規事業と同様な形で設立されたんですね。戦略的には活用できているのでしょうか。 投資事業としてピュアに投資をしていますが、既存の事業とシナジーを生むなど戦略的にはなかなか活用できていないです。 ファンドを通じて色々な情報は入ってきますが、既に河端と私の経営者のつながりなどから情報はある程度ある状態です。 CVCで企業に投資しても減損してしまうことも多く、またシナジーも見込むことはかなり難易度が高いと感じています。 上場会社がCVCをやるメリットはあまりないのではないかと感じています。 −− 企業投資は専門性も高く難易度が高いですよね。事業責任者の「パッション」で印象的なエピソードなどはありますでしょうか? 当社としては、少し特異な事業領域になりますが、強みである「営業力」と「マーケティング力」を活かし、接骨院領域でクリニックと患者のマッチング事業を行っています。 この事業の責任者は森口という者が担っています。 森口は元々、当社がM&Aしたメディア企業の代表でした。 当時のメディア事業を取り巻くマーケット環境が悪化し、新しい事業にチャレンジしたいとのことから、マーケティングと営業力を活かした接骨院領域のマッチング事業を担ってもらうことにしました。 事業は良い感じに伸びていたんですが、交通事故の件数が年々減ってきており、患者とのマッチング市場自体が限定的で、業績の観点からも事業の上限に達している感覚にありました。 一方、森口は「こんなのが事業の上限ではない」と強く信じていて、接骨院がどの程度儲けているのかなど解像度を高めるために、直接接骨院に足を運びヒアリング調査に行きました。 すると、接骨院が1人のお客さんを集客するにあたり、接骨院がいくら儲けられているかがわかり、一人当たりの送客単価を上げられることがわかり、早速事業に活かしました。 −− 自ら足を運んで、市場調査し、事業を拡大できたのはパッションのたまものですね。 本日はTWOSTONE&Sons の強さの根源や新規事業に対する考え方など学びが多いインタビューをありがとうございました。 引き続き(株)TWOSTONE&Sons のさらなる成長を応援させていただきます! (写真左)enableX 中村 陽二氏、(写真右)TWOSTONE&Sons 代表取締役 COO 高原 克弥氏 □ TWOSTONE&Sonsとは エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社BrandingEngineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場(現:グロース市場、証券コード:7352)へ新規上場。 2023年6月1日に、「株式会社TWOSTONE&Sons(ツーストーンアンドサンズ)」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。 グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。 会社名:株式会社TWOSTONE&Sons 所在地:東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル6F 代表者:代表取締役CEO 河端 保志、代表取締役COO 高原 克弥 証券コード:7352 設立日:2013年10月2日 事業内容:ITを活用したサービス事業 会社情報URL:https://twostone-s.com/ 革新的なAIテクノロジーと高度な事業開発の専門性を駆使することで、最適な人数で最高の結果をグローバルに提供する、事業開発ファーム 会社名:株式会社enableX 本社所在地:東京都千代田区麴町3-5-17 晴花ビル 4階・7階 代表者:代表取締役CEO 釼持 駿 設立日:2022年9月 会社情報URL:https://enablex-inc.com/